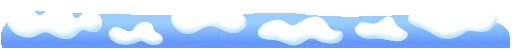ブルーランドマスター
緑川 とうせい
1/11ページ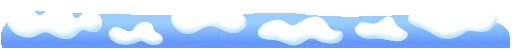
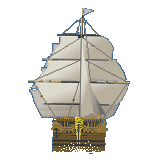
■1■ 出帆
バルドス島は、マロック海に浮かぶ騎士団の島である。
マロック海は、別名「青い宝石」とも呼ばれ、どこまでも続く青い海面に大小さまざまな諸島を擁し、その景観は文字通り宝石のように美しい。
そこに浮かぶ切り立った岩の島、バルドス島。半ば要塞化したこの島には、海の監視人「アナトリア騎士団」の騎士たちがいる。島の周囲の海域は、「海賊航路」という忌まわしい名称でも知られ、パトロールの軍用ガレー船が航行し、堅固な城塞の塔の上からは、マスケット銃を背負った見張りの騎士が不審船に目を光らせている。
物見の塔に通じる回廊からは、朝日に照らされてサファイアブルーに輝く海原が一望できる。波が岸壁にぶつかる響きと、かもめたちの鳴き声を聞きながら、島の騎士たちは毎日目を覚ますのだ。
今、その石造りの回廊を、二人の騎士が歩いていた。
それぞれ腰に剣を差し、騎士団の印であるライチョウを模した十字が縫い込まれたローブ姿で、急ぎ足で回廊を歩いてゆく。そのうちの一人は、ローブの下に赤い胴着を着込んで、日焼けした顔に口髭をたくわえた、精悍な騎士である。
「お前は、ここに来てからどのくらいになるのだった?」
「はい。隊長どの。島に来てから五日ほどになります」
答えたのは、こちらは白い肌に金髪の、まだ若そうな騎士だった。
「なるほど」
隊長らしいその騎士は、納得したようにうなずくと、目を輝かせるその若者を横目で見やった。重要な任務が始まろうというこの朝に、緊張と不安に顔を曇らせずにすむというのは、よほどの豪胆者か、あるいは経験のない新米だけだ。島に来て五日目では、まだ観光客のようなものに違いない。
「これからすぐに出航だというのに、お前は怖くはないのか?」
「いいえ。楽しみであります。船に乗りたくて、私はこの島への配属を願ったのです」
「ふむ。名は確か……グリンといったな。何歳になる?」
「二十一になります」
「若いな」
隊長騎士は、かつての自分の姿を見るようなまなざしを若者に向けた。
「銃と剣は使えるのだろうな?島に来る前はどこにいた?」
「はい。騎士団の本部では、造船所の方でガレー船の櫂職人の手伝いや、漕ぎ手応募者の審査係などを主にやっておりました」
「なるほど。実戦経験はなしか」
「しかし、先月の騎士団内の剣技会では六位に入りましたし、銃の方も……マスケット銃の扱い方などはひととおり習いましたので」
「それはもちろん。ここに来る以上、ある程度の書面での審査があったはずであろうから、お前の能力にはさほど心配はしない。しかし、やはり海上での実戦は別だからな」
「分かっています。船のことは色々と造船所で習いましたし、ガレー船の漕ぎ手も試しにやったことがあります。大砲の撃ち方も……空砲でしたが、経験しております。なにもかも上手くやる自信はあります。海賊どもなど怖くはありません。ここに来てまだ日は浅いですが、初めての海上任務に就けることを、今からとても楽しみにしております」
希望と情熱に輝くその目を見て、隊長騎士は年長者特有の落ち着いた笑みを浮かべた。
「ふむ。しっかりやれよ」
「はっ」
若い騎士は、自らを鼓舞するように拳を握り、大きくうなずくと、潮風の香る回廊を隊長について歩いていった。
港は夜明け前から出航の準備におおわらわだった。
桟橋に整列した騎士たちが、沖合に停泊した二隻のガレオン船に乗船するため、次々にボートへ乗り込んでゆく。
真新しい白と青の船上服に、士官帽をかぶった若き騎士は、出航前の署名を書きおえて、緊張の面持ちでそこに並んでいた。
「お前か、グリンという新米は」
署名係の男が、奇妙な目つきでこちらを見ていた。
「へえ、綺麗な白い顔をして。まるで丘の上のおぼっちゃんだな」
それを聞いて、並んでいた他の騎士たちもげらげら笑いだした。「金髪のおぼっちゃん。船の上にゲロ袋はもっていくのかい?」
背の高い一人が、馬鹿にしたように彼の背を叩いた。思わずかっとして振り返り、彼は相手を睨み付けた。
「なんだ、そのツラは。年長の先輩騎士様に向かって、文句でもあるってのか?」
相手の顔を見上げ、グリンは静かに言った。
「歳は下かもしれないが、私は騎士として選ばれた。もしあんたが下甲板の船員なら、海の上では私の命令を聞くべき立場にある」
「なんだと、この……」
とたんに男は眉をつり上げ、つかみかかってきた。
それを予期していたグリンは、相手をひょいとかわし、腰の剣に手をやった。
「面白え、やんのか?このガキ」
獰猛に歯をむき出し、男は細身の剣をすらりと抜いた。それを見て、グリンも鞘から剣を抜く。
「やれやれ」
「やっちまえデューン」
「そんなガキ、のしちまえよ」
周りにいた騎士たちが二人をけしかける。
「勝手につっかかってきた新米の若造を少々痛めつけたって、おとがめはねえからな。あやまるなら今のうちだぜ?ええ、ぼうや」
片手に細身の剣を構え、男はにやりと余裕の笑みを見せた。
「つっかかってきたのはそっちの方だろう。それに……俺はぼうやじゃない、グリンだ」
勇敢に言い返した彼だったが、思わぬ事態になってしまったことに、いくぶんの不安を覚えていた。
「……」
胸の鼓動が早くなる。
剣の腕にはそれなりの自信があったが、試合以外での実戦……ましてや決闘などは、これまでに一度もしたことがない。
(もし、相手が打ちかかってきたら、こちらも手を出すしかない)
だが、グリンの緊張をよそに、男は剣を構えたまま動こうとしない。
「まてよ。グリンっていったな?」
何事かを思い出したように、男がつぶやく。
「お前、下の名前はなんという?」
「……」
グリンはぐっと口を引き結び、相手を睨んだ。
「ちっ。おい名簿係。そこに書いてあるだろう。こいつの名前を読んでみろ」
「は、はい……ええと」
名簿係が慌てて紙を広げ、なぐり書きされた名前の列を指で追う。
その間、二人は剣を構えたまま向かい合い、その周りに集まった野次馬たちも、これから起きる事に注目するように、じっと黙り込んでいた。
「ああ、あった。ありました。ええとグリン……、」
名簿係はそこまで読むと、そこにある重大な意味にようやく気づいたように、さっと顔つきを変えた。
「どうした?早くこいつの名前を読め!」
「は、はい」
騎士に急かされて、名簿係がうなずく。
「あの……グ、グリン……、グリン・クロスフォード……」
その名前を聞いた瞬間、男は剣を構えたままぎゅっと眉を寄せた。
「……」
おずおずと、名簿係の男がグリンを指さした。
「クロスフォードというと、あの、もしかして……」
「クロスフォード……、そりゃたしか……」
「ああ、……そうさ」
周りにいた野次馬たちもざわめきはじめる。
かちり、と音がした。グリンに向けられていた剣が、鞘に戻されていた。
「はっ……。そういうことか」
「おい、デューン。それじゃやっぱり、そいつは……」
仲間に声をかけられ、男は吐き捨てるように言った。
「ああ、我らがアナトリア騎士団総長、ジョージ・クロスフォード……の、せがれだろ」
それを聞いた周りの男たちから「おお……」と、驚きの声が上がる。
グリンは、口元をぐっと引き結んで立ち尽くしていた。このような形で注目されることに、彼にはまったく耐えがたい気分だった。
「……」
剣をしまった男は、もうグリンには見向きもせず、さっさと船着場へと去っていった。
「もう……行っていいか?」
そう訊くと、名簿係はさっきとはまるで違う態度で、「もちろんです。どうぞ乗船を」と、その歪んだ顔にいやらしい作り笑いを浮かべた。野次馬たちが視線を注ぐ、その中をかき分けるようにして、グリンは歩きだした。
ボートからガレオン船の甲板に上がると、高々とそびえる三本マストの向こうに晴れ渡った空が見えた。
水平線の向こうまで流れてゆく白い雲。潮の香り、かもめの鳴き声さえもが心地よい。
(ああ……、ついに僕は、騎士として船に乗り込んだのだ)
次々と食料や水樽が船に運び込まれ、続々と騎士たちがボートから梯子を伝って乗り込んでくる。その様子を、まるで人ごとのようにぼんやりと眺めながら、グリンはこれから始まるだろう冒険に思いを馳せ、その心を高ぶらせていた。
だが、それも長くは続かなかった。錨が上がり、船員たちの手で手際良く帆が張られ、ついに船が港を出航すると、それからほんの半刻もたたぬうちに、彼はひどい吐き気のため、げっそりと顔を青ざめさせることになった。
「知ってのとおり、今回の任務は、ガルタエナまでの商船の護衛任務である。我がディスカバリー号に乗り込んだ諸君たちの中には、これが初めての航海となる者もいよう。船の上では規律を重んじ、全員が一体となって仕事にあたるべきことを忘れぬよう」
沖合に出た船が航路上に落ちつくと、ディスカバリー号の船員たちは甲板に集合した。艦長の言葉に耳を傾けるのは、航海長をはじめ、二十名ほどの騎士たち。彼らは紋章の入った群青色の胴着と白いズボン姿で、腰に剣を差し、マスケット銃を手に、一段高い後部甲板に整列している。
その他の一般船員たちは、皆真っ黒に日焼けをして、たいていは汚れたシャツにズボンという格好で、中央甲板から騎士たちを見上げている。八十名ほどいる彼らの仕事は、主にマスト張りや荷物運び、船倉の水の汲み出し、そして戦いの時の大砲の押し出しや白兵戦などで、多くは騎士見習いか、雇われた民間の船乗りであった。
それ以外には、医師、船大工、書記、長い航海の場合はこれに料理人や理髪師、それに食料係、樽職人などが乗船することもある。
「往復三日ほどの短い航海であるが、全員が気を引き締めて、無事に任務を遂行することを願うものである。騎士団とバルドスの誇りの上に」
「騎士団とバルドスの誇りの上に!」
騎士たち、船員たちは一斉に唱和し、それから各々が己の持ち場へと戻ってゆく。
そんな中にあって、一人青い顔をしていたのはグリンであった。今にも倒れそうなその様子に、そばにいた仲間が声をかけてきた。
「おい、大丈夫か?」
「あ、ああ……」
よろめくグリンは仲間の肩を貸り、船内へ続く階段を降りた。
ガレオン船の内部は何層かに仕切られており、用具室、食料、水樽の貯蔵室の他に、艦長室、医務室、それに船員用の船室がいくつかと、それぞれは狭いながらも多くの部屋がある。長い航海のときには、数年の間もここで暮らせるようにと、考慮されているのだ。
かつてのアナトリア騎士団は、陸上からの海峡の監視や、病院活動などがその主な活動であった。だが、いつのころからか海賊を拿捕した功績とともに、彼らに対しての「海の警護者」という認識が世間に広まると、今回のような商船の護衛任務が増えていった。
以後、毎年多くの者たちが、騎士としてガレオン船に乗り込むことを夢見てバルドス島にやってくる。実際に騎士となるためには、水夫としての訓練を受け、航海術と算術を学ばなくてはならないし、剣と銃の腕も試される。その全てを通過した者のみが、栄えあるアナトリアの騎士として叙されるのだ。
騎士たちと海賊の戦いの記録は、いつしか伝説となり、多くの若者たちを魅了し続けた。群青色のチョッキに尖った帽子をかぶり、後部甲板に立って颯爽と指揮をとる騎士たちの姿と、大海原を舞台に海賊との戦いに生きるという壮大なロマンは、いつの時代にも少年たちの心をざわめかせずにはおかないのだった。
「うう……うええ」
かつては、そんな憧憬を胸にしていたであろう若き騎士は、今は死人のように青ざめた顔をして、ハンモックに倒れ込んだ。
「おい、しっかりしろよ。まだ出航したばかりだっていうのに」
手を貸してくれた仲間の騎士が、グリンに水を差し出す。
「ほらよ。一口飲んだらしばらく横になっていろ。今のところはまだ忙しくはないから、お前一人くらい甲板にいなくとも、誰も変に思わないだろう。航海長には黙っててやるよ」
「ああ……すまない」
「じゃあ後でな」
船室に一人なると、グリンはぐったりと目を閉じた。水を飲んだせいか、吐き気も多少はおさまったようだ。
「くそ……」
自分の情けなさに腹がたった。
せっかくの初めての海上任務だというのに、ずっと憧れだったガレオン船に乗り込んだとたん、このざまとは。
(丘の上のおぼっちゃんか……)
乗船前に言われた言葉が頭をかすめる。
たしかに、自分には実戦の経験も、実際の航海に出た経験もない。だから、それらを求めてバルドス島に転属を希望し、こうして念願の周航任務に就いたのだ。それなのに……
(情けないな……まったく)
どこまでも広がる青い海を、大きく帆を広げて颯爽と進むガレオン船。太陽を浴びて輝く緑の諸島。迫り来る大嵐……海賊船との遭遇。鳴り響く大砲の音、そして、恐るべき海賊船長との決闘。
少年の頃、物語や伝説で聞かされた、それらの武勇伝に憧れ、いつかは自分の船で大海原を駆け巡りたいと、そう夢見ていた……
(だが……現実はこれか)
グリンは自嘲の笑いを浮かべた。
はたして、無事に最初の航海をまっとうできるのだろうか。不安ばかりの初任務となってしまった。
「おい、起きろ。おい」
体を揺り動かされて、グリンははっと目を開けた。どうやら眠り込んでしまったらしい。
「大丈夫か?気分はどうだ」
さっきの仲間が自分を覗き込んでいた。
「あ、ああ……だいぶいい」
「そいつはよかった。お前、初任務なんだろう。なら無理もないさ。俺も初めてのときは変にはしゃいじまって、行きは良かったが帰りは甲板で三度も吐いたっけ」
栗色の髪の若い騎士はにやりと笑った。
「俺はスウェン。バルドス島に来て二年目だ。よろしくな」
「俺はグリン……」
「知っているよ。グリン・クロスフォードだろう?さっき港の桟橋でそう聞いたよ」
「ああ……そうか」
二人は握手を交わした。
「まあ、船の上じゃ、どこの誰だろうと関係ないからな。せいぜい航海長の癇癪には気をつけようぜ。まあ、俺達は一般船員じゃあないから、すぐに鞭打ちにはならないだろうが、その分給料から引かれちまうからな」
そのとき、甲板の方から笛の音が聞こえてきた。
「お、いけねえ。そろそろ定時連絡の頃だ。だから起こしに来たんだよ。お前も来いよ。砲門のチェックの後でミーティングとメシの配給だ」
スウェンの手を借りてハンモックから降り立つと、気分はだいぶよくなっていた。
後部甲板に上がったグリンは、ロープを手に力仕事に追われていた。新米の騎士は、一般船員とともにマスト引きをするのが、この船のならわしであった。
「よし、引け!」
掛け声とともに、船員たちが一斉にロープを引っ張る。
これは思いの外重労働で、じりじりと照りつける太陽の下、甲板に足を踏ん張り綱を引き続けていると、背中や顔からはどっと汗が吹き出して、喉がからからになる。これが順風になると、たたんだ帆を綱を引いて広げ、また風が変わると、今度はヘッドマストに三角帆を広げて、それを引っ張りまたたたむのだ。そんな仕事を繰り返していると、もう船酔いどころではなくなった。
「どうだい?汗をかくのも気持ちいいもんだろう」
「ああ、まあな……」
友人になったスウェンとともに、グリンはひと休みしながら穏やかな海原を眺めた。
「風向きも良好。この分だと夕方までにはガルタエナに着けるぞ」
彼の言う通り、ディスカバリー号は護衛する商船とともに、西日に光る波間を、滑るようにして進んでいった。
モルグ岬を越えると、目的のガルタエナはもう目と鼻の先だった。
「進路、南東、微南四分の一」
「南東、微南四分の一。ようそろ」
航海長の指示と、操舵手の復唱が甲板に響く。
ほどなくして、見張り台から騎士が声を上げた。
「見えました。ガルタエナ湾です」
日が傾きはじめ、気温が下がったこともあって、海上には霧が出てきていた。ディスカバリー号の船員たちは、船の先に広がるガルタエナ港の風景を甲板の上から眺めていた。
「さすがに、停泊している船は十や二十ではきかないな」
「そりゃそうさ。貿易商人たちにとっては、ここはマロック海で最も重要な交易拠点なんだからな」
物知り顔でスウェンが説明した。
「だから、自然と俺たちの任務もこの港へ来るのが一番多いのさ。俺はこの二年間でもう十回は来たぜ」
赤く染まりはじめた西の海を背後にして、ディスカバリー号はゆるゆるとその速度を落とした。
湾内は水深が浅くなるため、喫水の深い大型船はこれ以上は入ることができない。先にゆく商船を見守りながら、騎士団のガレオン船はここで停泊することになる。
「ここまでくれば、もう任務は完了したも同じさ。湾内に入ってしまえば海賊は手出しができない。もし襲ってきたら、ここにいる俺たちと港からの警備隊と、その両方に挟まれるわけだからな」
スウェンの説明に、グリンはややつまらなさそうにうなずいた。船酔いとロープ引きとで終わった、冒険とは無縁の初航海であった。
「さて、俺たちも上陸の用意をしようぜ。今夜は町でうまい飯が食えそうだ」
甲板からガルタエナ港の灯を見やりながら、二人は最後のマスト引きに加わった。
帆をたたんだディスカバリー号は、錨を下ろし、港に船腹を向ける恰好で停泊した。護衛してきた商船、ノークライム号は、そのままゆったりと湾内を進んでゆく。
「よし。我々もジョリーボードで港へ向かう。二十名ずつ、三隻に分かれて出発だ。残りは船の警戒にあたれ」
艦長の指示に、甲板の船員たちは隊列を組み、縄ばしごでボートへ降りてゆく。先発隊に入ったスウェンは、次の隊列に並ぶグリンに向かって手を振った。
「それじゃ、お先にな。陸に上がったら町へ飲みに行こうぜ」
甲板上の残った騎士たちは、砲門の前にで周辺の警戒を続けていたが、彼らうちの半ばは、みな安堵の面持ちだった。二十四門もの旋回砲を湾の内外に向けていれば、もはや襲撃されることはないだろう。なにより、喫水の深い大型船は湾内に進入することはできないのだから。見張りに立つ騎士たちは、誰もがこっそりと、久しぶりに港の酒場で飲める新鮮なラムパンチやバンボウ酒のことを考えていたに違いない。
艦長を含めた先発隊のボートが船を離れてまもなく、マスト上で帆を縛っていた船員が、甲板に向け手を振った。
「おおい。向こうから船がくるぞう」
騎士たちが霧に曇りはじめた湾外に目をやると、見慣れない一隻の船が、ゆるゆるとこちらに近づいてきていた。
「ふん小型のスループ船だな。見たところただの商船のようだが、念の為だ、砲門を向けておけ。旗は見えるか?」
「はい。間違いなく商船のようです。ガルタエナの船乗り組合の旗が見えます」
「そうか。よし。警戒はおこたるなよ」
艦長からしばしの指揮を任された副長がそう命じる。
スループ船はゆっくりと接近してきて、ディスカバリー号のすぐ横を通過してゆく。その甲板には、乗客らしい人々がこちらに手を振っているのが見えた。派手な帽子にマント姿の紳士や、着飾った婦人、それに子供らしき姿もあった。
「ふん。身なりのいい連中だな。きっと金持ちを乗せた商人の船かなにかだろう」
「騎士団の船が珍しいんでしょう。おっ、ドレスの美人がこっちに手を振っている」
思わず甲板の騎士たちも手を振り返す。
スループ船が湾内へ入った。と同時に、パーン、という銃声のような音が響いた。
「なんだ?」
周りを見渡しても、とくに何かが起こったわけでもない。騎士たちが不審そうに顔を見合わせる。
スループ船が速度を上げていた。先発隊のボートを追い抜き、港に向かう商船、ノークライム号へ近づいてゆく。
「おい……なにが」
見守る騎士たちの前で、いきなりドーン、という大きな轟音が上がった。次の瞬間、ノークライム号のマストが吹っ飛んだ。
ディスカバリー号にいる騎士たちは、はじめ何が起こったのか分からなかった。皆あっけにとられたように、呆然としている。
「海賊です!」
最初に叫んだのはグリンだった。
「海賊が現れたんです。さっきのスループ船です。あれは海賊船だったんです!」
「なんと……なんということだ」
副長が呻いた。みるみるその顔を青ざめさせる。
今や速度を上げたスループ船は、マストを破壊されて立ち往生しているノークライム号に接舷しかけていた。
「むう、旋回砲用意!」
「駄目です。先発隊のボートがちょうどスループ船と我々の間にいて、今撃てばボートが転覆します」
「くそ。なんたる……とにかく、帆を上げろ。錨も巻き上げろ。すぐに動ける準備をするんだ」
副長の命令で、船員たちが大急ぎでマストの縄を引きはじめる。だが、あろうことか、肝心のヘッドマストの帆へつながる縄がどこにもなかった。
「ヘッドマストの縄が……切られています」
「なんだと?」
船員が切られた縄の先を見つけた。ほんの少し前まではまったく異常はなかったはずだ。
「これは……いったいどういうことだ」
困惑する艦長の横で、グリンが「あっ」と声を上げた。
「さきほどの銃声は……もしかして」
「銃だと?馬鹿な……銃でこんな細い縄を狙ったというのか?船の向こうから」
副長は、馬鹿馬鹿しいというように首を振った。確かにどう考えても、マスケット銃で狙い撃ちできる距離ではない。
その間に、スループ船は回頭してこちらに向かってきていた。あの船の狙いがいったいなんだったのかは皆目分からないが、このまま湾を出て逃げるつもりらしい。
「とにかく戦闘体制だ!砲門も準備しておけ。それから、誰か銃を持って戦闘楼へ上がれ」
ディスカバリー号の甲板上はにわかに慌ただしくなった。
砲門を引いてくる者、マストの縄を補修する者、銃に弾を込める者、錨を巻き上げる者……どちらにしても、騎士たちの半分ほどはまだボートから戻らず、絶対的に人手が足りなかった。
グリンもマスケット銃を背負い、戦闘楼に上った。いまやスループ船は、船体から砲門を突き出した戦闘体制で接近してきていた。
「ジョリーロジャーは見えるか?」
「いいえ。あ……待ってください、今上がりました」
ジョリーロジャー、つまり海賊旗は、それぞれの海賊団によって異なった絵柄を持っている。一般的には「頭蓋骨に交差した骨」というのが主流だが、それぞれの海賊の趣向によって別の図柄が使われており、商人たちは、凶悪として名が知られる海賊の旗が相手船のマストに見えただけで震え上がった。
「赤……、赤い旗です」
「赤だと?模様は?」
「模様はなにも……。ただ赤い、細くて長い旗がなびいてます」
「なん……だと」
甲板に立つ騎士たちが言葉を失った。艦長以下の船員たちも、みな青ざめた顔でそこに立ち尽くした。
「ジェーンレーンだ。女海賊……ジェーンレーンだ」
近くで誰かがつぶやいた。それを聞いたグリンは、ぶるっと背筋を震わせた。
「女……海賊?」
その言葉にはなにか、ひどく魅惑的な響きがあった。それは、少年の頃に聞かされた、海賊たちの伝説を思い起こさせるような……そんな幻想的なものを思い起こさせた。
(海賊……あれが海賊の船なのか)
これは夢ではない。自分は今、本物の海賊船を見ているのだ。
やや不謹慎な感動に身を震わせるグリンの前で、スループ船はすでにディスカバリー号の鼻先を抜けようとしていた。
「くそっ。砲門を船首に持ってこい!」
後部甲板で指揮をとる副長が叫んだ。しかし、船員たちは錨の引き上げとマストの補修に追われ、重い砲門を引いてこられるだけの人数は余っていなかった。
赤い流旗をなびかせた海賊船は、もはやそれをただ見送るだけの騎士たちをあざ笑うように、鼻先を通り抜けてゆく。
「……」
戦闘楼からそれを見ていたグリンは、何を思ったか手にした銃をその場に置くと、さらに上にあるてっぺんの見張り台に上っていった。
(よし、ここからならよく見えるぞ)
見張り台に立つと、甲板がひどく小さく見えた。本来高いところが得意なわけではなかったが、グリンは何故か恐怖を感じなかった。
(あれは……)
目を凝らして海賊船を見やると、あちらの船の戦闘楼にも人影が見えた。ここからでは、その顔まではわからなかったが……
かすかに、長い髪がなびいた。
(赤い……髪?)
西の海に沈みゆく夕日に照らされて、燃えるような赤い髪をなびかせている、その人影……
グリンはそれを食い入るように見つめた。
さきほど聞いた名が、自然と脳裏にこだまする。
(ジェーンレーン……)
(あれが、女海賊……ジェーンレーン)
何故かそれが確信できた。
しばらく時間が止まったかのように、彼の視線は海賊船の戦闘楼へ、吸いよせられるように注がれていた。
「何をしている!撃てっ、撃てっ」
甲板では、さっきから副長の怒鳴り声が響いていた。
どーん、どーん、とガレオン船の大砲が続けて火を噴く。しかし鉛の砲弾は、敵船の手前で失速し、次々に海面に水しぶきを上げるのみだった。
海賊船は、そのまま悠々とディスカバリー号から離れていった。相手船からの砲撃は一発として上がらなかった。それは、まるで無駄なことはしないとばかりのスマートさであった。
離れてゆくその船の姿を、グリンは見張り台の上からじっと眺めていた。汗ばんだ両拳を握りしめ、頬を紅潮させながら。
(ああ、行ってしまう……)
彼は知らず、激しい胸の高ぶりを覚えていた。
それは「海賊」という、かつて物語の中でしか知らなかった存在を、自分は確かに目撃しているのだという、少年のような純粋な感慨だったかもしれない。
スピードを上げた一本マストのスループ船が、霧の向こうに消えてゆくまで、騎士団の砲弾はひとつとして、その役目を果たすことはなかった。湾内に残されたのは、こちらの大砲による数知れない水しぶきと、帆の上がらないガレオン船、それにようやく船にたどり着いた騎士たちの乗るボートだった。
■次ページへ