ブルーランド・マスター
2/11ページ
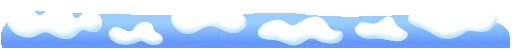
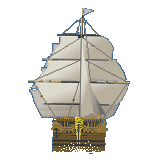
■2■ 海賊討伐作戦
ディスカバリー号の騎士たちは、誰もかれもが海賊船の逃げ去った方向を見つめて、呆然と甲板上にたたずんでいた。
銃を手にしている者も、ようやく錨の巻き上げを終えて座り込んでいる者も、そして彼らに指示を与えるはずの副長までが、何も言葉を発せず、ただその場につっ立っているだけだった。
先発隊のボートが戻り、艦長をはじめとする騎士たちが甲板に上がってきたところで、彼らはようやく、今起こった出来事を現実として受け止めたのだった。
「やられたな」
船に戻った艦長の第一声がそれだった。
「は……はあ……」
副長はそうまぬけな返事をしただけだったが、艦長はそれを怒るでもなく、すぐに冷静に指示を下した。
「とにかく、襲われた商船に向かう。怪我人がいるかもしれない。船は動かせるか?」
「あ……それが、その」
言葉を濁す副長の横に、見張り台から下りてきたグリンが近づいてきて、艦長に事の次第を説明した。
「なんだと?ヘッドスルーのロープが?」
「はい。おそらく……銃で狙い撃ちされたと思われます」
「本当なのか?」
にわかに信じがたいという表情で艦長が問い返す。隣で、「よけいなことを」と言うかのように、副長がじろりとグリンを見やる。
「いえ、まだはっきりしたことは。それに、いくら名うての海賊とはいえ、船の向こうから銃弾が届くはずは……」
「確かに。そんな神業のようなことが……いくら赤毛のジェーンの一味とはいえ」
(赤毛の……ジェーン)
グリンは心の中でその名をつぶやいていた。
騎士団の間でも、その名は相当に有名なものらしい。甲板の他の騎士たちも、敵船のマストに見えた赤い流旗について、さっきからあれこれと噂しあっている。
(では、戦闘楼にいたあの人影は、やはり赤毛のジェーンその人だったんだろうか)
そうに違いない。きっとそうだと思いながら、グリンはそれについては報告をしなかった。
腕を組んで考え込む艦長の横で、副長は両手を広げて言った。
「おそらく、切れたロープはすでに腐食していたのでしょう。他に考えようがない」
それにグリンは反論した。
「いえ、自分は確かに聞きました。はっきりと銃声を。そして、その後でロープが切られていたのです」
「偶然だ」
副長は笑いながら首を振った。グリンはなおも反論しようとしたが、艦長が目でそれをなだめた。
「もう済んだことはどうでもよい。それよりも、とにかく、一刻も早くマストの修理を。それから商船に向かい船員の救助だ」
「はっ。アイ・サー」
命令を受けた副長が指示を出しに離れると、艦長はグリンに向き直った。
「さて、ところで君の名はなんといったかな?」
「はい。グリンです」
グリンは直立して敬礼した。
「よし、ではグリン君、君も来たまえ」
「はっ」
夕暮れの迫る海面は、西日をうけてきらきらと輝いている。
ボートに乗り込んだ十数名の騎士たちが、息を併せて櫂を漕いでゆく。グリンは、後方に離れてゆくディスカバリー号を見ながら、さきほどの海賊船のことを考えつづけていた。
彼らは商船を装ってこちらを安心させ、湾内に入ると素早く獲物に近づき、そしてあっというまに去っていった、その手際の良さはまったく感嘆に値するものだった。しかも、こちらの船が即座に動けぬよう、マストのロープを狙い撃つなどということは、信じられない芸当である。
(だが……あの距離ではマスケット銃の弾は届かない)
前に座る騎士の動きに合わせて櫂を漕ぎながら、グリンは考えた。
(かといって、スナファンス拳銃では、命中率は上がるが、そのぶん射程は短い)
では、いったいどうやっても海賊はこちらの船のロープを切ることができたのか。それは魔法にしか思われなかった。
(赤毛の女海賊……ジェーンレーン)
その名前を思い浮かべる度に、想像は物語のように広がってゆく。ロープを絶ち切った魔法もそうだが、あのスループ船の戦闘楼に見えた人影も、グリンの想像をかきたてた。
(ジェーンレーン。いったいどんな顔をしているのだろう)
その正体を確かめたいという思いが、自分の中でどうしようもなく膨らんでゆくのである。
ボートが商船に横付けされた。メインマストを無残に破壊され、なすすべもなく浮いているだけの船に降り立った騎士たちは、すぐに負傷者の搬送を始めようとしたが、驚いたことに襲われたノークライム号には怪我人はほとんどいなかった。調べてみると、怪我をしているものといえば、砲弾を受けて飛び散ったマストの破片が運悪く当たったという数人くらいで、しかも彼らは皆軽傷であることが分かった。
次に騎士たちは、海賊によって掠奪されただろう積み荷を確かめに、商船の船長に案内を請うて船倉へと降りた。だが、ここでも驚くべき事実が待っていた。船倉には、積み荷である酒の入った樽や、香辛料の入った箱が整然と並んだままで、まったく掠奪された形跡などはないのである。
隊の指揮を任された騎士は、首をひねりつつ船長に尋ねた。
「奪われたものは何だ?」
背の低い、ずんぐりとした船長は、困ったような顔をして、こう言った。
「その……あのう……とくにありません」
「なんだと?」
その場にいた騎士たちは顔を見合わせた。海賊船に襲われて、何も取られなかったなどということが、はたしてありうるだろうか。しかし、確かに船倉には賊の足跡ひとつなく、積み荷の箱は一つとして、開けられたり動かされたような形跡はないのだった。
その後、商船の船員全員が甲板に集められた。「この船に海賊が降り立ったのを見たものはいるか?」という問いに、船員たちは皆首をかしげた。
「見たような気もする」というものもいれば、「海賊らしい者は見なかった」というものもいた。ただし、「小型のスループ船が近づいてきたと思うと一発大砲を発射し、船のマストが吹き飛び、その後甲板上は大騒ぎになった」という状況については、誰もが同様に「そうだ」とうなずいた。
結局、このいかがわしい海賊の襲撃に関しては、「海賊は何もとらずに逃げた」という結論に達した。何度確かめても積み荷に異常はなく、海賊を目撃したという船員も現れなかったので、騎士たちは商船の船員たちをボートに乗せ、彼らを港まで運ぶという任務についた。
マストの壊れた商船については、とりあえず応急修理が終わるまではここに停泊し、ガルタエナ港の他の船を借りて、積み荷をそちらに移すという手筈となった。船を去り際に、あることが気になっていたグリンは、海賊船の戦闘楼に赤い髪の人影がいなかったかと船員たちに尋ねたが、誰もそれを見たものはいなかった。まったく謎だらけのこの事件に、騎士たちはみな、まるで狐につままれたような顔で船に戻ったのだった。
ディスカバリー号の補修は今夜中に可能だろう。一応の任務を終えて、騎士たちは、今夜は港町でのんびりと過ごすことになった。
彼らは陸に上がると、船乗りたちで賑わう酒場や、娼婦たちが手を振る裏通りの徘徊を楽しんだ。ラム酒を飲み、久しぶりの海ガメの焼き肉に舌鼓をうち、他の船の船乗りたちと仕事や女の話などをしながら、陽気に笑い、踊るのだ。任務の後の陸でのひとときは、彼らにとって、短い息抜きの時間であるのだった。
グリンも酒場での時間を過ごした後、スウェンや他の仲間に誘われ、娼婦街に出掛けていったが、それほど酒に強くない彼は、すでに数杯のラムパンチでふらふらになっていた。
いつの間にかスウェンたちがいなくなっていることにも、てんで気づかぬありさまで、グリンは朦朧としながら女の声を聞いた。
そして、気づくと朝になっており、彼は自分が見知らぬベッドで寝ていることを知った。見ると、自分の隣には薄い金色の巻き毛の女が、シーツにくるまってすやすやと眠っているではないか。
「……」
何度か目をしばたいたグリンは、「あっ」と声を上げ、ベッドに起き上がった。
「あら、起きたの?」
眠たそうに目をこする女から飛びすさるように離れると、彼はようやく自分も裸であることに気づいて、床にちらばっていた服を急いで身につけ始めた。
「あんた、若いのね。ふふ……はじめてだったの?」
「な……な、」
グリンは真っ赤になった。
昨夜のことはまったく記憶にない。いったい、スウェンたちはどこへいってしまったのか。
「あなたのお友達なら、昨夜はそれぞれ別の女と部屋に入ったわよ。あんたは酔っぱらっていて、もうぐてんぐてんだったから、あたしが手を引いてここに連れてきたってわけ。銀貨二枚ちょうだい」
女は豊満な体を恥じらいもなくさらしながら、グリンに向けて手を差し出した。
「な……な、お、俺……」
自分が何をしたのか、まるで覚えていなかった。まさか見知らぬ女を、無意識のうちに抱いたというのか。混乱する頭でいくら考えようとしても、ずきずきとひどい頭痛がそれを許さなかった。
「はやくぅ」
「あ、ああ……」
とにかく一晩とめてもらったのだし、金を払ってさっさと出ていこう。それにボートに乗り遅れたら大変だ。
グリンは仕方なく女に金を渡し、あわただしく服を着終えると、いそいそと部屋を出ようとした。
「せっかちねえ」
女はくすくすと笑って、最後に彼の背中にこう言った。
「でも、裸になって横に添い寝するだけで銀貨二枚なんてねえ。気前がいいいわよ。ふふふふ」
グリンは何も言えず、真っ赤になって部屋を飛び出した。
「よう、遅かったな」
船着場には、めいめいに港町での一晩を過ごしたのだろう、晴れやかな顔をした騎士たちがすでに整列していた。遅れて列についたグリンに、にやにやと笑いながらスウェンが近寄ってきた。
「そんなに良かったのか?」
「な、なにがだ?」
「こいつ。寝坊するくらいベッドで頑張ったんだろう?」
「……」
グリンは顔を赤くした。
実際の事を言っても言わなくても、どちらにしてもひどく恥ずかしいことには変わらない。彼は何も言わないことにした。
朝日がきらきらと光る波間を見ながら、騎士たちはボートに乗り込んだ。これから帰途の航海が待っている。櫂を握りながら、グリンは再び己の気を引き締めた。
マストとロープの補修を終え、ディスカバリー号はいつでも出港できる状態になっていた。帰ってきた騎士たちが船に上がると、艦長はただちに船員全員を甲板に整列させた。
ふだんは冷静で温厚な艦長が、今朝はひどく不機嫌そうに顔をしかめていた。その理由はすぐに明らかになった。
「出帆前に、諸君らに昨日の事件のあらましを話しておかなくてはなるまい」
艦長は騎士団の規約条項にもある「航海と任務、その結果と終了に関する必要な説明」を船員たちに行うべく、航海長と副長とにその任を命じた。
説明の概要はだいたいこうであった。
昨夜の海賊の襲撃により、商船ノークライム号はマストを破壊され航行不能に陥った。同じく騎士団の護衛艦ディスカバリー号も、ヘッドスルーのロープの破損により一時停船を余儀なくされ、その間に海賊船は逃走に成功。その後の騎士団の調査で、商船における負傷者は軽傷が三名で死者はなし、掠奪された物資は無し、という結論に至った。そのため騎士団側としては、不手際は認めながらも、護衛の任務は物資がガルタエナ港に下りた時点で完了したものとみなした。それにより、従来通り、護衛任務遂行による報酬金は、商船の所属する国家であるセルムラードに対し正しく発生するものとする。ただし、商船ノークライム号の修理費、および怪我人の手当て、積み荷運搬にかかった費用は、それを引かれることを騎士団側は承諾するものである。
以上のような任務報告書をノークライム号の船長に渡し、サインを求めたところ、船長はこれを断固として拒否したという。
その理由としては、失われた積み荷に対する保証金を払ってもらいたいということであった。船長が言うには、昨日の段階では船倉の積み荷のすべてが無事であるということに同意はしたが、それは船の全ての積み荷が無事であるということを意味するものではない。すなわち、船長室の保管庫にあった二千枚、およそ三万デュガート相当の八リグ銀貨が紛失したことに対して、騎士団側はその保証額を支払うべきだと、こう言うのである。
これを聞いたディスカバリー号の艦長は激怒した。そして今もおそらく激怒し続けているのは、その顔を見れば分かる。なにしろ、任務の前に提出された書面、つまりノークライム号の積み荷リストには、そのような銀貨のことなどはまったく記載されていなかったのである。また、商船のほとんどの船員も、その二千枚もの銀貨の存在を知らされていなかった。それは明らかに商船側の規約違反だし、最初から知らなかったものが、いきなり無くなったと言われても、騎士団側としては困るわけである。
当然ながら、艦長はきっぱりと商船側の保証請求を拒絶した。すると、ノークライム号の船長は半狂乱になって騒ぎ立てた。
「私の銀貨が盗まれた。私の銀貨を返せ。さもなくば取り戻せ」
話し合いは打ち切られた。
騎士団側は、これでは話にならないので、商船の……というか船長の言い分は無視して、セルムラードの国家を相手に報酬金を申請することに決めた。一方、銀貨を盗まれたと言い張る船長は、騎士団の無能ぶりを暴露し、その失態を周辺諸国に報告してやると、激しくまくしたてた。
おそらく、その盗まれた銀貨というのは合法的なものではなく、船長個人の利益にかかわるものであることは明白だったが、それがこうして綺麗さっぱりなくなってしまったからには、もはやその存在を証明する手段がない。騎士団としては、そのような銀貨などはじめからありはしなかったと証言すればよいわけで、ここで一商船と争って、これ以上無為な時間をつぶすつもりはなかった。
とにかくも、当初リストに記された積み荷は、ひと樽のワインも奪われることなく、無事ガルタエナに陸揚げされたのである。あとは補修のすんだディスカバリー号が、商船側から任務完了のサインをもらい、バルドス島へ帰還するだけであったのだ。
「なるほどねぇ、そんなことになっていたとはな」
出帆の準備で、甲板の上を行き来する船員たちを見ながら、スウェンは人ごとのように言った。
「でも、サインをもらえずに、このまま帰ってしまっていいものなのかな?」
グリンの質問に、彼は「知るもんか」というように、両手を広げてみせた。
「だいたいさ、その銀貨二千枚ってのも、結局は本当にあったのかどうかも分からないんだし、あのごうつくそうな船長のでっち上げってこともありえるだろ?」
「そうかもしれんな」
しかし、グリンにはなんとなく、その銀貨は本当にあったのではないかという気がしていた。そうだとするなら、昨日のあの海賊船の俊敏な行動力、その大胆きわまりない手口も、それ相応の獲物のためであったと得心がゆく。
だが、もしそれが本当だとしたら、いったいどうやって、海賊はあのごくわずかな時間で銀貨のありかを見付けたのか。昨日の調査でノークライム号の船員に聞いたところでは、海賊船が船に接舷したのはごく一瞬だけで、しかも海賊らしき輩が船に乗り込んできたのを見たものは誰もいなかったというのである。二千枚もの銀貨を瞬時に見つけて盗み、船員たちに気づかれぬうちにそれを持って船に乗り移るなどということは、まったく不可能に思われるし、そう考えると、銀貨など最初から無かったという方が、まだ現実的な気がしてくるのである。
「だけどさ、相手があの『赤毛のジェーン』なら、やるかもな」
腕を組みながらスウェンは言った。
「この数年、このあたりの航路では海賊被害が特に多いんだが、手際の良さと大胆さでは、間違いなく『ジェーンレーン一味』がトップだよ」
初めて目の当たりにした、伝説の海賊一味の船について話しながら、スウェンは興奮を隠せない様子だった。
「俺も直接見たのは初めてだ。高速スループ船『ブルーマスター』号を駆る、赤い髪の女海賊ジェーンレーン。噂じゃ、すごい美人だとか、反対に恐ろしい顔をした残酷な女だとか、いろいろと聞くがな。じっさいに彼女を見た人間はそういない。なにしろ、その行動は迅速にして的確。狙った獲物以外余分なものはとらないし、無駄な戦闘もしない。昨日だってそうだろ?撃ったのはたった一発の大砲だけ。それで商船のマストを壊しておいて、そのあとはディスカバリー号の旋回砲の死角を通って、さっさとトンズラだもんな。こっちの砲門はいくら無駄弾を撃ったことか。……おっと」
後部甲板を副長が横切ったので、スウェンはあわてて口をつぐんた。それから、彼は少し声をひそめてグリンに言った。
「まあ、とにかくだ。してやられたのは確かだよ。その銀貨ってのがあるにしろないにしろさ。はっきり言っちまえば、俺たちには関係ないことだからな。航海分の給料さえもらえれば。あとはお偉いさんたちが話し合うことだ。それよりもなによりも、『赤毛のジェーン』の船を見れたってだけで、こりゃ島の連中へのみやげ話になるぜ。もしこれが残虐で名高いドルテック海賊団や、ジャック・ラカン、海賊王ボールドリッジあたりが相手だったら、こんなふうにやられたのがマストの縄一本で済まなかったろうからな」
海賊に関する豊富な知識を覗かせて、スウェンは名のある海賊たちの名を上げてみせた。しかし、グリンにとっては、それらの名前は依然として、現実性の薄い物語の中の名前のように感じられた。
「よーし、ミズンマストに帆を張れ」
艦長の指示が甲板に響いた。
錨の巻上げが済むと、船員たちは一斉にマストのロープをつかみ、それを引きはじめる。スウェンとグリンもそれに加わった。
空は晴れ渡り、青々とした海面は陽光を浴びて輝いている。
今日は暑くなりそうだった。上着を脱ぐと、グリンは掛け声とともにロープを引いた。昨日の酒がまだ抜けきれていないらしく、これから襲ってくるだろう船酔いと吐き気とが恐ろしかったが、とにもかくにも、ディスカバリー号はこれから帰途につくのであった。
帰りの航海では、運悪く強い横風が吹きつづけ、船員たちはほとんど一日中、交代でマストのロープを引き続けた。
風の方向が変わるたびに帆を緩めたり、反対側に角度を変えて張ったりしなくてはならず、グリンも汗まみれになりながら、一般船員らとともにロープを手繰った。
船は激しく揺れ、ときに大きく横に傾いた。帆は風向きによって「詰め開き」と「左舷開き」を交互に繰り返さなくてはならず、その度に船員たちは、ロープを手繰るために力を振り絞らなくてはならなかった。
そうして、彼らの尊い労働のおかげもあり、ディスカバリー号は夕方前にはバルドス島の港に到着したのである。へとへとになった船員たちは、それぞれに船を下りると帰着証明にサインをし、ばらばらと解散した。
騎士団居住区にある宿舎へと戻ったグリンは、出迎えた仲間たちに軽い挨拶をすると、そのままベッドに倒れこんだ。足は鉛のように重く、ロープを握り続けた手はひりひりと痛んだ。
記念すべき初めての航海は、まったくの肉体労働の時間に終わった。マスト、マスト、帆、帆、帆!
今晩自分がみる夢は、間違いなくマストと帆とロープだろう。彼はぐったりとなりながらそう考えた。
だが、実際にその晩に見たのは、赤い髪をした野性的な美貌の女海賊の夢だった。
騎士しての島での日々は、それからしばらくは平穏に過ぎた。
交代での砦の見回りと、剣と銃の訓練。航海術の講義に、週に一度の補給船が来たときは、物資の積み下ろしの手伝いをした。また、ガレー船に乗っての領海内パトロールでは、念願の旋回砲の実弾練習も行った。
先日の航海での銀貨紛失の請求問題が解決したのは、帰港から十日後のことであった。
結局、護衛を受け持った騎士団側としては、はじめから契約書に書かれていなかったそれら銀貨に関しては、その存在の如何にかかわらず、それを任務外の物資とみなし責任は持てない、との態度を崩さなかった。ノークライム号の船長が、いったいどのように自国のギルドと保証を請け負う政府側に、今回の請願書を提出したのかは不明だが、ともかく護衛任務完了にともなう騎士団への報酬は支払われた。ただし、その額は規定の半分ほどであったが。
報酬から差し引かれた名目である商船のマスト修理代が、それほど膨大な額になることは疑わしかったが、騎士団側はあえて文句を言わなかった。この件に関して、これ以上の議論を長引かせることは騎士団自体の名誉にもかかわるし、今回の任務における影での失態が明るみに出てしまうことも避けたかったのである。
当然ながら、騎士団への報酬の額が半分になれば、その分船員たちへの給料も減らされる。給金係から十枚ほどの八リグ銀貨を渡されたとき、しかしグリンは、自分が初めての航海でもらったその金を、誇らしげに握りしめたのだった。
しだいに、グリンは早く次の航海に出たくなった。
帰還した翌日までは、もうあんな重労働はたくさんだと思っていたのだが。甲板上から見た、あのどこまでも続く海原の青さ、頬を撫でる心地よい風、マストに広がる白いメインスルー、眼前に広がるマロック海の島々、かもめたちの声……船酔いとロープ引きの労働を差し引いても、それらは素晴らしい体験であった。
次の任務は意外にもすぐに決まった。
騎士団はきたる六月のはじめに、マロック海周辺、特に海賊の頻出する海域であるキャスタナル諸島一帯での、大がかりな作戦の敢行を決定した。これは総勢六百人の騎士と、商船に偽装した五隻の武装したガレオン船による、いうなれば囮捜査で、あわよくば大きな海賊団のアジトを割り出し、それらを一網打尽にするという、それは近年に例をみない大胆な作戦であった。
この作戦が提案されると、その危険性やそれにかかる莫大な資金などの面から、一部の騎士団幹部からは当然のように反対の声も上がった。だが、最終的には本部の了解も得て正式な決定がなされた。
資金面の問題も、海賊退治という名目があれば周辺の諸国からの援助も少なからずあり、さらには捕らえた海賊たちを各国に引き渡すことで受け取ることができるはずの賞金も考慮に入れれば、おおむね解消される見込みだった。
また一方では、アナトリア騎士団の名声を高めるという点でも、これは重要な作戦であった。一部ではすでに噂となっている、先日の銀貨消失事件での失態を取り戻すという目論見も、あるいは上層部にはあったはずであった。
普段の護衛任務であれば、船に乗り込む騎士船員は事前に決められるところだが、今回は任務の危険性もあって、艦長、副長以外の乗組員はすべて、それぞれの自由意思での応募による乗船となった。
商船に化けて海賊と接触し、場合によっては海賊の基地に単独で乗り込むことにもなろうという、大変危険な任務である。それだけに帰還した場合の給料も大きいが、また命を失うか、船の事故や戦いなどで戻れないという可能性も大きい。
乗船にあたって、騎士たち、船員たちには自分が乗り込む船を自由に選ぶことを許された。まず船の名前と、その船の艦長の名前が公表され、作戦への参加を志願する者たちは、自分の選んだ艦長の船に乗り込めるわけである。
今回の重要任務を任されたのは、すべてが騎士団では名のある艦長たちであった。作戦への志願応募は出航の三日前まで受け付けられた。もし定員に満たない場合は、船の数を減らすことも検討されていたが、その心配は無用となった。
バルドス島の騎士たちは皆、勇敢であった。作戦決行日の七日前には、すでに志願する騎士の数は、募集定員の六百名を超えていた。
グリン・クロスフォードも、この作戦が決まった段階で、早くから心のうちで参加を決めていた。たとえ、これが危険な任務であろうとも、いっこうにかまわなかった。いや、かえって直接的に海賊に関わる任務であるということが、彼の冒険心を否が応にも刺激してしまったのである。あのガルタエナで遭遇した海賊船と、そこに見た人影……戦闘楼に立ち赤毛をなびかせるその姿を、彼は島に戻ってからも、毎日のように思い描いていたのだ。
初めての航海から戻ってから、彼は、少しでも船上で騎士として立派に働けるよう、航海海術や船の構造、それに海図や天候などの勉強に打ち込んだ。剣の腕を磨き、マスケット銃とスナファンス拳銃の射撃練習をこなし、大砲の指揮を覚えた。苦手だったマスト登りの練習もした。次の任務では、船酔いで船室のハンモックに運ばれるようなざまは見せまいと。一人前の騎士として働き、戦ってみせると。彼はそう、自分自身に言い聞かせた。
そして、その日が来た。
朝日が昇りはじめたバルドス島の沖合には、五隻の帆船がきらきらと輝く海面に悠々と浮かんでいる。軍用ガレオン船をこの一ヵ月で改装し、商船に見えるように塗装も上塗りしてあった。大砲口には目張りをし、最新式だった帆も、わざと少々汚れた、古めかしいものに取り替えてある。
前日からの船の出航の準備もほぼ終わり、船員たちはそれぞれが乗り込む船に向かってボートを漕いでいた。彼らは騎士姿ではなく、騎士も艦長も普通の船員服や私服を着て、商人になりきっていた。
銃や剣などの武器は船底に隠し、積まれた大砲には覆いがかぶせられた。あくまでもただの商船として海賊たちと接触するのが今回の作戦である。そして海賊のアジトを見つけたら、そこに五隻を集結させ、一気に殲滅するというのが最終的な目標であった。そのためには、海賊たちの巣窟であるキャスタナル諸島の海域を、海賊船や不正商船などに混じって、怪しまれずに航行しなくてはならない。
「そこでまずは、我々はポート・イリヤへ向かう」
ガレオン船タンタルス号の艦長、ブレイスガードは、乗り込んだ船員たちを前に、さっそく作戦の詳細を語った。
「当然のことながら、今回の作戦に参加する五隻はすべて別行動をとり、それぞれにキャカタナル諸島を周航する。我々はあくまで商船であるから、それを疑われるような連携は船の間でとることはできない。出帆も半刻ずつ遅らせて一隻ずつだ。五隻はれぞれの船ごとに別のルートを航行しつつ、時間を定めて自然な形で航路上をすれ違う。互いの情報の交換はそのときだけだ。今回の五隻の中で、我々の船だけは、エボイア島のポート・イリヤを目指す。そしてそこで上陸する」
船員たちから、「おお」という声があちこちで上がった。
ポート・イリヤといえば、キャスタナル諸島でも、海賊たちや不法な商人、密売人たちが集う最大の港町として名高い。
ただ、陸の上ではいかに海賊だろうとすぐには逮捕はできない。騎士団に与えられた権限は、マロック海の海上における海賊行為の現行犯での逮捕のみなのだ。もちろん相手が戦闘をしかけてくれば話は別だが、今回の作戦の目的は、海賊団のアジトを探り、彼らを一掃することにある。騎士たちには、小さないざこざや、無意味な戦闘をするのはなるべく避けよという通達があらかじめ申し渡されていた。それにしても、商人を装って犯罪者の町ポート・イリヤに上陸するというのは前代未聞の作戦であり、非常な危険を伴うであろうことは、ここにいる誰にでも理解できた。
騎士たちは一般船員の服装をするだけでなく、普段なら腰に差すはずの剣も外し、頼りになるマスケット銃なども、まとめて船倉に隠してある。小型のスナファンス銃のみが所持を許されたが、それも緊急時以外の使用は厳禁とされていた。
縞模様のシャツに薄汚れたズボンという、下級船乗りの恰好をしたグリンは、元の育ちが良いだけに、そのままではひどく不自然に見えた。彼は仕方なく髭を剃るのをやめた。数日もすれば、伸びた髭とぼさぼさにした髪が、きっと騎士の顔を隠してくれるだろう。
いっぱいに張られたメインマストの帆が順風を受けて膨れ上がった。騎士たちを乗せた船は、海面をすべるように出帆した。
タンタルス号は北東に進路をとった。他の四隻の船は、それぞれキャスタナル諸島を別方向から周航し、最終的にはポート・イリヤのあるエボイア島の北で合流するという手筈になっている。今回の航海期間は、目安として十五日ほどの予定であったが、これはあくまでも最短での日数であり、それぞれの船には一ヵ月分の食料と水が積み込まれた。
船室に下りたグリンは、思わず顔をしかめた。
船には食料となる豚や鶏などが生きたまま乗せられていて、それらのひどい匂いがどの部屋にも漂ってくるのだ。しかも、今回使用された船は、商業船としてカモフラージュに適したものが選ばれていたので、彼が最初の航海で乗ったディスカバリー号とは比べ物にならぬくらい古かった。船室の床は所々板が剥がれかかっており、壁といい天井といい、じめじめと湿っているような感じで、空気までよどんでいた。夜になり、部屋のハンモックで休むときも、床や天井をネズミが駆け回る音で、彼は何度も目を覚ました。半刻ごとに鳴らされる鐘の音で、定時の見回りの順番が回ってくるのだが、暗がりを起き上がり、じめじめとした廊下の床を、カンテラを頼りに歩いていくのはひどく気味が悪かった。
しかし航海が始まって二日もたつとそれにも慣れ、日中の甲板での重労働のせいもあってか、カビ臭い湿った船室でも眠れるようになった。密かに懸念していた船酔いに陥ることもなく、グリンはてきぱきと働いた。すっかり日焼けし、以前よりもずっと太くなった腕でロープを引くその姿は、もう何年もこうしてきたような、立派な海の男に見えた。
船は順調に海路を進み、ついに四日目の朝、目的地のエボイア島をその視界にとらえた。
エボイア島はキャスタナル諸島でも最大の島であり、この海域では唯一の整備された港町、ポート・イリヤを擁する。ポート・イリヤは、どこの国にも属さない完全な自治都市で、どんな船でも自由に寄港ができるこの港町は、この十数年で急速に発展した。
この辺りの海域には小さな島々が無数に点在しており、周囲にサンゴ礁が連なる、まるで迷路のように入り組んだ地形は、海賊たちにとっては恰好の根城であった。運悪くその近くを通った船は、商船であろうと騎士団の船であろうと見境なく襲われた。騎士団の大型のガレオン船にとって、喫水が浅く小回りがきく海賊船は、こうした海域では非常にやっかいな相手であった。また、鋭く尖ったサンゴ礁は、常に座礁の危険をはらみ、船員たちを驚怖させた。
そうした危険のため、数年前からはポート・イリヤとその周辺海域は、騎士団のパトロール区域から除外されていた。この諸島一帯はしばらく放置され、その間に海賊たちはその数をどんどん増やしていった。
現在このポート・イリヤを訪れるのは、その多くが密輸入者や裏商人、そして海賊のたぐいである。いうなればここは、犯罪者と海賊の町であり、お訊ね者の天国であると言えた。
寄港をひかえたタンタルス号の船室では、騎士たち全員を集めた綿密な打ち合わせが行われた。
上陸隊のメンバーが選考され、当然のようにグリンもそれに志願したが、結局、彼は居残り組に入れられた。町に上陸し、海賊の情報を集めるという任務には非常な危険が伴い、やはり経験のある者が選ばれるのは当然ではあった。
選ばれた二十名ほどの上陸隊は、どこから見ても騎士には見えず、かといってまともな船員でもなく、海賊だらけのこの港町に似つかわしい、つまりいかがわしい商人に見えそうな服を着て、情報集めに必要となるだけの金を懐につめ、ボートに乗り込んだ。
船に残されたものたちは、いつでも緊急に出帆できるよう、常に錨を巻き上げるための人員を甲板におき、交代でマストに登って周囲の海域を見張った。そのかたわら、船倉の武器類の点検、大砲窓にあてがわれた目張りがはがれていないかの点検をしつつ、他の船と落ち合う海域を正確に割り出すため、アストロラーベ(太陽や北極星の高さを測り、緯度を調べる道具)による確認を行った。
グリンに与えられた役割は、船倉の点検という、ポート・イリヤへの冒険行に比べればまったく地味な仕事だったが、半刻おきに砂時計をひっくり返すだけの時刻係をまかされるよりはまだマシだと、そう自分をなぐさめながら、彼はその仕事をこなした。
船倉に並んだたくさんの樽のうち、カモフラージュのために穀物や果物、それにワインなどが詰まったものが前面に置かれ、武器類の隠されたものは一番奥に置かれた。また、空の樽も用意されていた。これは必要の際には、その中に武器を持った騎士たちが隠れられるように、万が一に備えてのものだった。
グリンは、ひとつひとつ樽の中身を確認しながら、武器の入った樽、火薬の入った樽、そして空の樽の場所を覚え込んでいった。
日が沈み、海上が暗闇に包まれても、ポート・イリヤの港町にはいくつもの明かりが灯っていた。
(眠りにつくことのない海賊たちの町……か)
妖しく輝く町の灯を甲板上から眺めながら、グリンは物語に出てくるような海賊が行き交う町の光景を想像するのだった。
「なるほど。それは確かな情報なのだな」
偵察隊が戻ったのは、真夜中過ぎだった。艦長室に集められた主立った騎士たちは、緊張の面持ちで彼らの報告を聞いていた。
「間違いありません。最も信頼のおける情報屋から大金をはたいて買ったものですから。これです」
差し出されたのは一枚の海図だった。
キャスタナル諸島一帯を示したその地図に、赤く付けられた印は、名のある海賊団のアジトだというのである。
「おそらく、ボールドリッジか、またはドルテックあたりのものかと思われますが」
報告する偵察体の隊長の声は、興奮のためかいくらかうわずっていた。彼らのポート・イリヤでの成果は予想以上のものであった。
「海賊王ボールドリッジ……、それにあのドルテック海賊団か」
普段は冷静なブレイスガード艦長も、驚きを隠せぬ様子であごひげに手をやった。
海賊ボールドリッジは、このマロック海を根城とする海賊たちのなかで、最も有名な一人である。従える部下の人数は四百人以上ともいわれ、十数隻のスループ船に加え、騎士団並の武装をしたガレオン船に快速のガレオットまで所有しているという噂も聞く。冷酷かつ残忍にして知られるドルテック、焼き打ち船で恐れられるジャック・ラカンも、それに並ぶ大物であった。
その大海賊のアジトの場所をついに突き止めたのだ。居並んだ騎士たちは、高ぶる気持ちに、誰もがその顔を紅潮させた。
「明日は、戦闘になるだろう」
重々しい一言が、ブレイスガード艦長の口から発せられた。
「予定通り、明日の日の出前に他の船と合流、そして、そのまま地図に記された海賊のアジトを急襲する。異存のある者は?」
騎士たちは無言で直立した。いよいよ、大作戦が始まるのだ。
「よかろう。それでは、これよりただちに合流海域へ向かう。その間は交代で仮眠をとっておくよう。明日は長い一日になるぞ」
「アイ、サー!」
騎士たちが帽子に手をやり敬礼する。むろん、今は正規の航海服ではなかったが、誰もが騎士としての誇りと戦いへの高ぶりを胸に、声を上げたに違いない。
夜半を過ぎる頃から、海は荒れはじめた。
空は曇り、星は隠れて、海面は闇に覆われた。漆黒の中、強い波がタンタルス号の船体にぶつかり、その度に船はひどく揺れた。
エボイア島の北側、ポート・イリヤとは反対側の海域がクインズドウター号、ソーレファルド号の二隻との合流ポイントだった。
この時点でなにも収穫がなければ、船は再びそれぞれの単独航海に戻るという予定であったが、タンタルス号の得てきた情報は大きく、合流後はただちに全船揃っての海賊討伐に向かうことになるだろう。その他の二隻、リリアンアクス号、アラベスク号ともなるべく早く合流し、武装準備をした五隻で一気に海賊のアジトを包囲する。それがブレイス・ガード艦長のたてた計画であった。
夜明け前の深い闇……月が隠れ、星の光が消えるこの時間は、船乗りたちが最も気をつかう時刻でもあった。しかもこのあたりは、海図にも記されていない岩礁が多く、常に海底の深度に気をつかっていなくてはならない。
「深度、六つ……六つ半です」
重りのついたロープで、海底までの距離を測る船員の報告にうなずきながら、艦長は厳しい面持ちで後部甲板に立っていた。
「帆影が見えます!」
見張り台から報告が上がると、艦長はさっと顔を緊張させた。
「ふむ。合流地点まではまだだいぶ距離があるが……。船影はクインズドウター号か?それともソーレファルド号か?」
「はっきりとは分かりません。ですが、方角から判断して、クインズドウター号かと思われます」
「よし、合図のカンテラを振ってみろ」
「アイ・サー」
暗闇の中、前方やや右手からゆっくりと近づいてくる船影が、徐々にはっきりと浮かび上がってきた。騎士たちは合図であるカンテラを、船の左右に一つずつ灯し、それをゆっくりと上下に振った。
「どうだ?」
「はい。あ……相手方もカンテラを灯しました」
「数は?」
「一……二、二つです」
それを聞いて艦長は眉をひそめた。
「二つか。妙だな……」
「あ、いえ……もうひとつ、小さく見えます。それを入れれば三つですが、あ……また消えてしまいました。灯はふたつです」
「うむ……たぶん、芯が湿っているかして灯らないのだろう」
艦長はひとつうなずくと、船員たちに向けて告げた。
「クインズドウター号だ」
甲板の騎士たち、船員たちは歓声を上げた。
命がけの任務のさなかで、仲間の船との合流は、じつに心強く感じられるものだ。タンタルス号の船員たちは、眠気も忘れたように、仲間を迎えるために全員が甲板に上がってきた。
グリンも舷側に身を乗り出して、近づいてくる味方艦を見守っていた。暗がりの海面にうっすらと見えはじめた船のシルエットに、彼はふと眉をひそめた。
「おい、クインズドウター号ってあんなに小さかったか?」
「さあな。まだ距離があるから小さく見えるんだろう」
横にいた騎士は、とくに気にするようでもない。
「そうかな……」
なにか釈然としないものを感じながら、グリンはじっとその船影に目を凝らした。
だが、その船が船体全部をあらわにし、タンタルス号の真横に滑り込むと、甲板上の騎士たちがざわめき始めた。
「艦長、あれは……クインズドウター号ではありません!」
副長が報告するまでもなかった。
クインズドウター号は、このタンタルス号と同形の三本マストのガレオン船を改造したもので、大きさもほとんど同じである。しかし、目の前に現れた船は、一本マストにメンスルーといわれる縦帆をもつ中型のスループ船だった。
「相手船は砲門を開けたまま接近しています!」
副長の言うように、相手船の砲窓は全て開かれ、そこから大砲がいくつも顔を覗かせている。
「海賊船か。しくじったな。ここで戦闘を始めれば、せっかくの情報を無駄にすることになる……」
艦長はつとめて冷静に言った。
「むやみに撃ってこないということは、我々を拿捕するつもりではないのかもしれん。なにせここはまだポート・イリヤに近いからな。それにまさか、こちらが騎士団の船だとまでは知るまい。我々が海賊と取引のある商船だと思わせれば、あるいは、そのまま去ってくれるかもしれん」
「では、このままやり過ごすのですか」
「そうだ」
決断したようにうなずいてみせると、艦長は甲板の船員たちに指示を与えた。
「落ち着くのだ。いいか、銃器類は見つからぬようけっして手にするな。我々はあくまで商船としてふるまうんだ。普通にしていれば大丈夫だ。海賊といえども、自分たちの商売相手にいきなり大砲を撃つようなことはしまい。いいか、決してあわてた様子や、恐れる顔は見せるな。騎士だと知られずにやりすごすのだ。そう、商人らしく笑顔で手でも振ってやれ」
「アイ・サー」
スループ船は、ゆっくりとタンタルス号の右舷付近を通ってゆく。夜明けまではまだしばらく間がある。このまま通り過ぎていってくれさえすれば、よけいな戦闘をすることもなく、また作戦を続行できる。そうすれば、すべてはうまくゆくのだ。
艦長はじめ、甲板の騎士たちは、おだやかに装った顔の下で、息の止まるような緊張を感じながら、ほとんど止まりそうな速度で、のろのろとすれ違ってゆく海賊船を見つめていた。
「よし……いいぞ。そのまま……」
相手船は、タンタルス号の側絃すれすれを不気味な静かさで通りすぎていった。その船尾が離れてゆくのを見て、誰しもがほっと胸をなで下ろそうとした。
そのときであった。
「あっ、ジョリーロジャーです!旗が上がりました」
見張り台から声が上がった。同時に、相手船はタンタルス号の船尾に付くように、右に回頭しはじめていた。その一本マストのてっぺんに、こちらを威嚇するかのような海賊旗が上がった!
「ああっ!」
まるで絶望のような、悲鳴にも似た声……
「旗の柄は、骸骨と砂時計です。黒地に骸骨と……砂時計です!」
それが何を意味するものかは、たとえ騎士でなくとも、このマロック海の船乗りであれば、誰でも分かることだった。
「ドルテックだ。ドルテック海賊団だ……残酷な黒い海賊だ!」
■次ページへ