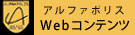![]()

続・騎士見習いの恋 エピローグ
一年後……
湖畔の城にやってきた夏が、また過ぎてゆこうとしている。
野山に咲き誇っていたアカンサスやヘリアンサスの花々もしだいに見頃を過ぎ、涼しげな湖面には、夏の間は見られなかった水鳥たちの姿が、少しずつ増え始めている。
ながれゆく時の中で、毎年繰り返される季節のうつろいと、色彩を変えてゆく風景たちは、そこで生きる人間に、己の有限の生について思いを馳せさせてくれる。
そうしてまたひと夏を過ごした湖畔の城を青い湖の向こうに臨む、その丘の上に、今、一人の女性がたたずんでいた。
全身を黒い喪服に包み、未亡人の証であるレースのついた帽子で髪を覆い、その顔にはほのかな憂愁の翳りを、その瞳には静かな悲しみの色を浮かべて、
その女性は、かすかに震える口元をして、墓の前に膝をついた。
黒曜石で造られたその墓の前で、彼女は両手を組み合わせると、そっと目を閉じた。
今年も暑い夏を過ごし、彼女は少し痩せたように見えた。目を閉じたその横顔は、ほっそりとしたあごと白いうなじが美しく、喪服のせいか、肌はまた透けるように白く、ひどくはかなげに見えた。
「……」
ゆっくりと彼女は立ち上がり、墓を見つめながら、もう一度祈りの言葉をつぶやいた。
美しく輝く湖の青と、木々の緑に包まれたこの土地で、彼女……マリーンは未亡人として生きてゆくことを決意した。
そして、もうひとつの決意。
それが、彼女のこれからの人生において重要な意味を持つだろうことを……
祈りの中に、彼女はそれをつぶやいた。
そのとき風に乗って、赤子の鳴き声が聞こえたような気がした。
マリーンが振り返ると、丘を登る道を、侍女のクインダが歩いてくるのが見えた。
「マリーンさまぁ」
侍女がこちらに手を振る。抱えているものを落とさぬようにと、とても気を配る様子で。
クインダは忠実な侍女で、今では、マリーンにとって、どんなことでも話せる、まるで友人のような存在であった。マリーンが新たに屋敷の主となったときも、彼女はまっさきに祝福してくれ、他の侍女たちをまとめてくれたことに、マリーンはとても感謝していた。
その侍女が腕に抱くものとともに歩いてくると、マリーンの顔には、いつくしむような、やわらかな微笑みが浮かんだ。
「マリーンさま」
丘を登ってやってきた侍女が、ふうと息をついて、抱いていたものを差し出す。
「ありがとう、クインダ」
だぁ、だぁ、という無邪気な声がした。それはいつものご機嫌の印である。
マリーンは、侍女の手から受け取ったそれを大切に胸に抱くと、優しい声で囁きかけた。
「いい子ね。お坂を登るのは恐くなかった?さあ、これがあなたの……パパのお墓ですよ」
彼女が抱き抱えていたもの……小さな可愛らしい赤ん坊に見せるようにして、マリーンは墓の前にしゃがんだ。
なにを見せられているのか分からぬように、赤ん坊はきょとんとして首をかしげていたが、やがて墓の方を見ながら、きゃっ、きゃっ、とはしゃぎだした。
「まあ、おわかりになるのでしょうか?」
侍女が驚いたように言った。
「さあ……どうかしらね」
マリーンはくすりと笑い、いとおしそうにその小さな体をそっと引き寄せた。
「お母様がいますからね。あなたには、お母様が、ずっと、ずっと……一緒にいますからね」
赤ん坊に優しく語りかける、その彼女の姿は、いくつかの悲しみを乗り越えて、母親となった喜びを知りそめた、そんな伯爵夫人としての姿だった。
黒曜石の墓の隣には、こちらは小さな、まるで急いで立てられたと見える墓石が、二つ並んでいた。
マリーンは、そちらにも祈りを捧げるように手を組み合わせた。
「そちらは、一年前に亡くなった貴族のお嬢様と、もうお一方のお墓でしたね」
「ええ」
侍女の言葉に、マリーンはつらそうにうなずいた。一年前のあの日、この場所で起きたことを思い出すように。
「あの、少年……レナスといったかしら」
マリーンはつぶやいた。
「きっとコステルさんのことを、とても愛していたのでしょうね。あの後……自分で自分の喉に剣を刺して……」
「恐ろしいですわ」
侍女はぶるっと体を震わせた。
「そんな、人の愛し方……私にはとうてい分かりません。相手を殺して、自分も死ぬなんていう。考えただけで……おお、恐ろしい」
「そうね」
その小さな墓を見つめながら、マリーンはひそやかに言った。
「妄執……といっていいのかしら。相手への執着、自分の心にひそむ暗い炎……そうした心にひそむ鬼というものが、人の中には確かにあるのよ。相手のすべてを手に入れたいと思う心、気が狂いそうになるほどの執着……。きっと、彼もそうだったのでしょう」
マリーンの声はかすかに震えた。
「たとえ体を抱いても、心までは手に入らない。なのに……それが分からずに、そういう激しくてつらい愛で、みんな泣いたり怒ったり、絶望したりするのよ。相手を殺したいほどの愛情は、相手を殺したいほどの憎しみと同じこと。きっと……きっと、人は、激しく愛した分だけ、激しく憎めるのだわ」
「分かりませんわ。そんな恐ろしいこと……」
横で聞いていた侍女は、両手を頬に当てた。
「そうね。それでいいのよ。でも……私には、なんだか少しだけ分かるのよ。相手を自分のものにしたい……そういう執着が、愛することを憎しみにもする。きっと私にも、そうしたものがどこかにあったのだわ」
「そう……なんですか」
なんと言っていいか分からぬ様子の侍女に、マリーンは笑いかけた。
「あなたは、まだ若いから。でも、そうね……もし、そういう恋が見つかったら、あなたにも分かる時がくるかもしれない。つらくて、つらくて苦しくて……激しい恋が。愛情と憎しみが入り交じって、どうしようもなく、自分が壊れそうなほど、狂いそうなほどに、誰かを愛してしまう、そんな……刃物のような恋が」
「……」
「でもね、その激しい恋を超えたあとには、もっと豊かで、穏やかな愛が訪れるのよ。自分に素直に、そして相手をいつくしむことのできる、静かで深い愛が。つらい恋に互いの身を滅ぼしてしまう少年や少女たちにも、それが分かれば……。そうすれば、彼らもこうならなくてすんだかもしれないのに……」
墓を見つめて、マリーンはもう一度両手を組み合わせた。
「そして、後悔しないような、激しい恋もあるわ。そういう季節を通り過ぎてきた。だから私は……今を愛している」
それはまるで、自分自身に囁くようなつぶやきだった。
悲しげな目をしながら、どこか誇らしげでもある。そんなマリーンの表情に、見つめる侍女は、不思議そうに首をかしげた。
「おお、よしよし……」
腕の中でぐずりはじめた赤ん坊に、彼女は優しく笑いかけた。
「ごめんなさいね。お母様怖いお顔してた?よしよし……もう大丈夫よ。いい子ね。よしよし」
赤ん坊に話しかけるとき、彼女は、まるでこの世で最も大切な宝物を見るような目をしていた。限りない愛情の込められた母親の顔が、そこにあった。
「そういえば、確か、今日はあの方が戻られる日でしたでしょうか?」
話題を変えられることにほっとしたように、侍女は言った。
「ええそう」
マリーンはうなずき、子供を抱きながら嬉しそうに微笑んだ。
「たぶん、もうすぐ帰ってくるでしょう。夕方くらいになるかしら」
「お久しぶりですね」
「そうね……半年ぶりかしら」
マリーンの頬にさっと血の気がさすのを、侍女は見逃さなかった。女主人の顔がこの上なく美しく見えるときを、侍女はよく心得ていた。
「それでは、私は一足早く戻って、お食事の準備でもしておきますね」
「それがいいわ。きっと長い旅でお腹を減らしているでしょうから」
丘を下りてゆく侍女を見送ってからも、彼女はしばらくの間、西日に輝く湖面を丘の上から見つめていた。
「ああ……もう夏も終わりね」
ふとそうつぶやいたとき、彼女は不思議な感覚を覚えた。
去年の夏にも、たしか同じことをつぶやいた気がするような……それは時間を越えて反芻される言葉の記憶だろうか。
(ときは……ながれてゆくのね)
なにかに取り残されてゆくような、そんな寂しさが、マリーンの胸いっぱいに広がった。
(時間は戻せない……いいえ、もう、戻らないのだわ)
これまでに失ったものや、過ぎ去っていった時間の中にある思い出たち。それらに思いを馳せながら、マリーンはじっと湖面を見つめていた。
退屈したように、胸に抱いた赤ん坊が、うんうんと体を動かした。
「ああ……ごめんなさい」
小さくやわらかな頬を指先で撫で、彼女はあやすようにして体を揺らせた。
「いってしまう命もあれば、授けられる命もあるのだわ。あなたは……私の宝物」
にっこりと笑ってマリーンが体を揺らせると、赤ん坊はきゃっ、きゃっ、と嬉しそうな声を上げた。
「さあ、そろそろ戻りましょう」
太陽は西に傾き始めていた。もうすぐ、沈みゆく赤い円盤がこの湖を盛大に照らすだろう。それは一日の終わりと、あらたな次の始まりに思いを馳せる、素敵なひとときだ。
丘を下りる小道をうつろいゆく黄昏色の空を見ながら、マリーンはゆっくりと歩いていった。腕のなかで、すやすやと眠り始めた赤子を、泣きたくなるほどのいとおしさに包まれて見守りながら。
彼女の決意……
それは、この子をモンフェール伯爵の子として育てること。
これからずっと、たとえなにがあっても……この場所で、この子を守り、育ててゆく。亡き伯爵を父として。
それが、悩み抜いた末にマリーンがたどり着いた決意だった。
安らかに寝息をたてる腕のなかの赤ん坊……この茶色みがかった巻毛は、この子の父ゆずりのものに違いない。
その真実を知るものは、彼女以外には……一人だけ。
(大丈夫……あなたは私が守るからね)
マリーンはいとおしそうに、赤ん坊の頭を優しく撫でた。
夕日の残照を受けて、オレンジ色に輝く湖面……涼やかな風の吹く湖畔の道を、マリーンは歩いていた。
しばらくして、腕のなかの赤子がぱっと目を開け、「だぁ」と声を上げた。
ときとして赤子はとても敏感だ。なにかの気配に気づくように泣きはじめることもあれば、自分を愛する存在を察知して微笑みかけてもくれる。
「まあ、どうしたの?」
マリーンが腕の中を覗き込むと、きゃっ、きゃっ、と嬉しそうに声を上げて、赤ん坊が笑っている。
ここは湖面にほど近い、彼女がよくボートに乗って漕ぎだすあたりだった。
「ボートに乗りたいの?ううん、違うわね……」
マリーンは首をかしげた。
そのとき、西日を受ける土手の上に、人影が見えた。
「……」
はしゃぎ続けている赤ん坊を抱きしめる、マリーンが見上げる先に……
「やあ……」
手を振る、彼がいた。
「帰ったよ」
馬を連れた騎士姿で……その背にひらめくマントには、騎士の証である赤い裏打ち。
すらりとした背丈は、この一年でまたいっそう伸びたのだろう、もう彼女よりも頭ひとつも高くなったに違いない。
「ああ……」
見上げるマリーンは、感動に声をつまらせた。
かすれる声で……
「お帰りなさい」
わき出る喜びと愛情を込めて、マリーンは言った。
「ただいま。マリーン」
彼女を包み込む、優しい声。
そして、名騎士であった彼の父のように、見事な剣の腕と誇りとを持ち、彼はそこにいた。
見習い騎士の少年はもういない。
彼女に恋をし、彼女を愛し、苦しみと喜びをすべて共に味わってきた。
見習い騎士は、逞しい青年となり、
ついに騎士となった。
黄昏に包まれた湖畔の城に、彼が帰ってきたのだ。
「リュシアン……」
かつてと同じように、その名を呼び、
震える
マリーンの声。
土手を下りるごとに、広がり輝く笑顔たち。
差し伸ばされる、手と手……
「ああ……」
長く激しい恋の季節を経て
ようやくたどり着いた。
その場所に。
「マリーン、愛しているよ」
巻毛の騎士の強い腕に引き寄せられ、
赤子を抱いたマリーンは、穏やかに目を閉じた。
完
Ending BGM “Half the Mountain”
by MOSTLY AUTUMN
あとがき
ランキングバナーです。クリックよろしくです!