ブルーランド・マスター
8/11ページ
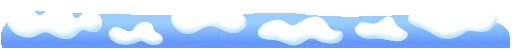
■8■漂流……そして
「いくぞ、グリン。船が危ない」
砂浜に引き上げたボートを押し出し、二人はそれに乗り込んだ。
「急げ!早くしないと船が……私の船が焼けてしまう」
ジェーンレーンはグリンに櫂を渡し、自ら櫂もをとり漕ぎはじめた。その間にも、巨大な炎の塊のような船は、ぐんぐんと近づいてくる。グリンは必死に腕を動かしながら、ときおりその炎に包まれた船を見やった。
焼き討ち船というのは、甲板に油をまいて火をつけた船を、そのまま相手船にぶつけるというものである。この時代の船はほとんどが木造であるから、火が燃え移れば、あっという間に船ごと焼けてしまう。多くの船乗りが火を恐れ、船内での煙草を禁じたり、ランタン以外の明かりの使用を極力しないのも、船火事を恐れてのことである。燃え上がる船をそのまま武器にするというこのやり方は、危険きわまりなく、特に多くの船が碇泊する港などへ夜を狙って焼き討ち船を放つのは、おそるべき被害と恐慌とをもたらすのだ。
「待て、漕ぎ方やめ」
ボートが湾内の中ほどに差しかかると、ジェーンレンーンは櫂を置き、周囲を見渡した。
キーオス島の湾内には数隻の船が碇泊していたが、どの船でも、突如現れた焼き討ち船のせいで、大変な騒ぎが起こっているのが見て取れた。ブルー・マスター号の甲板上にも、慌ただしく駆け回る船員の姿が見える。恐らく慌てて出帆準備しようとしているのだろうが、いったんマストを下ろして碇泊してしまうと、すぐには船を動かせない。このまま焼き討ち船が突っ込んだなら、湾内は大惨事になるだろうことは明らかだった。
「どうする、ジェーンレーン。ブルー・マスター号に戻るのか?」
「いや……」
彼女は首を振った、その目は、不気味に近づいてくる炎の船を見据えたまま、距離を計るかのように細められた。
「我々が船に戻っても、同じことだろう。その間に焼き討ち船がぶつかる。船首が触れただけで火は燃え移る。そうなれば、もう船はおしまいだ」
「では……どうする」
こうしている間にも、勢いを増した炎が燃え盛るその船が、徐々に眼前に大きく迫ってくる。
焼き討ち船はかなり大型の船のようだった。三本マストに張られた帆が、燃え上がる炎に照らされオレンジ色に輝いている。今や、ごうごうという炎の音が聞こえてきそうなほど、暗い海面を昼間のように明るく照らしながら、船はまっすぐこちらに向かっていた。
「あっ」
グリンが思わず声を上げた。沖合に碇泊していたカラベル船から火が上がった。焼き討ち船が接触したのだ。
「帆を張ると風で火が燃え移るんだ」
苦々しげにジェーンレーンはつぶやいた。
湾の中程に停泊しているブルー・マスター号に目をやると、甲板で船員たちが錨を上げようとしているのが見える。操舵長であるオギナの指示が徹底されているのだろう、マストに帆を張ろうとする様子はない。
「よし」
ジェーンレーンはひとつ小さくうなずくと、櫂を持ち直し、グリンにボートを漕ぐように促した。
「どうするんだ?」
その問いに、彼女はむっつりと言った。
「焼き討ち船に乗り込む」
「なんだって?」
あの炎が燃えさかる船に乗り込もうとは、正気の沙汰とは思えない。だが彼女は、ボートを漕ぎながら淡々と言った。
「それしかないだろう。あの船に乗り込み、進路を変えるんだ」
「しかし、無茶な……」
「他に方法がない。このまま私の船が燃えちまうのを、黙って見ていられるか」
私の船というその言葉に、どれほどの重みが込められていただろう。彼女の育ての父、リングローズから受け継いだブルー・マスター号。あの船が燃えたら……彼女はただではいられないだろう。あの船と仲間のためならば、この女海賊は誰よりも勇敢に戦い、そして命をかけるに違いない。
「分かった」
グリンは櫂を握り直すと、彼女とともに力いっぱい漕ぎだした。
沖にゆくにつれ海はやや荒れはじめているようだった。揺れるボートをなんとか操りながら、彼らは焼き討ち船に近づいた。
その周囲はまるで真昼のように明るかった。オレンジに燃え盛る炎が頭上高くから辺りを照らし、ぱちぱちという木が燃える音と、焦げ臭い匂いが辺りにたちこめている。
「よし、この辺でいい。船の横につけろ」
焼き討ち船に平行に並ぶように、慎重にボートを近づける。
燃え上がる炎に照らされて水面は赤く輝き、頭上からはときおり火の粉が舞い落ちてくる。見上げると、上空にはすさまじい煙が上がり、夜空の星々を黒く覆い尽くしていた。
「お前は、ここで待っていてもいいぞ」
ボートの上でジェーンレーンは立ち上がった。たった一人でも船に上がろうという決意であるらしい。彼女はそのまま、焼き討ち船の舷側に手をかけた。
「俺も行く」
彼女を一人で行かせたくなかった。グリンも後を追って、舷側のはしごにへばつりいた。
「うっ……」
船体はかなりの熱さだった。ジェーンレーンは一言も声を上げなかったが、舷側を登るグリンは手が焼けるように感じた。
必死の思いで甲板にはい上がると、そこは炎の海だった。
ごうごうと音を立て燃え上がる炎に、すさまじい煙と熱風……ここはまるで地獄のようだ。
「くっ……ジェーンレーン、どこだ?」
煙で前が見えない。顔を焦がすような熱風から顔をそむけながら、グリンは甲板上を歩きだした。
「こっちだ。ここに舵がある……」
後部甲板に手を振るジェーンレーンの姿が見えた。火を避けながら、グリンはそちらに走り寄った。立ちのぼる熱風で、まだ燃えていないところでも焼けるように熱い。
「……舵が、動かないんだ」
ジェーンレーンは両手で舵をつかみ、それを必死に回そうとしていた。
「う……くそ。……うっ」
だが舵はびくとも動かない。彼女は苦痛に顔を歪ませ、その場に座り込んだ。
「ジェーンレーン!」
「ああ……大丈夫だ」
彼女の手は真っ赤になっていた。その額から汗を吹き出し、肩で息をする様子を見て、グリンは自らが舵の前に立った。
「俺がやる」
ハンドルを握った瞬間、あまりの熱さに思わず彼は顔を歪ませた。
「うぐ……おおっ」
焼けるような熱さに耐えながら、全身の力を込めて舵を回す。
「ああ……ぐ、うう……っ」
手の皮が焦げるようだ。誰か水をかけてくれとグリンは願った。
見上げると、燃え上がる火はすでにマストの帆を焼きはじめている。このままでは少しもたたずにマストは燃え落ち、この船は炎の塊と化すだろう。
「く……そ……」
どうせこのままでは死ぬのだ。半ばやけくそのような気持ちで、グリンは最後の力を振り絞った。
舵がゆっくりと回りだした。
「いいぞ!グリン」
横にいるジェーンレーンの声が気力を支えた。グリンは歯を食いしばり、力を込めて舵を回し続けた。
「そうだ。そのまま、取り舵だ」
湾内を見ながらジェーンレーンが指示をする。
「そうだ、いいぞ……」
船はゆるやかに左に回り始めた。
「いいぞ……そのままだ。グリン」
焼けるような手の平の熱さに、苦悶の呻きを漏らしながらも、グリンは舵を握りつづけた。ジェーンレーンは舷側に乗り出し、ブルー・マスター号との距離を計っていた。
「よし。もう少し……」
焼き討ち船の舳先が向きを変えてゆく。
右舷にはブルー・マスター号がすぐ近くだった。甲板上に手を振る船員たちの姿が見える。彼らにも、この船にいる自分とジェーンレーンの姿が分かったのだろう。歓声がグリンの耳に聞こえてきた。
それに力を得て、グリンは舵を握る手にまた力を込めた。
「よし、グリン。今度はゆっくりと面舵だ。船尾がブルー・マスター号に当たらぬよう、ゆっくりと頼む」
「了解」
反対に舵を回してゆくと、焼き討ち船はブルー・マスター号と平行に並んだ。二隻の距離は、飛び移れそうなほどに近いが、なんとか接触せずにやりすごせそうだ。
そのまま舵を保つと、グリンは耐えきれず手を離した。倒れ込みそうになるのを、横からジェーンレーンが支えてくれた。
「よくやったぞ、グリン!」
その笑顔がグリンには最高の褒美だった。
「よし、もういいだろう。すぐに脱出だ」
炎はすでに、彼らのいる後部甲板にも広がり始めていた。もう船体全てに火が回るまで、そう時間はかからないだろう。
「よし、急ごう」
二人は走り出した。しかし、燃え上がるマストの横を抜けようとしたとき、頭上から焼け落ちた柱が襲ってきた。
「うわあっ!」
ジェーンレーンは、とっさに倒れこんでそれを避けた。
「ジェーンレーン!大丈夫か?」
「ああ……、なんともない……」
彼女は笑ってうなずいたが、焼け焦げたミズンマストの柱が彼女の足の上に倒れていた。
「くそ、抜けない……」
マストは甲板にめり込むように突き刺さり、ジェーンレーンの足首は、それにがっちりと挟まれてしまっていた。
「待ってろ、今……」
「いや……もういい。すぐにここも燃えてしまうだろう。お前は早く逃げろ」
「何を言っている!」
グリンは怒鳴った。それから膝をついて、ジェーンレーンの足に乗った柱を両手でつかむ。
「待ってろ……すぐに持ち上げてやる」
だが柱は相当重く、彼の力ではびくともしない。
「くそ……。待ってろ……すぐに持ち上げて……くっ」
「いいから。早く行け……死ぬぞ」
煙と炎がそこまで近づいていた。マストを持つ手も、床に着いた膝もひどく熱い。煙のせいか息が苦しく、頭が朦朧としてくるようだった。焼けるような熱さに耐えながら、グリンは柱を持ち上げようと力を込め続けた。
「私はもういい……。船が無事ならな、それでいいんだ……」
ジェーンレーンは薄く微笑み、そう言った。
「馬鹿を言うな。俺は……嫌だ」
グリンは歯を食いしばり、睨むように彼女を見ると、焼け焦げたマストの下に手を入れ、ありったけの力を込めた。
「無理だ……お前まで、死ぬぞ」
「それなら……それで、いいさ」
グリンはにやりと笑った。
「俺は、船よりも、君が……」
「グリン……」
手の皮が焼けるのもかまわず、マストを持ち上げようとする彼の姿を、ジェーンレーンはじっと見上げた。歯を食いしばり、足を踏ん張りながら、グリンは決して手を離そうとはしなかった。
「う、おおお」
ついに、グリンの雄叫びのような掛け声とともに、柱がわずかに持ち上がった。
「早……く……」
持ち上げられた隙間から、ジェーンレーンは足を引き抜いた。手を離すと、焼けた柱が甲板にめり込んだ。
「グリン……」
汗をびっしょりとかいて、肩で息をするグリンの顔を、彼女はしばし、呆気にとられたように見つめていた。
「足は平気か?」
「大丈夫。その……助かった」
小さく礼を言った彼女に、グリンはにこりと笑い返した。
「よし。早く行こう……」
今にも床が焼け落ちそうな甲板の上を走り、二人は燃え上がる船から海へと飛び込んだ。夢中で泳いでボートに上がると、二人は櫂をとり、漕ぎはじめた。
「ジェーンレーン。船が……」
ボートから振り返ると、船体のいたるところから炎が上がりはじめ、「ごごごこ」という、不気味な音が海上に響き始めていた。
「とにかく、船からできるだけ離れるんだ。積んである火薬が爆発するようだぞ」
二人は無我夢中でボートを漕いだ。
焼けた手の痛みに半ば朦朧となりながら、グリンは櫂を動かし続けた。少しずつ、焼き討ち船の炎が後方に遠くなる……
巨大な炎の塊と化した船が最後のときを迎えた。ドーンという爆音とともに、焼けた火の粉が四散し、空に舞い上がった。彼らのボートの近くにも、ポチャン、ポチャンと、船の板切れが舞い落ちた。
「なんとか……助かったな、ジェーンレーン」
返事はなかった。ジェーンレーンは櫂を握ったまま気を失っていた。グリンの方も気力の限界だった。炎に照らされる夜の海を見ながら、やがて彼もボートの上に倒れこんだ。
気がつくと辺りは暗かった。
暗がりの中で、ちゃぷちゃぷという水の音が聞こえている。
(ここは……)
グリンは寒さにぶるっと体を震わせた。
服がぐっしょりと濡れていた。そして、ひりつくような手の痛みに顔をしかめる。手の皮がむけ、火傷のように赤く腫れていた。
頭のなかで、ゆっくりと思い出される映像……
焼き討ち船の燃え上がる紅蓮の炎、そして爆発……
ゆっくりと上体を起こしてみる。
ここはボートの上、周りは暗い海だ。そして隣には……
「ジェーンレーン……」
ボートの上に長い赤毛が広がっていた。目を閉じた彼女がそこにいた。どこかに怪我を負った様子はない。
「無事で……よかった」
ジェーンレーンのまぶたがかすかに動いた。濡れそぼった髪が頬にまとわり、サンゴ色の唇がうっすらと開かれ、その胸はゆるやかな呼吸に上下している。こんな時に見ても彼女は美しかった。
「ここは……どのあたりなんだろう」
グリンは改めて周りを見回した。漆黒の海の他にはなにも見えない。ただ、空はかすかに明るさを増してゆくようで、おそらく今が夜明けに近いだろうことを物語っていた。
少なくとも近くに陸地のある気配はないようだ。船の明かりも見えない。キーオス島の沖合からどのくらい流されたのだろう。
櫂をとろうとしたグリンは、焼けつくような手の痛みに、思わず呻いた。それも仕方がない。燃えるような熱さの舵を握り、ジェーンレーンを助けるため、焼けるマストをつかみ、持ち上げたのだ。
「よく助かったもんだ……」
まるで地獄のような火炎の中で、船を動かし、女海賊を助け、海に飛び込んで命からがら脱出したなど、とうてい前の自分であれば想像もできなかったことに違いない。こんな危険な冒険に、自分が実際に身をさらすことになるなどとは、物語や夢の中でしか考えられなかったことだ。
その証である、焼けただれた自分の手を見て、彼は思わず笑いを浮かべた。そしてあのとき、自分が勇敢にふるまえたことが誇らしく思えた。
(ジェーンレーン……)
自分の隣には、美しい女海賊が目を閉じて横たわっている。彼女を見ていると、たとえここがどこであろうとも、「なんとかなるにちがいない」と思えてくる。
水平線の彼方から太陽が登りはじめたころ、ジェーンレーンが目を覚ました。
「ああ……ここは、……どこ?」
目を開けた女海賊は、傍にいたグリンに気づくと、体を起こした。
「海の上だよ。どうやら流されたらしい」
「ああ……」
ジェーンレーンは何度か目をまばたかせ、まぶしそうに朝日に手をかざした。
「そうか……助かったのか」
彼女も、昨夜の事を思い出したようにつぶやいた。濡れた髪をかき上げて自分の姿を見下ろすと、ぷっと吹き出した。
「なんて恰好だろう」
燃えさかる焼き討ち船の甲板を駆け回り、海に飛び込んだのであるから当然であったが……彼女の服は、焼け焦げや破れでボロボロになり、ひどい有り様だった。それはグリンの方もたいして変わらなかったので、ジェーンレーンは次にグリンを指さして、けらけらと笑い声を上げた。
「ああ……でも、そうか。私達は助かった。たぶんブルー・マスター号も無事だろう」
笑いをおさめると、彼女は改めてグリンを見た。感謝をたたえたまなざしが、微笑みかけていた。
「お前の、おかげだな……」
「いや……」
グリンは照れくさそうに頭を掻いた。
(俺は、船よりも君が……)
彼女を助け出すときに思わず口から出た、自分の言葉を思い出し、顔を赤らめながら。
「……ところで、ここはどのあたりなんだろうな?」
海面を見回し、ジェーンレーンはつぶやいた。
「ああ、俺もそれを考えていたんだが……」
「なにも……見えないな」
ジェーンレーンの言うとおり、周りは一面の海。それだけだった。
四方を見渡しても、陸地はおろか島陰すらも、まったく見当たらない。昇りゆく太陽の他には、方向を見定めるものはなにもない。ただ青々と広がる海面が、どこまでもどこまでも続いているだけだった。
櫂が流されずに残っていたのはいいが、いったいどちらに進めばいいのか。それすらも分からない。
「ジェーンレーン……」
不安に顔を曇らせるグリンを見て、ジェーンレーンはうなずいた。
「とにかく……だ」
四方の海面をしばらく見渡していた彼女は、現在の状況をだいたい頭の中で整理したのか、ボートの上にどっかりと座りなおした。
「キーオス島から流されて、まだあまり時間がたっていないはずだ。あのときの潮の流れを考えれば、今ここがどのあたりなのかは、だいたいの見当はつかなくもない」
さすがは海賊船の船長として長年やってきただけあり、彼女はいたって冷静に分析した。
「幸い櫂もあるし、方向さえ間違わずに漕げば、いずれは陸地なりどこかの港なりにたどり着けるはずだ。問題は……水だな」
「水……」
「数日間なにも食べなくともどうということはないが、水がないと……おそらく五日はもたないだろう。それまでに、どこかの船に見つけてもらうか、うまく陸地か島にでも辿り着けなければ……」
静かな口調だったが、ジェーンレーンの言葉には、船乗りとしての海に対する畏怖が感じられた。海上の遭難の怖さを、彼女は実感として知っているのだ。
グリンは、いかに自分がいままで、恵まれた中での航海しか経験したことがなかったかを思い知った。騎士団の大型ガレオン船には、食料も水も酒もたっぷりとあり、船酔いとマストのロープ引きを苦痛に思いながら、あたたかい食事をし、綺麗な寝床で休むことは、どれほどの贅沢であったろうか。
「とにかく、少し休んだら漕いでみよう。このまま、ただ流されているよりはマシだろう」
ジェーンレーンは濡れた上着とブーツを脱ぐと、ブラウスの袖を細く破ってそれで髪を束ねた。
「もしかしたら、案外早くブルー・マスター号が見つけてくれるかもしれないぞ」
自分を元気づけるような彼女の言葉に、グリンはうなずいた。
どのくらい進んだのか。だが、いっこうに陸地は見えなかった。
漕いでも漕いでも、見えるのは、いつまでたってもただ青々とした海ばかり。まるで体を小さくされて、青一色の世界に放り出されたような気がするほどだ。
日中は太陽の方向を見ながら、二人は西をめざしてボートを漕いだ。といっても、櫂を握るのがやっとグリンよりは、ほとんどの時間はジェーンレーンが漕いでいたのであるが。
彼女の考えでは、この潮の流れを考えると、キーオス島に戻るよりは、むしろ流れに乗って西へゆき、別の島を目指したほうがいいということだった。キャスタナル諸島の西側には、海賊たちのアジトが点在しており、うまくすればジェーンレーンの知己である海賊のいる島にでもたどり着けるだろうというのである。また、そのあたりにはブルー・マスター号が補給のためによく立ち寄る島もあり、見つけてもらえる可能性も低くはないはずだと彼女は説明した。
二人は体を休めながらボートを漕いだ。おそらく一日か二日で島が見えてくるはずだと、ジェーンレーンは考えているようだった。
日中日差しが強くなると、二人はボートに寝ころび、上着を頭にかぶせて休んだ。水も食料もないので、余分に体力を消耗するのを避けなくてはならない。太陽が雲に隠れると、二人は起き上がってボートを漕いだ。
やがて海に黄昏が訪れた。
巨大な円盤が海の彼方に沈みゆくのを、二人はボートの上から眺めた。紫と赤と紺色の混じった盛大な夕焼けと、最後の残照を放つ黄金色に輝く海面を見ながら、二人は櫂を動かした。
日が沈むと、海上はぐっと涼しくなった。
二人はしばらく手を休め、星の美しい夜空を見上げた。こうして落ち着いてみると、ジェーンレーンとたった二人で、小さなボートの上に肩を並べて座っているという事実に、こんな際ではあったがグリンの胸はざわめいた。
ふと彼女の方を見ると、ジェーンレーンの横顔は変わらず穏やかに見える。どこへ向かうのか分からないまま潮に流されるボートの上で、彼女はつんと顎を持ち上げ、口をまっすぐに結び、ときに艶然と微笑みさえする。グリンは、それに感嘆を覚えずにはいられない。女海賊ジェーンレーンは、どんなときでも誇り高く、勇敢で、そして美しかった。
「どうした?私の顔になにかついているか?」
「ああ……いや」
振り向いた彼女に、照れたようにグリンは櫂をとった。こうして二人……海の上にいるのも、まんざら悪くもないなと考えながら。
翌日になると、二人はまた交代でボートを漕ぎつづけた。
だが、やはり行けども行けども、陸地らしきものはその影すらも見えない。そのうちに空は曇りはじめ、風も出てきた。昨日のうちは、二人きりの漂流も楽しいかもしれないなどと、甘く考えていたグリンであったが、飲まず食わずで海の上で過ごすのは、さすがに体力が続かなかった。
「大丈夫か?少し休もう」
「ああ……すまない」
女であるジェーンレーンに気遣われることが、情けなく思えた。何も食べていないのは彼女も同じだというのに。
二人は櫂をおいて、ボートに座り込んだ。
「ここはどのあたりかな?」
四方に見えるのは延々と続く青い海原。聞こえるのはただ、風と波の音だけである。
「さあな……しかし、大洋のど真ん中ということはないだろう。マロック海自体、そう広大なわけではない。二三日すれば、きっと……どこかには着くはずだ」
「そうだな」
グリンは、希望を抱いた顔つきでうなずいてみせた。彼女にしても、確信を持っているわけではない。内心で不安なのは同じなのだ。
その日は日が沈むまでボートを漕いだ。西へ、ただ西へと。
夜になると、二人はボートに向かい合い、いろいろな話をして過ごした。体力を使わないためには黙っていた方がよいのだろうが、こみ上げてくる不安をまぎらわせるには、何かを話していたほうが楽だった。
グリンは、ずっと気になっていた、彼女の額の傷のことを尋ねてみた。
「つまらないことを聞くね。こんな時に」
ジェーンレーンはふっと笑い、眉間に手を触れた。
「これはね……十七のとき。独り立ちするにあたっての最後のテストとして、おやじと剣で戦ったときのものさ」
思い出すように、彼女は目を閉じた。そうすると端麗な顔だちの中で、×の字につけられた眉間の傷跡が、ひどく目立って見えた。
「それで……負けたのか?」
「いいや。勝ったさ。勝って油断しているときに、おやじがいきなり私の顔に切り付けたんだ。これが、合格の印。これが海賊になった印だってね」
ジェーンレーンはかつてを懐かしむように、薄く笑みを浮かべた。
「そのころは、ちょうど親父に反抗している時期でね。叱られるたびに、いちいちうるさいんだよコイツは、って思ったり……側にいるだけでうざったいとかね。だから、顔に傷を付けられて、そのときはとても怒ったけど、今思うと……おやじは、おやじも迷っていたのかもしれない。私を育てながらね。おやじはいつも言っていたよ。お前を海賊にするよりも、あのとき殺していたほうが、もしかしたらずっとお前のためだったかもしれない、ってね。そのときはよく分からなかったけど、今はときどね……確かにそうかもしれないと思うときがあるよ」
そう言った彼女の顔は、なんだかはかなげに見えた。
「こうして漂流しているときとかも、そう思うんだろう?」
グリンが少し冗談めかして言うと、彼女はくすりと笑い、
「そうだね。でも……」
星空を見上げながら小さく言った。
「私はね、生きていて良かったと思うよ。海賊になって、よかったと思うよ」
「ああ……」
グリンも一緒に空を見上げた。星空を覗き込むように、彼女が見ていたのは、幼い日の自分だったのか……
「私が、もしおやじだったとしても……」
その囁きは、彼女の自分自身への……自分という存在への問いかけだったのか。
「やっぱり殺さなかっただろう」
そのときに彼女が見せた、泣き顔のような、あるいは微笑のような顔を、グリンはずっと忘れられなかった。
月が高く昇った夜空のもと、
チャプチャプという水の音を聞きながら、しばらく二人はなにも言わずに、ただボートの上にじっと寄り添っていた。
三日目になると、にわかに海が荒れだした。
強風はときに横凪にボートを襲い、ときに向かい風となって、彼らの行く手を阻んだ。二人の乗る小さなボートは、強い潮の流れの前には、ただの無力な木片にすぎなかった。
太陽は灰色の雲に覆われ、ゆくべき方向すらも分からない。そして飲まず食わずでボートを漕ぎ続ける力は、二人にはもうあまり残っていなかった。
ボートは流された。
ついに二人は櫂を置き、無駄な努力をやめた。少なくとも風と波がおさまるまでは、何をやっても無意味に思えた。
グリンは膝を抱え、ボートの上でうずくまった。喉はからからに乾いていた。櫂を持ち続ける腕もびどく痺れていた。話をする気力もない。それは横にいるジェーンレーンも同じようだった。
二人はぐったりとなり、ボートから荒れる海を見据えて、ただじっとしていることしかできなかった。いったい、自分たちはどこへ向かっているのか。この先に陸地はあるのか。そうした不安が、時間とともに確実に大きくなってゆく。
日が沈むころになって、ようやく少し風がおさまってきた。だが二人はまだ起き上がる気力もなく、ボートに寝そべっていた。
このままで、あとどれくらい気力と体力が持つのだろう。グリンの心には、再び絶望的な不安と、どうしようもない恐怖とが渦巻きだしていた。
「しかたないな……」
ゆっくりと、ジェーンレーンが体を起こした。
「なるべくぎりぎりのときまで残しておこうと思ったんだが……」
「あ……み、水?」
彼女がベルトの裏側から、小さな水筒を取り出すのを見て、グリンも飛び起きた。
「ああ。こういうときのために、いつも身につけているんだ。二人で分けるとほんの少しずつだが、今日明日くらいはこれで命がつなげられるだろう。……そら」
ジェーンレーンは水筒をグリンに渡した。
小さな水筒を手にしたグリンは、恐る恐るその蓋を開けた。軽く振るとちゃぽちゃぽと音がする。彼女の言うとおり、二人で分けるなら、ほんのわずかな量でしかないようだ。
「……」
「どうした?飲め」
「あ、ああ……」
グリンはごくりと喉をならした。水筒を持つ手が震える。
「なにを遠慮している。私はまだ大丈夫だ。しばらく水を飲まなくても平気なように、おやじから訓練もされた。だがお前はそう……ただの商人だろう」
ひりつくような喉の渇きは、我慢できないくらいまでにきていた。一口でも飲めば、きっと生き返るほどに心地よいに違いない。
しかし……
(お、れは……)
グリンの中で、何かが声を上げていた。
(俺は、商人なんかじゃない……)
(俺は……)
肉体の苦痛を上回る、ある種の感情……失いかけていたものが呼び起こされてゆく。
(俺は、騎士だ)
それは、ひとことで言うなら、「誇り」であったかもしれない。そしてまた、男としての意地だったのかもしれない。
「……」
グリンは水筒の蓋をしめると、それをジェーンレーンに返した。
「……飲まないのか?」
「ああ……。君が飲まないのなら、俺も飲まない」
「なんだ?なにを恰好つけているんだ。私は平気だと言っているだろう」
「いや……大丈夫だ」
グリンは強情そうに首を振り、またボートに横になった。それを奇妙な目で見ながら、ジェーンレーンは懐に水筒をしまった。
翌日になると、風と波はすっかりおさまっていた。だが、そのかわりに、照りつける太陽が二人を苦しめた。
渇きに耐えながら、陸を目指して櫂を動かし続けるが、やはり、四方にはいっこうに島影は現れなかった。気力と体力は徐々に奪われ、二人は櫂を下ろして、延々と続く海面を呆然と見ていることが多くなった。
朦朧としてくる意識で、なんとか少しずつでも進もうと、重たい櫂を持てないときは、海面に手を入れて漕ごうとしても、それも長くは続かない。二人は疲れ果て、のどの渇きに声も出せずにぐったりと膝を抱えるしかなかった。
その夜、ジェーンレーンは水筒を取り出し、それを押しつけるようにグリンに渡した。
「もう限界だな。水を飲め」
だが、差し出された水筒に見向きもせず、グリンは首を振った。
「いや。大丈夫……だ」
「どこが大丈夫だ!いいかげんに……」
いらいらしたようにジェーンレーンは言った。
「お前がくたばったら、私は……」
「……」
「……私は平気だから。さあ、飲め。いっときでも楽になる」
女海賊の懇願にも似た言葉にも、グリンは断固として首を振った。
「何故だ。どうして……」
「あんたは……」
ぐったりと、死んだように目を閉じていたグリンが、顔を上げた。
「あんたは……女だろう」
「だから……どうした」
「俺は男だ。だが女は……いつかは、きっと誰かのお母さんになるんだから」
「なんだって?」
頓狂なことを聞いた様子で、ジェーンレーンは何度か目をしばたたくと、笑い出した。
「ははっ……面白いことを。お母さんだって?」
「そうだろう。女性は……いつかは誰かの恋人になり、誰かの妻になり、そして、お母さんになるんだ。だから……だから、大事に守らなきゃならないんだ。違うか?」
二人の目が合った。
水筒を手にしたまま、ジェーンレーンは目を白黒させていたが、それから馬鹿にしたようにグリンを見た。
「ははあ……。へえ。それじゃ、この、赤毛のジェーン姐さんも、いずれその、お母さんてやつになるっていうのかい?あんたは」
「ああ。そうかもしれない」
ジェーンレーンは、また笑い飛ばすか、それとも何か言い返すか決めかねたように口を歪めていた。だが、グリンの目つきがあまりにも真剣だったので、結局そのまま黙りこんだ。
「俺は、いつも母にそう教わったよ」
静かにグリンはつぶやいた。
乾ききった唇からは、しわがれたかすれ声しか出なかったが、グリンは、己の信ずる矜持をジェーンレーンに語った。
「女の人を大事にしろって。どんなときでも女性を助けてやれる男になれって。女の人は……たとえどんな女の子でも、時がたてば、いつかはきっと大切な子供を産み、誰かのママになるんだからと」
「……」
ひどく奇妙なものを見るように、彼女はじっとグリンを見つめていた。
「だから……俺だけ先に水を飲むことはできない。だって、俺は……俺は男なんだから」
本当なら、「騎士」だからとも言いたかったのだろうが、グリンはそれを口のなかで呑み込んだ。
しばらく、ジェーンレーンは、なんと言ったらいいものかと思いあぐねるように、じっと黙っていた。
「……あんたの母上は」
それから、彼女は口をひらいた。その声には少し戸惑いの響きがあった。
「さぞ立派な人なんだろうね。今でもよく言われるのかい?」
グリンは首を振った。
「母は死んだよ。俺が十四のときに」
「そう、か……」
ジェーンレーンはそれきり黙りこんだ。
グリンの話した言葉は、冗談で笑い飛ばすべきものではなく、それが彼にとって神聖な事項に属するものであることは、彼女にも分かったのかもしれない。
夜空を見上げると、雲間から月が顔を出していた。
波が、ちゃぷちゃぷと音をたてる。小さな二人乗りのボートの周りには、黒々とした海ばかりが広がっている。
話し終えて力が尽きたのか、グリンはボートの上に上体を倒していた。彼はついに水筒に手を伸ばさなかった。
「……眠ったのか?」
囁くようにジェーンレーンは言った。
「水を飲まないと死ぬぞ」
だが、いらえはなかった。グリンはもう死んだように動かなかった。かろうじて、その胸が呼吸に上下している。
「……なんて、強情なやつだろう」
呆れたように一人つぶやく。
「それに、お母さんだって?そんなこと初めて言われたぞ。ふふ」
自分よりもいくつも年若いはずなのに、海のことなどまだよく知りもしないくせに、どうしてこの男は、こんな真面目な顔で説教じみたことを言うのだろう。
「面白いやつ」
くすりと、ジェーンレーンは笑った。
「四五日くらい、水を飲まないのには慣れているのに。私は……」
いったん櫂を取ろうとした彼女だったが、思い直したようにまたグリンの横に座った。
「……」
目を閉じて動かないグリンを覗き込む。内心では何をしたいのかを知りながら、それをためらってでもいるかのように、
「馬鹿だな……」
彼女は震える声で囁いた。乱れかかったグリンの髪をそっと撫で、水筒の水を口に含む。
「……」
おそるおそる、横たわった騎士の上に覆いかぶさる。そして、ゆっくりと顔を近づけた。
水面に映った月が、ゆらゆらと揺れている。
ボートの上の二人は、しばらくそうして、静かに重なっていた。
(……)
喉が心地よく潤う感触に、グリンは薄く目をあけた。
それが夢なのか幻なのか、彼には判断がつかなかった。意識が朦朧となり落ちてゆく前に、顔を離したジェーンレーンの、かすかに微笑んだ顔が見えた気がした。
(グリン)
自分を呼ぶ声が聞こえる。
それでは、まだ自分は死んではいなかったのか?
(グリン)
誰かが呼んでいる。自分の名を。
それとも、これはまだ夢なのだろうか。
自分はボートで漂流していたはずだ。水も飲まず、喉がカサカサに渇き、疲れ果て、意識が遠のき……
そして……
自分は……、夢を見ているのかもしれない。
あるいは、漂流したことそのものが、本当は夢で、自分はまだ船室で眠っているのだろうか。
船……。海賊船……
いや……
騎士……そう、騎士だ。
栄えあるアナトリアの騎士。
きっと、自分は「海賊になった」夢を見ていたのだ。
物語の中の海賊たちの伝説にあこがれて。こうして夢の中で、美しい女海賊と出会い、冒険と危険に満ちた海へのりだし……、
そして……
そして、自分はこれから目を覚ますのだ。
起きれば、きっとそこは見慣れた騎士団の宿舎か、それとも初めての航海に臨むガレオン船の船室のハンモックか……
そうにちがいない。
きっとそうに……
(グリン)
まだ声が聞こえる。
今度のは、さっきよりもずっとはっきりと……その声が
「グリン」
友人か仲間の騎士が、自分を起こそうとしているのだろう。
自分は……目を覚ますのだ。
また、騎士としての日常が待っているだろう。
平穏な航海を続けながら、心のどこかで海賊や冒険に憧れる……そんな日々が。マストのロープを引き続ける、退屈だが、それなりに充実した平凡な日々が……
「グリン」
ああ、分かっているよ。そろそろ起きなくては。
でも、なんだかとても眩しい。ここは海の上なのか……
目を開けたら、「海賊になった夢を見ていたよ」と、仲間たちに話してやろう。皆きっと笑うだろう。
「起きろ……グリン」
「ああ……分かったよ」
しわがれた声が、口から漏れる。
これが……俺の声なのか?
なんだか、ずいぶん聞き慣れない……低くかすれたような声だ。
「……う」
グリンは呻いた。
眩しさに腕を顔に当て……その目を薄く開ける。
「起きたか、グリン」
「ああ……ここは」
まず目に入ったのは、真っ青な空。そして聞こえるのは……ちゃぷちゃぷという水の音。
「寝ぼけているのか?おい……早く起きろ」
そう言って、自分を起こすのは誰なのだろう?
仲間の騎士でもなく……上官でもなく、
「う、ああ……」
「どうした?大丈夫か」
ゆっくり目を開くと、自分を覗き込む顔が間近にあった。
「ああ……」
「よし、では起きろ。グリン」
毅然とした、強い響きの声だ。相手の顔が、だんだんとはっきりとしてくる。自然と口から名前が出た。
「ジェーン……レーンか」
「他に誰がいる。おい……本当に大丈夫か?まさか頭がどうにかなったのじゃあるまいな」
くすりと笑って首をかしげるその肩から、赤い髪がこぼれ落ち、グリンの頬をくすぐった。
「いや……大丈夫だ」
霧がかかっていたような頭の中が、徐々にはっきりとしてくる。グリンはゆっくりと上体を起こした。
「ジェーンレーン。俺は……生きてる」
「ああ。そうだ」
女海賊はにこりと笑ってそこにいた。
まぶしさに慣れてきた目で、晴れ渡った空を見上げると、これがまぎれもない現実なのだと、グリンは実感できた。
「グリン。船だ」
「なに?」
いったいなんのことか、分からなかった。
「船だよ」
もう一度繰り返すと、彼女はグリンの肩に手をやり、一方の手で海を指した。
「船が見える」
ジェーンレーンの指の先へ、グリンも目を向けた。
すると、
「おお……」
確かに見えた。
まだかなり遠いが……帆を広げた船影が。
「ジェーン……レーン」
「ああ。船だよ。グリン、助かったぞ!私達は」
ジェーンレーンは弾んだ声を上げ、グリンの肩を叩いた。
「漕げるか?グリン」
「……ああ」
いったんは失われかけていた希望と、そして気力が、再び少しずつ自分の中に沸き起こるのを感じた。
「漕げるとも!」
生への渇望が、彼らの目に輝き取り戻した。
二人は櫂を取り、まだ遠い船影に向かって、そして、近づいてくる希望に向かって、力いっぱいボートを漕ぎはじめた。
■次ページへ