ブルーランド・マスター
9/11ページ
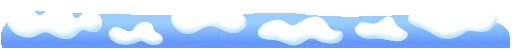
■9■ ドルテック海賊団
いったいどこに、これほどの体力がまだ残っていたのだろうかと、自分でも驚くほどだった。グリンの腕は、力強く櫂を動かし続け、ボートはぐんぐんと進んでいった。
ジェーンレーンも、漕ぎながら時々前を見ては、船の存在を確かめた。彼女にしてもグリンにしても、目を離した間に、その船がふっと消えてしまっているのではないかという、わけもない不安を感じないではいられなかったのだった。
だが、遠くに見えていた帆船は、しだいに、その船体や帆の形までがはっきりと判別できるようになった。それは三本マストの大型船であった。
「こっちに来るぞ。見つけてくれたんだ!」
櫂を手に、グリンは歓声を上げた。
このボートに気づいたのか、船はゆるやかに向きを変えはじめていた。希望に沸き立った二人は、勢い込んでボートを漕いだ。
やがて二人の眼前に船の姿が大きくなった。もう海に飛び込んで泳いでいっても、たどり着けるというほどの距離である。
それはなかなか見事なガレオン船だった。
三本マストに高々とはためく四角帆、船首には女神のヘッドフィギュアが飾られ、突き出したバウスプリットは長く鋭く尖っている。もしこれが商船であるなら、よほど大国のものであるに違いない。
「助かった。ジェーンレーン。俺たちは助かったぞ!」
船を見上げ、弾んだ声を上げるグリンだったが、ジェーンレーンの方は何故か無言だった。彼女は櫂を動かす手を止め、その視線をじっと船の方に注いでいる。
「どうしたんだ?……ジェーンレーン」
振り返った彼女の眉がつり上がっていた。その顔には、先程までの喜びの色は微塵もない。
「あれを……見ろ」
眉間に皺を寄せ、彼女は指さした。
「まさか、こんなところで……な」
ジェーンレーンは苦々しげにつぶやいた。
彼女が指しているのは、船のマストにはためくものだった。
「あれは……ジョリーロジャー」
グリンもそれに気づいた。
旗の模様は、
「骸骨と砂時計……」
ゆっくりと口に出す間に、グリンの顔もしだいに蒼白になっていった。黒地に骸骨と砂時計の模様は、マロック海の船乗りたちが、もっとも恐れなくてはならないものであった。
「ドルテック……」
震える唇でグリンはつぶやいた。さきほどまでの沸き立つような喜びと希望は、一瞬のうちに消え去った。
ドルテック海賊団。マロック海で最も残虐非道な海賊たち……
呆然と見つめる彼らの前で、海賊船の船体の砲門が次々に開かれた。まるで悪魔の使いのように、恐ろしげな武装ガレオン船が、二人の乗るボートに迫っていた。
(ああ……)
殺戮と恐慌の記憶が、グリンの中で甦る。
「ジェーンレーン!どうする。逃げるか?」
「無駄だ。こんなボートではすぐに捕まる。それに、奴らは躊躇なく大砲を撃つだろうさ」
櫂を投げ出したジェーンレーンは、むっつりとつぶやいた。
「まったく、運がいいのか悪いのか。まさかドルテックの奴に捕まるとはな。はっ……待遇はともかく、せめて水と食料くらいはくれればいいがな」
その間にも、砲門をむき出しにした海賊船は、ボートの上の無力な二人を威圧するように、その船体を大きくしていった。
「まさか、おめえだったとはな」
黒いあごひげの海賊が、驚きまじりの顔で声を上げた。
後ろ手に縛られたグリンとジェーンレーンは、海賊船の甲板に引き上げられると、銃や短剣を持った海賊たちに取り囲まれた。
「まったく驚いたぜ。ただの漂流者かと思ったら……助けてみりゃあ、麗しのジェーンレーン姫さまときた。こいつはとんだ拾いもんだぜ。なあ」
ちぢれた黒髪を後ろに束ね、伸びたあごひげを撫でつける、筋肉質の海賊……マロック海のすべての船乗りから恐れられる、ドルテック海賊団の首領がそこにいた。
「わが、キャッスル・オブ・リベンジ号へようこそ」
そう言って、海賊はにやりと不敵に笑ってみせた。左目と右の頬にある、いかにも歴戦の古傷らしき傷跡も恐ろしげに。
「男ばかりのむさくるしい船だが、勘弁してくんな。なに、アジトへ着くまでの辛抱だ。そうすりゃ、あとはたっぷり……」
ドルテックは口元に下品な笑いを浮かべ、ジェーンレーンを舐めるように見回した。
「ところで……そっちの若造は、お前の新しいコレかなんかか?」
いやらしい顔つきで海賊が親指を立てて見せると、ジェーンレーンはふっと笑いを浮かべた。
「まあ、そんなところだ」
それを聞いて、ドルテックは黄色い歯をむき出し、ナイフを閃かせた。
「そうかい……こいつがな」
刃先をグリンの頬に突きつける。
「よく見るとまだガキじゃねえか。赤毛のジェーンレーンともあろうものが、こんなひよっこを愛人にしてるとは、とんだお笑いぐさだな」
「……」
冷たいナイフをぴたぴたと頬に当てられ、グリンは顔をこわばらせたが、すぐに口元を引き結んだ。この黒髭の海賊は、かつてタンタルス号を襲い、仲間たちをなぶり殺した、憎むべき仇なのだ。
「なんだか反抗的なぼうやだな。その目はなんだ?ああ?」
海賊は鼻に皺を寄せ、獰猛な笑みを浮かべた。
「ムカつく野郎だな。おい、ガキ!てめえの方には用はねえんだ。なんならいますぐ、ここで切り刻んで魚のエサにしてやってもいいんだぜ?ええ、ぼうや」
その言葉は脅しではあるまい。残忍無比なこの海賊であれば、やるといったらやるのだろう。
「……」
あの船倉での残酷な光景がグリンの脳裏に甦る。背中に汗が伝った。彼は海賊から目をそらした。
「けっ、根性なしが。半端にいきがるんじゃねえよ」
海賊はぺっと唾をはいて、馬鹿にしたように言い放つと、もはやグリンには何の興味もなくなったように、ジェーンレーンの方に近づき、馴れ馴れしくその肩に手を置いた。
「さあて、どうする?ジェーンレーン。すべてはおめえの気持ち次第だぜ。このガキが生きるも死ぬも、な」
「……」
ドルテックが何を言いたいのか、おおよそ察しはついているようだった。彼女は顔を近づけた海賊から、ぷいと目をそむけた。
「しかしまあ……なんとも色っぽい恰好だ。そんなボロボロになったシャツは、いっそ脱いじまった方がよくねえか?」
そう言って、ドルテックはガハハと笑い声を上げた。
(くそ……なんでこんなことに)
グリンは心の中でつぶやいた。
助かったと喜んだのも束の間、ボートで漂流するよりも、むしろもっと悪い相手に捕まってしまうとは。じわじわと悔しさと怒りが込み上げてくる。だが喉は渇き、体は弱り果てていた。逃げることはできそうにない。なにより、周りには数十人の海賊たちがこちらに銃を向けている。
これから自分はどうなるのか。そして彼女は……
「さて、とにかく、こっちのガキは船倉に閉じ込めておけ。島に着いたら牢屋で飼ってやる」
「へい」
命じられた二人の海賊が、両側からグリンに銃を突きつけた。
「さて、ジェーンレーン。お前さんは、どうするんだったかな?」
意地悪そうにドルテックは訊いた。
「私も一緒に船倉に入れないのか?」
「めっそうもない」
海賊は、わざとらしく両手を広げてにやにやと笑っていた。
「美しいジェーンレーン姐さんを、まさかしみったれた船倉なんかに。とんでもない!お前さんはここだ。俺の傍にいるんだよ。いっときも離れずな。じきに島に着く。俺のアジトよ。そうしたらもう逃げられねえ。おめえはそこで、俺と暮らすんだ」
「……」
「今までも何度となくそう誘ったよな。リングローズの親父がくたばってから。だが、今度こそおめえは俺のものになるんだ。こんなチャンスはもうのがさねえよ。島に帰ってから、たっぷりと楽しませてやる。徹底的にな」
いやらしい目つきで体を見回す海賊を、彼女は眉をつり上げて睨みつけた。
「もちろん、島に着けばその縄を解いてやるし、新しい服もやるぞ。温かい食事と酒、それに豪勢なベッドも。なんでもな。だが……」
ドルテックの目がぎらりと物騒に光った。
「それとも……そんなに船倉がいいのか?あいにく、船倉には戦利品の樽やら箱、それに豚や鶏がいっぱいでな。一人分しか入れる余裕はねえんだ。それでも船倉に入りたいなら……、このぼうやの方は他に置いとく場所がねえな……」
グリンの方を指さし、歯をむき出してにっと笑う。
「そうなったら海に放り込むしかねえな」
明らかに、それは「自分と一緒にいろ」という脅迫にほかならなかった。ジェーンレーンはぐっと口を引き結んだ。
「さあ、どうする?決まったかな。船倉か、それとも俺の隣か」
黒い髭を撫でつけながら、海賊は粘ついた目で彼女を見、声を荒らげた。銃を突きつけられたグリンは、なにもできぬ自分の情けなさに歯を食いしばった。
「早くしろ!」
ジェーンレーンは顔を上げた。
「……分かった」
「そうこなくちゃ」
海賊はバチンと手を叩いた。
「さすが頭のいい女よ。これからは俺の女になれ。この俺さまの片腕にしてやる」
「だが、ひとつだけ……頼む」
「いいとも。なんだ?」
ジェーンレーンはちらりとグリンの方を見た。
「この者に……水と食事をやってくれ」
「なんだ、そんなことか。ああ、いいとも。お前が俺の言うことを聞くというならな」
「やめろ。ジェーンレーン」
グリンはたまらず声を上げた。
「俺は大丈夫だから。こいつの言いなりになどなるな」
「てめえはだまってろ!誰が話していいって言った。この場でブチ殺すぞ、ガキが!」
海賊は片手でグリンの胸ぐらをつかみ、締め上げた。
「うっ……」
「ドルテック。私は分かったといっただろう。グリンに……手を出すな」
「ああ、そうだったな」
ジェーンレーンの言葉に、海賊は手をゆるめ、ぺっと唾をはいた。
「まあいいんだよ。こんなガキのことは、どうでもな」
グリンは唇を噛みしめた。
(くそ……)
ひりつくような喉の渇きに、頭が朦朧としてくる。いっそのこと、ここで自分が死ねば、ジェーンレーンの重荷にはならずに済むのだろうか。
(海に飛び込むか……)
両側の海賊を押しのけて、このまま甲板から飛び込めば……
そう考えていたとき、ジェーンレーンがこちらを見た。
(……ジェーンレーン)
ほんの一瞬、二人の目が合った。彼女は、軽くこちらにうなづきかけた。それは「自分は大丈夫だ」という、合図のようだった。
己の無力さに歯噛みする思いで、グリンは行動を思いとどまった。
「ようし。では、ガキは船倉だ!連れてゆけ」
ドルテックの命令が甲板に響いた。
グリンは背中に銃を突きつけられ、前後を海賊に挟まれた恰好で、船内へのハッチへ歩かされた。小突かれるように階段を下りながら、グリンは最後にもう一度、ジェーンレーンの方を振り返らずにはいられなかった。
海賊船はそのまま西に進路をとった。
やがて、大小のいくつもの島々が姿を見せ、美しい緑の宝石のように船の両側を取り囲む。海の色が鮮やかなエメラルドグリーンに変わる頃、その先に目的の島が見えた。
ここは喫水の深い大型船ではまず通れない。一見美しいエメラルドの色をした海は、船乗りたちにとっては危険地帯を示す恐ろしい海域である。一歩間違えれば、突き出した鋭いサンゴに船底が引っ掛かり座礁してしまうのだ。さらに、この辺りは潮流も早く、ボートや素潜りで近づくのも危険であるから、まず大抵の船乗りならその先にある小さな島になど近づこうとも思わぬだろう。
「そこが狙い目なのよ」
ドルテックは自慢げに言った。
「ここはキャスタナル諸島の中でも、特に多くの島が複雑に入り組んだ場所だ。しかも城塞のようなサンゴ礁が取り囲んだあの島は、俺たちにとっては絶好のアジトになるわけさ。腕のいい操舵手がいなけりゃ、島に近づくことなどできやしねえからな」
「つまり、ここは俺たちの天国よ」
にやりと笑って、海賊は横にいるジェーンレーンの肩に手をおいた。後ろ手に縛られたままの彼女は、それを振り払うこともできず、無言のまま、ただ前方に近づく島を見つめていた。
「野郎ども!」
甲板の男たちに向けて、ドルテックは威勢よく叫んだ。
「今日は祝杯だ。島に着いたら好きなだけ飲んで食って騒げ!そして女を抱け。こうして赤毛のジェーンさんが、俺の元にやってきた記念すべき日なんだからな」
海賊たちは拳を突き上げ、一斉に野卑な歓声を上げた。
キャッスル・オブ・リベンジ号は、サンゴ礁の中をするすると抜けて、三日月のような形をした島の入り江に辿り着いた。周囲には数隻の小型船が停泊している。ここが海賊の島の港なのだろう。
小さな島の丘の上に、石作りの建物が見えた。あれが海賊たちの「家」なのだろう。その左手の切り立った崖の方には、物見の塔のような砦もあった。
錨を下ろすと、迎えに出てきていた島の海賊たちが、どやどやと船に乗り込んできた。甲板上はにわかに慌ただしくなり、はドルテックの指示のもと、積み荷が陸に下ろされてゆく。
船倉に捕らわれていたグリンも、後ろ手に縛られたまま船から下ろされた。少しの水は与えられていたので、ひどい脱水状態からは回復してはいたが、まだ足元はふらついた。
島はごつごつとした岩場が多く、ひどく殺風景な印象だった。丘の上にある建物も、一見して目立たぬ地味なもので、まさかここが悪名高い海賊団の本拠地であるとは、誰も想像できないだろう。
積み荷が全て下ろされると、海賊たちが長い行列となって、荷物をアジトに運んでゆく。数えきれないほどの樽や木箱が次々に運ばれ、さらには、どこかで捕らえられたのか、何人かの若い女性が悲鳴を上げながら引っ張られていった。
岩場に囲まれたドルテック海賊団のアジトは、石造りの要塞のような建物だった。剥き出しの石を積んで建てられた母屋は二階建てで、丘の形に添って細長く横に広がっている。おそらく、海賊団の人数が増える度に棟を大きくしていったのだろう。
アジトの周りには、戦闘時のための城壁があり、数人の見張りが行き来している。少し離れた海側の崖には、砦のような細長い建物があり、そこから幾つもの砲門が海に向けられている。接近してきた敵を迎え撃つ態勢も万全らしい。長年かけて造り上げてきたこのアジトは、まるで小さな王国のようでさえあった。
海賊たちの行列が城壁をくぐり、入り口にやってくると、ここにも多くの男たちが待ち構えていた。いったん降ろされた荷物がここで種類ごとに分けられ、手際よく建物の中に運ばれてゆく。
海賊に小突かれながら、グリンもアジトの中に入っていった。
建物の内部はひんやりとしていた。それに、外から見るよりも意外に広く、石造りの壁と天井が回廊となって遠くまで続いている。
荷物を運ぶ海賊たちが忙しく行き来する中を、ジェーンレーンを伴ったドルテックが入ってきた。グリンはそちらに近づこうとしたが、後ろから海賊に縄をつかまれた。
「ジェーンレーン……」
彼女はグリンに気づきもしないのか、石のように固まったままだった。その手の縄は解かれ、もはや逃げ出すこともなかろうというふうに満足げな様子のドルテックの横で、黙って立っていた。
「ワインと食料はちゃんと古いものを前に出しておけよ。この前肉を腐らせた馬鹿は鞭打ちで一週間寝込んだからな。お宝は、宝石と金銀、武器と服は別々の部屋だからな。間違えるな」
海賊たちはドルテックの指示のもと、木箱を持ち、樽転がしながら、次々に回廊の奥へ消えていった。
「さてと、」
荷物を運ぶ男たちの行列が一段落すると、ドルテックはグリンを振り返った。
「最後に、おめえは地下牢だ」
無慈悲にそう言い放つと、海賊はこれ見よがしにジェーンレーンの肩に手を掛けた。彼女は抵抗しなかった。
「ジェーンレーンは、俺のものだ」
にっと黄色い歯を見せる海賊の顔を、グリンはただ力なく睨むことしかできなかった。
「連れていけ」
「ジェーンレーン……」
屈強そうな二人の男に引きずられながら、グリンは何度も振り返った。だが彼女は、最後までこちらをちらりとも見なかった。
地下牢はじめじめとした、とても嫌なところだった。
昼間でもじっとりとして薄暗く、苔の生えた石壁には不気味な虫がうごめいている。いくつかの牢屋には、ずっと昔に死んだ囚人とおぼしき白骨が、衣服もそのままに捨ておかれていたりした。
「おら、今日からここがお前の家だ」
グリンは牢の中に突き飛ばされた。
背後で格子が閉められ、鍵がかけられた。男たちがげらげらと笑いながら去ってゆく。
グリンは狭い牢内を見回した。
壁際には格子のはまった小さな窓があるだけで、とても手が届きそうもない。地面は湿った石か固い土のようで、冷たく、しかも嫌な匂いがした。
「くそっ」
グリンは壁を叩いた。
ジェーンレーンのことが心配だった。船の上では、おそらく彼女は自分を気遣って、ドルテックの言いなりになったのだ。グリンはそのことにひどく心を痛めていた。
(俺のせいで……ジェーンレーンが)
とにかく早くここを出て彼女を助けるのだ。頭の中にはそれだけしかなかった。
グリンは弱った体で、なんとか壁をよじ登ろうとしたり、壁石をあちこち叩いてみたりした。それから格子が外れないかと調べ、隣の牢に誰か人がいないかと、壁越しに呼びかけたりもした。
そうしている間にも、髭面の海賊がジェーンレーンに襲いかかっている、そんな考えたくもない想像が頭をよぎる。
(そんなこと……させるか。彼女は俺が守るんだ)
グリンは己を奮い立たせると、脱出するためのあらゆる試みについて必死に考え続けた。
しだいに窓から差し込んでいた光が失せ、牢内はいっそう暗さを増していった。もう夕刻に近いのだろう。地下牢はしんと静まり返り、ぽたぽたというどこかで水が落ちる音だけが響いていた。
壁に背中を付けたグリンは、ぐったりと疲れきっていた。
試してみて分かったのは、床は土のようだがすぐ下が岩盤になっているらしく、地面を掘って逃げることはできないということ。となると、あとは窓から逃げるか、何とか格子を開けるしかないのだが、格子の方は頑丈で鍵がなくては出られそうもなかった。
壁の窓にも格子がはまっているが、それは古びていてなんとか外せないこともなさそうに見える。ただ、高いので手は届かない。この湿った壁を素手でよじ登ることも難しそうだ。何度か試してみたが、手が滑ってすぐに落ちてしまった。
(くそ……なにか、なにか方法はないか)
無用に体力を浪費することを恐れて、グリンは休みながら考えることにした。
しばらくして、牢の外に足音が聞こえてきた。
グリンははっとなって身構えたが、現れたのは食事を運びにきた見張りの男だった。男は格子の小さな窓を開け、銅の皿に乗ったスープとパンを牢の中に入れると、無言で行ってしまった。
(食事か……こんなときに)
少し迷ってからグリンはそれを食べた。腹が減っていたので、固パンに塩漬け肉のスープという食事でも、ひどく美味かった。この銅の皿が何かに使えないかと考えたが、何にもなりそうになかった。男が食事を入れた小さな格子窓も確かめたが、到底体が抜けられる大きさではない。グリンは諦めて、また壁際に腰を下ろした。
(ジェーンレーン……)
そうしていると、考えてしまうのは、やはり彼女のことだった。
無事でいるのか。なにか酷いことをされてはいないか。
あのドルテックの下品な顔と彼女を見るいやらしい目つきが、グリンをいらいらさせた。
(もしも、彼女に何かしたら絶対許さない。しかも奴は……タンタルス号の仲間の仇だ!)
船倉でなぶり殺しにされた水夫たち、甲板で戦い、殺されていった仲間のことを考えるほどに、また心の中にふつふつと怒りが沸き起こってくる。樽の中で聞いた悲鳴と海賊たちの笑い声を、自分は一生忘れないに違いない。
そういえば当のドルテックの方は、タンタルス号で会ったはずの自分のことを、まったく覚えていない様子だった。確かに、この今の自分……顔は日に焼け髪も髭も伸びて、ボロボロの服をまとったこの姿では、分かろうはずもない。
(よもや、あのとき、船倉に隠れ、船から脱出した一人の騎士が、今ここにこうしている俺だとは、思うまいな)
激しい怒りと、復讐心とがグリンの中でうずまいた。それが脱出のための折れない心の支えとなる。グリンは、己に言い聞かせた。
(見ていろ……俺はきっと)
暗い牢内で壁にもたれ、どのくらいたった頃だろうか。
いつのまにか、グリンはうとうととしていた。
このしばらく、焼き討ち船からの脱出にボートでの漂流、そしてドルテックの船との遭遇と、緊張の連続のせいで、まともに休めたことが無かったのだ。たとえ牢屋とはいえ、襲いかかる荒波や敵の襲撃などに気をつかわずに済むというのは、それだけでもありがたかった。
眠りかけていたグリンは、かすかな足音を聞いて目を開けた。
今度の足音は、明らかに海賊のものとは違うようだ。音を立てぬよう慎重な、それでいて早足のような……
その足音はしだいに近づき、牢の前でぴたりと止まった。暗がりを覗き込むようにしながら、グリンはゆっくりと立ち上った。
「誰だ?」
グリンが格子に近づくと、ふわりとした白い布が見えた。
「私だ、グリン」
「ジェーンレーンか?」
「しっ。大きな声を出すなよ。誰かに気づかれたら終わりだ」
「ああ、よかった……無事だったか」
グリンは格子に顔を付けて、そこにいる彼女を確かめた。
「ジェーンレーン……その姿は」
「ああこれ……」
彼女は苦笑した。その身には、ふわりと可愛らしい白のドレスをまとっていた。
「無理やり着せられたんだ。女の子みたいなドレスを。まったく馬鹿馬鹿しいったら……変だろう?」
グリンは目を白黒させつつも、思わずその姿に見とれてしまった。
「い、いや……。それで、奴らは……ドルテックは?」
「ああ。今は酒をたらふく飲んで居眠りしている。私が奴を酔わせるために飲ませたんだ。お前が心配で、見つからぬよう抜け出して来てみたが……ひどい所だなここは」
辺りを見回しながら、彼女は言った。
「まあ、牢屋だからな」
「その……すまなかったな」
「なんのことだ?」
「……さっきは、なるべく私がお前に無関心でいるフリをした方が、嫉妬深いドルテックのことだ、たぶんお前の扱いが少しはマシになるかと踏んだんだが……あまり役に立たなかったようだな」
粗末な食事が乗せてあった汚い銅の皿が転がっているのを見て、ジェーンレーンは眉をしかめた。
「いいんだ。俺のことは気にするな。船の上でだって……俺のせいで君は、奴のいいなりに」
グリンはぎゅっと格子を握りしめ、彼女を見た。
「……」
少しのあいだ、二人は格子ごしに見つめ合った。それからジェーンレーンは、ふっと笑って言った。
「私の心配より、自分のことを考えろよ。ずっと飲まず食わずで漂流していたんだからな。さあ、もうあまり時間がない。奴が起きるまでにまた戻らないと。とりあえず、今はこれくらいしか持ってこれなかったが」
彼女は食事用のナイフを取り出すと、格子の間からグリンに手渡した。
「なんとかお前をここから出す方法を考えてみる。今日はもう無理だが、明日の食事どきにはなんとかしてみるつもりだ。海賊の下っぱの中に、たらし込めそうな奴がいたんでな。うまく抜け出せたら……あとは一人で逃げるんだ」
「なんだって?」
「奴の狙いは私だけだ。お前がいなくなっても、たぶん追手を放つことはあるまい」
「だからって、君を置いて行けるわけないだろう」
「私は大丈夫だ。奴は……ドルテックは、少なくとも私を殺すことはしない。ま……あんなのに抱かれることを考えると、今から身の毛がよだつけどね。私にだって好みってものがあるのだからさ」
にやっと笑って、彼女は言った。
「お前は……けっこう私の好みだったよ」
「ジェーンレーン……」
「巻き込んでしまって、すまなかった」
照れたように目をそらし、彼女はひとつ髪をかきあげた。
「ジェーンレーン」
その名を呼んだグリンの声に、求めたものを聞いたのだろう。彼女は格子をつかむ相手の手にそっと触れ、そこに軽く唇をつけた。
「グリン……、あいつの目的はこの私だ。たぶんこのままここにいたら、奴はお前のことなどいずれ忘れてしまうだろう。そうしたら閉じ込められたまま、ろくな食事ももらえず、やがてお前は死んでしまう」
「……」
「だから、逃げろ。私がなんとかする。いいな」
「待て、ジェーンレーン……俺は」
格子の間から手を伸ばそうとするグリンから、彼女はすっと体を離した。
「もう……時間がない。戻らなくては」
薄く微笑んだ彼女の顔は、まるで最後の別れをする恋人を見るときのように、寂しさを押し隠すようにも見えた。
「お前の無事を祈っている」
そう言い残し彼女は立ち去った。
牢の中のグリンは、大声で彼女の名を呼びたい衝動を堪えながら、鉄の格子をずっと握りしめていた。
牢での一日はひどく長く感じられた。
朝がくると、牢内にも窓から差し込む光が届いて、囚人に一日の始まりを告げる。早いうちから目を覚ましたグリンは、狭い牢内を歩き回りながら、これからのことを考え続けた。
ときおり座り込んで腕を組み、目を閉じて休んでは、また不安になってぱっと立ち上がる。それの繰り返しだった。
こうしている間にも、ジェーンレーンがどうしているのかが気になって仕方がなかった。薄汚いドルテックの手が彼女に触れることを考えただけで、グリンは苦痛に顔を歪めた。そして、己の妄想を断ち切るように壁を殴りつけるのだった。
そうして、また半日が過ぎ、牢内が暗闇に包まれはじめた。
昨日と同じ食事係の男が現れ、銅製の皿に入ったスープとパンを、小さな窓を開けて牢内に置いてゆくと、グリンはそれに飛びついた。
確かジェーンレーンは、食事のときになんとかすると言っていたはずだ。なので、てっきり食事係の男が鍵をくれるものかとも思っていたのだが、そうではなかった。
ではどういうことなのだろう?
グリンは皿からパンを取り、スープを覗き込んだ。皿の中に何か入っているのかとスプーンですくってみるが、鍵かなにかが入っていることもなかった。
「ダメだったのか……」
グリンはため息をつくと座り込んだ。
ジェーンレーンが何かしくじってしまったのだろうか。それとも……頭の中に言い知れぬ不安がよぎりはじめる。
ともかく、まずは食事をしようと、グリンはなんとはなしにパンにかじりついた。そのとたん、ガチンと何かが歯に当たった。
「痛っ、……なんだ?」
どうやらパンの中に何かが埋め込まれている。鍵……ではないようだ。もっと大きいもの。
グリンはパンを二つに割って、中にあるもの取り出した。
「これは……」
それは鉤のような金具だった。船上でもロープなどを引っかけたりするときによく使われる、拳ほどの鉤である。
これはどういう意味なのだろう。しばらく考えたすえ、グリンはふと壁を見上げた。格子のはまった小さな窓は、グリンの身長の二倍以上の高さにある。
「あ、そうか!」
何かを思いつくと、彼は牢内を見回した。
ここに入れられるときに腕から解かれた縄が、そこに落ちていた。それを拾うと、グリンは迷わず鉤に縛りつけた。
縄の付いた鉤が出来上がった。グリンは壁から少し離れて狙いを定め、窓目掛けて鉤を投げた。
最初はなかなかうまくかからなかったが、十回、二十回と根気よく投げ続けるうちに、ついに鉤が窓の格子に引っかかった。
「よし」
牢の外に誰もやって来そうにないことを確かめると、グリンは窓の格子から垂れ下がった縄をつかんだ。だが、それを手繰って壁に足を付けて踏ん張ったとたん、バキンと音がして鉤が外れた。
背中から床に落ち、グリンは顔をしかめた。
「痛たた……」
見ると、窓にはまっていた格子の一本が抜け落ちていた。鉤をかけて引いた際に外れたのだ。
「なるほど……これはいいぞ」
グリンは鉤を拾うと、再び窓に向かって投げはじめた。何度かやっているうちにこつをつかんできた。鉤を引っかけた格子が、一本、二本と窓から外れたのだ。
「よし、こんなものでいいだろう」
こうして、格子の抜けた窓に、人一人が抜けられそうな隙間がぽっかりと開いた。あとはもう一度よじ登って、あそこから外に出ればいい。
そのとき、牢の外に足音が聞こえた。グリンは持っていた鉤を後ろに隠し、何気ない格好で壁にもたれた。
「なんか音がしたから見てこいっつってもな、なにも変わったこたねえよな……」
ぶつぶつと呟きながら歩いてきたのは、見回りの海賊だった。ここで見つかっては元も子もない。グリンは息をひそめ、緊張しながら牢の中で眠ったふりをした。
「ったく、お頭は人使いが荒いんだからよ」
海賊はグリンのいる牢の前で立ち止まり、こちらを覗きこんだ。格子の外れた窓が気づかれないか、グリンは気が気でなかった。
「うう、それにしても地下は寒いぜ。とっとと上に上がってまた酒を飲まねえと……」
独り言をつぶやきながら、海賊はそのまま去っていった。足音が完全に消えるまで、グリンは動かなかった。
(ふう……あぶないあぶない)
ほっと息をついたグリンは、夜が更けるまで脱出を待つことにした。海賊たちがいつまで起きているのかは知らないが、どちらにせよ深夜の方が外の見張りも手薄になるはずだ。本当は一刻も早く、この汚い牢から抜け出したかったのだが、はやる気持ちを抑えてグリンは待った。
やがて夜が更けた。静まり返った暗がりのなかで、グリンは立ち上がった。ここにいる間にすっかり暗闇にも目が慣れていた。
鉤を手に慎重に狙いをつけると、窓をめがけて投げた。
格子の一本に鉤が引っかかると、慎重に縄を引いてみる。今度は簡単に抜けそうもない。しっかりと体重を支えられそうな手応えがあった。
「よし。頼むぞ……」
縄を手繰り、壁に足をかける。食事をとったおかげて、体力もだいぶ戻っているようだった。両腕にぎゅっと力を込め、壁にかけた足を踏ん張り、グリンは壁を上っていった。
「もう……少しだ……」
ついに窓に手が届いた。残った力を振り絞って壁をはい上がると、グリンは格子の間をくぐり抜けた。
外に出た。
とたんに、清涼な空気がふわりと彼を包んだ。
「やった……」
グリンは大きく息を吸い込むと、あたりの気配を窺った。どうやら近くに人の気配はない。辺りは暗く、静まり返っている。
ゆっくりと立ち上がって壁沿いに歩き出す。
もう夜もだいぶ更けた頃だろうが、深夜番の見回りもいるに違いない。グリンは足音を立てぬよう、慎重に歩いていった。
このまま一人で逃げることも出来ただろうが、グリンの頭には始めからそんな考えはなかった。
(ジェーンレーンを……彼女を探さなくては!)
その崇高な目的が、グリンを勇敢にさせた。ときおり建物の窓からこぼれる明かりを頼りに、彼は暗がりを進んでいった。
建物にそってしばらくゆくと、壁から突き出た古びた石柱が目にとまった。これを上って二階に上がれそうだ。マスト上りの要領でするすると柱を上り、二階の窓枠部分に立つと、グリンは壁にへばつりくようにして移動した。
(あそこから入れそうだ)
少し先に、大きめの窓があるのを見つけた。
その窓に近づいていって中を覗くと、部屋にはランプの明かりが灯っていたが、誰もいないようだった。窓には格子も付いていない。こんなところから入ってくる者がいようとは、誰も思わないのだろう。グリンは窓をくぐり、さっと部屋の中にすべり降りた。
その部屋はさほど広くはなかったが、なんともいえず豪奢な雰囲気だった。
まず目についたのは、金色の柱と天蓋のついた大きなベッドだった。壁には高価そうな絵画がいくつも飾られ、床には東方風の刺しゅうが施された絨毯が敷きつめられている。それに椅子もテーブルも何もかもが、まるで王侯貴族の寝室のように立派なものだった。もちろん、これらのすべての品々が強奪品であることには疑いの余地はなかったが。
(もしかし、ここはドルテックの……)
グリンがそう考えたとき、扉の外から声が聞こえた。
耳をそばだてると、確かに話し声が聞こえてくる。それも男女の言い争うような声が。
(こっちに来る……)
グリンは急いで辺りを見回し、窓際にあるカーテンの影に身を隠した。扉が開かれ、誰かが部屋に入ってきた。
グリンは息をひそめて気配をうかがった。
「やめろ。触るな」
その声が聞こえたとたん、グリンは心の中で叫んでいた。
(ジェーンレーン!)
すぐにも出ていきたいのを堪えて、拳を握りしめる。
「へへっ、ここまで来て、そりゃねえだろう。なあ、ジェーンレーン。昨日は飲みすぎたせいか、ついつい寝ちまったが、今日こそはいただかせてもらうぜ。むろん、その後はおめえを俺の女として、このドルテック海賊団の副団長にしてやるつもりだ。どうよ?こんないい話はあるまい」
確かめるまでもなく、それはドルテックの声だった。グリンはカーテンの隙間から室内を窺った。
青いドレス姿のジェーンレーンが見えた。海賊は酒に酔っているのか赤い顔をして、いやらしい笑いを浮かべながら彼女の肩に手をかけている。
「俺はずっとお前が欲しかったんだよ。ジェーンレーン。おめえが十五歳になったくらいから……ずっとな。あの頃は、親父もいたし、簡単には手は出せなかったがな。だが、親父が……リングローズがくたばって、俺は出世した。こうして今、やっとお前を俺のものにすることができると思うと……、嬉しいやら、たまらんやら……くっくっ」
海賊は上着を脱ぎ捨てると、乱暴にジェーンレーンを引き寄せた。
「美しいぞ。ジェーンレーン。船でのおめえもいいが、そうやって女らしいドレスを着ていると、本当にどっかの姫をかっさらって来たみたいな気になる」
彼女は顔をそむけたが、ぐいと顎をつかまれた。
「いいんだぞ。そうやって嫌がっても。どうせ俺にやられちまえば、あとはひいひいとよがりだすんだからな。どんな女だってそうなるのさ。くくく」
「この……下司が」
「その下司に、これからお前は抱かれるんだよ。逆らえねえよなあ。なにしろ、お前の気に入りのあの小僧は、俺の牢屋にいるんだからな。ああ、まだ生かしてやるとも。おめえが逆らわないかぎりは、あの牢屋の中で飼っていてやるさ。いつまでもな。さあ、脱げ」
「……」
「どうした?脱がないのなら。俺が脱がせてやろうか?ええ?」
「……やめろ」
肩をつかまれ、引き寄せられながら、ジェーンレーンは抵抗した。だが、さすがに女の腕力ではかなわない。両腕を押さえつけられたジェーンレーンは、ずるずるとベッドの方に引きずられていった。
「おとなしくしてろ。すぐに良くしてやるよ」
海賊の顔に喜悦の色が浮かんだ。
「……」
カーテンの影から、グリンはじっと機会をうかがっていた。
目の前でドルテックの手が彼女の体に触れる度に、たとえようもない怒りがこみ上げた。右手に取り出したナイフを何度となく握りしめて、彼はそのチャンスを待った。
ジェーンレーンをベッドに投げ出したドルテックが、その上に覆いかぶさろうと、こちらに背中を向けた。
(今だ!)
その瞬間、グリンはカーテンから飛び出すと、ナイフを投げた。
とたんに、「ぎゃっ」と声が上がった。
(サンキュー。ルー・パイ)
心の中でナイフ投げの師匠に礼を言う。
グリンの投げたナイフは、見事にドルテックの背中に突き刺さっていた。
「くそっ!なんだこりゃ。痛え!」
叫び声を上げる海賊にかまわず、グリンはジェーンレーンのもとに駆け寄った。
「無事か、ジェーンレーン」
「グリン。お前、逃げずに……」
「当たり前だ」
彼女の手を取り、グリンは大きくうなずいた。
「ああ……グリン」
「くそっ、てめえら……」
床にうずくまっていたドルテックがよろよろと立ち上がった。
すかさずジェーンレーンは、テーブルにあった置物の絵皿を、その頭に思い切り叩きつけた。
「がっ……」
粉々に砕けた高価な皿とともに、ドルテックが床に倒れた。
「ふう……これで少し時間が稼げるだろう」
海賊を見下ろしてそう言うと、彼女はグリンに向き直った。
「ジェーンレーン……」」
「来てくれて、嬉しい」
にっこりと微笑んで囁くと、彼女はグリンの頬に唇を押し当てた。
「この格好、ドレスの姫君に見えるか?」
「ああ。では、俺はその姫を助ける騎士かな」
顔を見合せ、二人はくすりと笑いあった。
「よし、行こう」
グリンが手を取ると、ジェーンレーンもその手を握り返してきた。
二人は部屋の窓から外に出た。グリンが柱を伝って先に飛び下り、続いてジェーンレーンも飛び下りた。下からグリンが彼女を支えたが、二人はもつれて地面に腰を付いた。
「大丈夫か?」
「ああ。おかげさまでな」
「走れるか?」
「このドレスが邪魔だが……これでなんとかなるだろう」
ジェーンレーンはドレスの裾をたくし上げ、足もあらわな姿になると、グリンを見てはにかんだ。
「お転婆姫で悪かったな」
「君にはお似合いだ。よし急ごう」
二人は手を取って、暗がりの中を走り出した。
見張りの海賊たちにが気づかれる前に、できるだけアジトから離れておかなくてはならない。
「とにかく港まで下りて、船を奪って逃げるのがいいだろう」
しかし、そのグリンの考えは簡単に頓挫した。というのも、二人が脱出したのは丘の反対側だったので、港にゆくためにはアジトををぐるりと回ってゆかなくてはならない。それにきっとドルテックは、港への道をすぐに封鎖するだろう。
「仕方がない。ともかくここから離れよう。こちら側からも海に下りられる道があるかも知れない」
ジェーンレーンの言葉にグリンもうなずいた。
二人はそのまま島の南側を目指した。辺りにはごつごつとした岩場で、木々はおろか身を隠せそうな茂みもなかった。月明かりを頼りに、二人は岩地に転ばぬように気をつけながら走り続けた。
背後に見えていたアジトの明かりが遠くなると、二人は少し歩を緩めた。
「……しかし、よくもまあ、あの鉤だけで牢を抜けられたな」
グリンの手をしっかりと握りながら、ジェーンレーンが感心して言った。走り続けて少し息を切らせた彼女は、その頬をかすかに紅潮させていた。
「本当は、牢の鍵を渡したかったんだが、牢番はさすがにドルテックの直接息のかかったやつでな。なんとか食事係の一人をたらしこんで、あの鉤をパンに入れるくらいがやっとだった。お前なら……あれだけで脱出できるかもしれないと思ったから。それにさっきのナイフの腕といい、感心したぞ」
「ああ。これも船でルー・パイにさんざんナイフ投げのコツを教わったおかげだな。それに、ブルー・マスター号でのマスト登りやロープ引きでも、けっこう鍛えられたからな」
照れくさそうに答えながら、グリンはドレス姿の女海賊をちらりと見た。
「また……助けられたな」
そう囁き、彼女はぎゅっと手を握り返してきた。
「ポート・イリヤでも、あの焼き討ち船の上でも、それに流されるボートの上でも、お前は……私のために戦い、私のために、水も飲もうとしなかった……」
月明かりのもと、ジェーンレーンの横顔が美しく浮かび上がる。
「お前は……お前は、ただの商人などではない。それに……海賊でもない。その心には誇りを持っている。強くて、そして紳士だ」
「……」
「お前は……まるで」
グリンを見上げる彼女の目が、そっと閉じられた。
「ジェーンレーン……」
彼女を抱き寄せ、グリンはその肩にそっと手をおいた。
互いを求める二人の唇が、ゆっくりと合わさろうとした。
そのとき、銃声が上がった。
はっとした二人が振り返ると、後ろの岩影から追手の海賊たちが現れた。銃を手にしたドルテックが先頭にいる。
「いやがったな。待ちやがれ!逃がさねえぞ、てめえら」
怒声とともに、立て続けに何発かの銃声が上がった。
「ジェーンレーン!」
二人はまた手を取り合い、丘を登る岩場を走り出した。
この暗がりでは簡単には銃弾は当たるまいと、グリンは考えていたが……いつのまにか、先も見えないほどの漆黒の闇は、少しずつその明るさを増し始めていた。
東の空が白みはじめている。もう夜明けが近いのだ。
グリンは焦りを覚えた。このまま朝になれば、闇に隠れることもできず、確実に追い詰められてしまうだろう。それに、自分自身も、ずっと走りつづけるだけの体力はまだ戻っていない。
(このままでは……)
迫り来る絶望感を追いやりながら、それでも走るしかなかった。
海賊たちに追い立てられるように丘を登りきると、いきなり目の前に海が開けた。
「く……」
二人は立ち止まった。
そこは鋭く切り立った崖だった。
海からの風が冷たく頬を撫でつけ、岩に波がぶつかる恐ろしい音とともに、激しいしぶき立ち上る。
「グリン……」
ジェーンレーンがその顔を曇らせた。
「大丈夫だ」
やはり、無理をしてでも港の方に降りるべきだったのか。唇をかみしめたグリンだったが、それでもまだ、希望を失わぬ顔でうなずきかけた。背後からは海賊たちが追いついてくる。ここで立ち止まってはいられない。二人は崖に沿うように走り出した。
「グリン!」
ジェーンレーンが前方を指さした。
こちらの行く手をさえぎるように、ばらばらと海賊たちが現れた。奴らは二手に分かれて、こちらを追い込む形で回り込んでいたのだ。
「くそ……」
ついに二人は足を止めた。切り立った断崖と銃を手にした海賊たちに囲まれて、もはやどこにも逃げ場はなかった。
こちらを追い詰めたとみると、海賊たちはいったん距離をとって立ち止まった。
「ジェーンレーン!」
ドルテックの猛々しい声が上がった。
「もう逃げられないぜ。それにそっちのぼうやもな。油断した俺が馬鹿だったが、もう容赦しねえ。二人ともぶっ殺す!」
マスケット銃を高々とかざし、海賊は凶暴に怒鳴り散らした。
「さあ、どうする?ジェーンレーン。もし俺の所に戻る気があるなら、お前だけは許してやってもいい。今すぐに決めろ!」
銃を構えた海賊たちは、こちらを崖に追い詰めるように一列に並び、じりじりとと近づいてくる。
「助かりたくはないのか、ジェーンレーン。そのガキと一緒に死ぬつもりなのか?」
ドルテックは威嚇するように銃を撃った。弾は二人の近くをかすめた。
「次は当てるぜ。おめえの大事なぼうやにもな!」
二人は断崖を背に後ずさった。
「すまんな」
ジェーンレーンは囁いた。その手は、グリンの手を離さなかった。
「私は……行きたくない」
「ああ」
にこりと笑って、グリンもつないだ手を強く握り返す。
「俺もそのほうがいい」
「よかった」
ジェーンレーンは嬉しそうに微笑み、恋人の胸に飛び込んだ。
それを見ていたドルテックは、かんかんになって叫んだ。
「てめえらっ。もう許さねえ。こうなったら、二人まとめて撃ち殺してやる!」
海賊たちが一斉に銃を構えた。
「よーし、撃……」
ドルテックが手を振り降ろそうとした、そのときだった。
何の前触れもなく、ドーン、という轟音が上がった。
続いて、ずしーんという重たい爆発音とともに、辺りが揺れた。
「な、なんだ?」
ドルテックは仰天して辺りを見回した。
さらに続けざまに、ドーン、ドドーンと爆音が響いた。
「これは……」
グリンとジェーンレーンは顔を見合わせた。
「大砲の音だ!」
まるで島全体を揺るがすような、ずしーん、ずしーん、という着弾の轟音が、間隔を置いて鳴りはじめ……
それはしだいに激しさを増していった!
「お、お頭……アジトが!」
「なんだと!」
部下の報告に振り返ると、アジトの方角から、もうもうと土煙が上がるのが見えた。
「こ、攻撃です!」
「いったい何者だ?」
その間にも、次々に撃ち込まれてゆく砲弾と、爆発の轟音があたりを揺るがした。そのうちの一発が近くの岩を粉々に吹き飛ばすと、海賊たちはその場で右往左往しはじめ、叫びだしたり、逃げまどったりと、パニックに陥った。
夜が、明けはじめていた。
グリンは崖の上から海上を振り返った。
その横で、ジェーンレーンもまた、息を呑んだようにそれを見つめていた。
水平線に、最初の陽光がまぶしくきらめき……
そこに現れた船団を。
■次ページへ