ブルーランド・マスター
7/11ページ
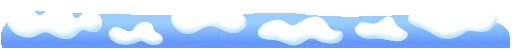
■7■再び船へ
ブルー・マスター号の出航準備は、夜明け前から行われていた。
当初は今日いっぱいは滞在する予定であったものの、ジェーンレーンがすぐにも出帆するつもりであることを知った操舵長は、船員たちを集めてそれを伝えた。こうした予定変更はさして珍しいことではなかったので、船に乗り込んだ船員たちには昨夜の酒を残す様子もなく、不平を言う者もない。日が顔を出す前の薄暗い港に、忙しそうな男たちのかけ声が響き、食料や水、その他の物資が、次々と船に積み込まれてゆく。
当のジェーンレーンが船に姿を見せたのは、とうに日が昇りきった、朝の六点鐘を過ぎたころだった。
「すまん。遅くなった」
束ねた赤髪を肩に垂らし、腰には剣を、ベルトには小銃を下げたいつもの姿で、彼女は甲板に上がってきた。久しぶりの陸の感触を楽しんだせいか、その顔には晴れ渡った空のような、すっきりとした微笑が浮かんでいる。
「ご苦労だな。どうだ?」
傍に来たオギナに尋ねると、何事もよくわきまえている操舵長は、よけいな事はいっさい言わず、てきぱきと必要な事項を報告した。
「帆の修理は完了しました。食料、水の積み込みももうすぐ終わります。前の船員のうち七名ほどが船を降りましたが、新たに十一名が乗船を希望しております」
「うん。では後で私がチェックする。武器は届いたか?」
「はい。ただし、旋回砲は半数が中古品ですが。マスケット銃は上物です。火薬、弾丸共に問題なしです」
届けられた銃の一丁を試しに構えて、彼女は満足げにうなずいた。
「ふん。悪くない。さすがにログウッド。渋ったフリをしても、ちゃんとものは集めたようだな」
「では、予定通り、半刻後に出帆ということで」
「ああ……」
銃を構えたまま、彼女は答えた。
「それでは」
「あいつは……戻ったか?」
立ち去ろうとするオギナの背中へ、彼女は何気ない口調で尋ねた。
「あいつ?……グリンのことで?」
「そうだ」
「いいえ、まだ」
「そうか」
「少し、待ちますか?」
「無用だ。予定通り出帆する。いいな」
そう言って銃を放って返すと、彼女は甲板をすたすたと歩いていった。舳先に立ち、湾内を見渡すジェーンレーンの横顔を、オギナは少しの間見守っていた。
船上に出帆を告げる音が鳴り渡った。
「よし、錨を上げろ」
船首にある巻き上げ機を、男たちが慣れた手つきで回し、錨を引き上げてゆく。つづいて甲板に並んだ船員たちの手で綱が引かれ、メンスルーが上げられる。
「ヘッドスルー、トップスルー、用意はいいか?」
「ようそろ」
掛け声とともに海賊たちが一斉に綱を引くと、ブルー・マスター号のマストに大きく帆が広がってゆく。
「進路、南西、微西四分の一」
「南西、微西四分の一、ようそろ」
舵をとるオギナが、横に立つジェーンレーンの指示を受け、ハンドルを回す。船は帆に風を受けて、ゆるやかに動きだした。
「あいつ……戻ってこなかったね」
甲板から港を見やりルー・パイが言った。そばにいたドリスもつまらなさそうに唇を尖らせた。
「せっかく、マスト登りのコツを教えてやったのに。なにも言わずに出ていくなんて」
「あーあ、こんなことなら、アイツを強引に押し倒して、唇くらいもらっとくんだったわ」
そう言って、ルー・パイは後部甲板を振り返った。
「あいつ、てっきりお頭に気があると思っていたのに……あたしの気のせいだったのかな。こんなにあっさり行っちまうなんて」
「よう。ルー・パイ。また男に逃げられたのか?なんなら代わりに俺がなぐさめてやろうか」
「うるさいね。この馬鹿!毛むくじゃらで垢だらけのあんたなんて、御免だよ」
げらげらと笑いながら通りすぎる海賊に、彼女は怒鳴り返した。
船はポート・イリヤ湾をすべるように進んでゆく。風は順風、空は青々と晴れ渡っている。
湾の出口にさしかかったあたりだった。いつのまに登ったのか、マストの上の見張り台からドリスが手を振っていた。
「おおい!ボートだ。ボートが来るよ!」
「なんだって?」
ぐるぐると大きく腕を振りながら叫んでいるドリスを、甲板にいた海賊たちが見上げる。
「ほら、あっち。あっち!」
振り返って見ると、船の後方、港の方角から、確かに一艘の小さなボートがこちらに向かってくる。
「あれは……」
ルー・パイをはじめ、海賊たち全員が、そちらに目をこらした。
「グリンだ。グリンだよ!」
興奮したドリスの声が、見張り台から降ってきた。
「あいつだ。あいつ戻ってきたんだよ!」
「お頭!」
ルー・パイが、後部甲板に駆け寄って報告する。。
「グリンが帰還しました!」
「……」
ジェーンレーンは、黙ったまましばらく後方を見やっていたが、それからすっと手を挙げ、静かな口調で命じた。
「停船。帆をゆるめろ」
船の速度が落ちると、後方からのボートは徐々に近づき、そこに乗る人影が甲板からもはっきりと見えた。
「やっぱりグリンだ。あいつ……戻ってきやがった」
ルー・パイは、ボートに向かって手を振った。
「おおい!」
他の海賊たちも、近づいてくるボートに手を振る。
「おおい!おおい!」
「おおーい」
ボートの上からも、櫂を手にしたグリンが手を振るのが見えた。
「戻ってきた……あいつが」
ルー・パイは涙ぐんだ目で、徐々に近づくボートを見つめた。
船に乗り移ったグリンが甲板に降り立つと、待ち構えていた海賊たちが彼を取り囲んだ。
「なんだ、おめえ。戻ってきやがったか」
「どうしたのかと心配したぜ」
「乗り遅れるなんて、ドジな野郎だ」
「まったくだ」
意外なほどの歓迎ぶりで、海賊たちに荒っぽく肩や背中を叩かれて、グリンは咳き込んだ。
「グリンー!」
走り寄ってきたルー・パイが、グリンに飛びついた。
「なんだよ。あんた……心配させて。もう、このまま別れちまうのかと思ったよ」
「ああ、すまない。またしばらく世話になるよ」
グリンは照れたように言った。
「へへっ。またおいらとマスト登り競争しようぜ」
鼻をこすりながら、ドリスが嬉しそうに笑った。
グリンは甲板上を見回した。
彼の探す姿は後部甲板にあった。一段高くなった指令用の甲板に立つジェーンレーンは、そこから降りてくる様子はなく、ただまっすぐにこちら見ているだけだ。
「……」
馴染みの海賊たちとひと通り握手を交わすと、グリンはそちらに歩き出した。
後部甲板の下まで来ると、彼はそこにいた相手を見上げた。
「戻ってきたのか?」
「またこの船に乗せてくれますか?」
「ここは客船じゃない。ただの商人を乗せてやる場所はないが」
ジェーンレーンの声はひどくそっけなかった。だが、横にいるオギナは、何故かおかしそうな顔をしている。
「分かっています。それでは……」
相手から目をそらさずに彼は言った。
「海賊として、では?」
「……」
一瞬、彼女はぴくりと眉を寄せた。
集まってきた海賊たちからどよめきが起こる。
「……いいだろう」
彼女は、ふっと、やわらかな笑いを漏らした。
とたんに、「わっ」と歓声が上がった。
「グリンが仲間になった!」
「俺たちの仲間だ!」
海賊たちは声を上げ、誰からともなく手を叩きはじめた。
その喝采の中で、グリンは、たった今、自分の船長となったばかりの赤毛の女海賊をじっと見上げていた。とまどったような彼女の方が、先に目をそらすまで。
ブルー・マスター号は、晴れ渡った空の下、滑るように進んだ。
彼方にキャスタナル諸島の緑の島々と、どこまでも続くエメラルドの海を眺めながら。
流れゆく雲、黄昏の空、満天の星空、月の隠れた闇夜、そして暁のうす紫の空のもとを。船は進んだ。
グリンはもう完全に、海賊たちから「仲間」として受け入れられたようだった。
同じテーブルで食事をし、ハンモックで眠り、鐘の音で飛び起きては甲板に上がって見張りをし、マスト登りも、帆を張るためのロープ引きも同じようにこなした。陽気に酒を飲んで、歌ったり踊ったりもした。これまでは立ち入りが許されなかった船倉にも、操舵長の許しを得て足を踏み入れ、予備の大砲の点検をしたり、食料や水の管理なども手伝った。食堂ではグリンの忠告で料理人が味付けを変え、それが好評になると、喜んだ二人はさらなる新メニューの開発に取り組んだ。
毎朝起きると、決まってドリスかルー・パイがやってきて、彼をマスト登りかナイフ投げの練習に誘った。夕方になると、ローガンの「鳥撃ち」を見物しにマストに登り、夕食後は海賊たちと酒を飲み交わした。男たちは豪快な笑い声を上げ、野卑な言葉で女や冒険や海の話をしてくれた。やがて誰かが笛を吹きはじめ、ヴァイオリンが鳴り出すと、彼らはそれに合わせて踊りはじめるのだった。
もちろん、船では楽しいことばかりではなく、時に凪や嵐に出会うこともあった。
海上でまったく風がやんでしまう凪の時は、どうすることもできず、船員たちはただ時間をつぶすしかない。甲板や部屋でねそべったり、トランプを始めたりして、皆めいめいに退屈な時間を過ごした。海賊たちはそれに慣れている様子だったが、船がまったく進まないというのは、大変な恐怖を感じるものであることをグリンは知った。このままここに永遠に取り残され、食料が尽きるのを甲板の上で待っているしかないのかと、恐ろしい考えがふと浮かぶ。だがしばらくして、「風だ、風だぞう!」という声が上がると、誰もがとたんに目を輝かせ、「帆を張れ!帆を張れ」の叫びが甲板中を行き交いだす。一致団結した海賊たちの手で速やかに帆が張られ、それが風を受けて広がるのを見上げるとき、グリンはなんともいえない興奮を味わうのだった。
嵐のときはさらにひどかった。降りしきる雨と風とに、船は揺れに揺れ、まるでこの世の終わりのようだった。ざあざあと容赦のない雨が打ちつける甲板を、足を滑らせながら走り回り、たまった水を汲み上げては海に捨てるという作業が一晩中続いた。風にあおられ、ぎしぎしと船が軋む音が鳴り、大きな波が甲板の上にまで押し寄せた。濡れねずみになりながら、海賊たちはジェーンレーンの指揮のもと、必死にマストを支え、水をくみ出し続けた。ようやく嵐が過ぎ、雲の間から青空が見える頃には、誰もがへとへとになって、甲板上にぐったりと倒れ込んだ。
風が順風の時は、海賊船は天国のようだった。風向きが変わればその度に帆の角度を変えるために、マストのロープを引き続けなくてはならないのだが、その必要のない順風においては、船は快速船さながらに海を滑った。厳しい規則や騎士の品格を気にすることもなく、グリンは甲板に大の字になって空を見上げ、ときにマストに登って見張り台の上から沈みゆく夕日を鑑賞した。
黄金色の光を放ちながら水平線に消えてゆく巨大な円盤……それを眺めていると、なにも恐れるものはない、すべてはこれでいいのだというような、心地よい解放感が彼を包んだ。
だが、もちろん、ここは遊覧船などではなく海賊船であった。そうであるからには、生きるために海賊行為をしないわけにはいかない。マストに登った見張りが……それはたいていはドリスの仕事だったが……海の彼方に帆影を見つけると、ブルー・マスター号の甲板では戦闘の準備が始まる。
狙いをつけるのは、たいていは中型以下の商船か、ときに武装の薄そうな私掠船などだった。襲撃が決定すると、オギナによって細かな手順が定められ、海賊たちはそれぞれに銃を握り、大砲を並べてゆくのだ。
これこそ、最もグリンが恐れていたときだった。海賊船と知った上でこの船に乗り込んだものの、実際に海賊行為を手伝うということになると、さすがに騎士としての誇りと良心とがそれを阻んだ。相手船が私掠船や海賊船などであればまだ良かったが、一般の商船などであった場合は、罪悪感にさいなまれた。そんなときは、なるたけ略奪行為に関わらぬよう、大砲や銃から離れて、彼は船内に引きこもった。
ただし、ジェーンレーンのやり方はまったく見事なものだった。かつてガルタエナの湾内で見たように、必要最小限の威嚇や戦闘で相手の物資や食料を奪うと、無用の殺生はせず、彼女はすぐに船から引き上げさせた。それは、おそらく彼女が、父親であるリングローズから教わった方法を実践しているのであり、無駄な砲弾を使わず、人殺しはせずという、ある種の矜持にも基づいているようにグリンには思えた。
船から略奪した物資は、食料や酒であったり、ごくまれに高価な宝石や衣服、または武器やたばこ、ときには家畜などであったりした。それらは、船で消費されるものや、船員に分配される分を除いては町で売られた。
グリンが驚いたのは、キャスタナル諸島の島々には、意外に多くの町があるということだった。ポート・イリヤのあるエボイア島の他は、ほとんどが無人島であるとばかり思っていたのだが、無数に点在する島にはそれぞれに人が住んでおり、少し大きな島になるとちゃんと港もある立派な町が存在していた。
船は定期的に、補給や修理もかねて最寄りの島に寄り、そこで奪った品物を売ったりした。島の住人の多くは、海賊を相手にする商売人などで、このような掠奪物資を取引する密売のルートがあるらしい。ここで売られた品物が、さらに闇商人の手でもっと大きな港町で売られたり、または別のルートで大陸のどこかの国へ持ち込まれたりするのだという。
物資を売って儲けた金は、海賊団を維持するための大切な費用となる。船の修理費や、新たな大砲、銃器の購入、船員への給料、さらにはポート・イリヤへ払う入港費用にもなるのだ。組織的な大海賊とは違い、自分たちの食べる分は、すべて自分たちだけで稼がなくてはならない。黄金と金貨に埋もれて高笑いをするという、物語の中の海賊とは随分な違いである。
港町でつかのまの休息と、陸の感触を確かめると、男たちはまた船に乗り込み、すぐにまた次の航海が始まる。
こうして、海賊たちは、その日その日を生きながら、自由とともに与えられた「生きのびるための苦難」に、その身をやつしてゆくのだった。命を落とすか、あるいは陸に降りてまっとうな生活に戻るかという、いつかは訪れるであろうその選択を、少しでも引き延ばすために。
ブルー・マスター号は軽快に海原をゆく。
大型船では決して入り込めぬ、エメラルド色のサンゴ礁を近くに、ときに島々の間を縫うように走り抜け、また広大な自由の海へと。
陸地も島も見えない大海で、太陽を背に、風を受けて駆ける船の姿は、さながらこの「青い大地」の主のようだった。
そして十日が過ぎ、二十日が過ぎていった。
ある朝、顔を洗おうと、水おけを覗き込んだグリンが見たのは、日焼けした顔に髭をたくわえた、精悍な顔つきの一人の海賊だった。
はじめ、彼にはそれが自分の顔だとは信じられなかったが、次に笑いが込み上げてきた。騎士団の仲間が今の自分を見たら、はたしてかつての仲間だと気づくだろうか。これが、「金髪のぼうや」とからかわれた、軟弱なグリン・クロスフォードだとは!
しかし、彼には何故か、あまりそれが嫌な気分ではなかった。
苦手だったマスト登りもドリスに続いて二番目に速くなったし、剣の腕はもちろん、ルー・パイに教わったナイフ投げもかなり上達した。騎士団で学んだ大砲の扱いは海賊たちに教えるほどだし、帆を動かすときのロープ引きもコツも飲み込んだ。
ときに甲板の掃除をし、料理も手伝い、洗濯もやる。今の自分は、騎士団にいた頃よりよっぽど自立した生きかたをしている。海賊たちは粗暴で下品だが、案外正直だし人なつこい。彼はこの船で、ついに本来の自分の居場所を見だしたと感じることさえあった。
もうひとつ、グリンをこの船に惹きつけていたのは、いうまでもなくジェーンレーンの存在だった。
あのポート・イリヤでの一日からというもの、酒場で聞かされた彼女の身の上を思い返すにつれ、心の中では美貌の女海賊に対する気持ちが、日増しに大きくなっていった。甲板上でジェーンレーンと目があったり、船内ですれ違ったりすると、グリンは我知らず、胸の高鳴りを覚えた。
とある島で物資の調達を済ませたある日の夜、グリンはジェーンレーンに呼ばれ、船長室におもむいた。扉を叩いて部屋に入ると、テーブルには二人分の食事が並んでいた。
「たまには、食事でも付き合ってもいいだろう」
「も、もちろん」
グリンは胸を踊らせ、席に着いた。だが、それは彼の期待していたようなものではなかった。
食事の間、ジェーンレーンはほとんど口を開かず、むしろ不機嫌そうな顔でただひたすら食べ、ワインを飲んでいただけだった。胸をどきつかせたグリンは、ときおりちらりと相手を見るのだが、彼女は自分と目を合わせようともしない。
当てがはずれた思いで食事を済ませ、グリンは船長室を出た。
ひどくがっかりとした彼だったが、驚いたことに、その数日後にも、また誘いがあった。
今度こそはと、グリンは気合を入れて身だしなみを整え、なるたけ上等なシャツを着て船室を出た。船長室のテーブルには食事が用意されており、無愛想な顔でジェーンレーンが彼を迎えた。
期待と緊張とに声をかすらせ、グリンがつまらぬ挨拶を述べると、彼女は口元をゆがめた。そのとたん、すべての希望が消え失せた。
この前と同じに、彼女はひとつの笑顔も浮かべず、なにも話すことはないとばかりに淡々と食事をし、ワインを飲んでいた。その状況に耐えかねたグリンは、意を決して話しかけようとするも、彼女にぷいと横を向かれて、思いついた言葉も口の中で消えた。
またしても、味の分からぬ食事をしただけで、グリンはすごすごと部屋を出てゆくしかなかった。
これが三度目になると、もはや何の期待もなかった。船長室を訪れたグリンは、今日一日の出来事や船でのよもやま話を少しだけすると、あとはただ彼女と向かいあって食事をし、それが済むとワインを飲んでいる彼女を無言で眺め、やがて沈黙に耐えられなくなって彼が部屋を出てゆく。そして夜の甲板を歩きながら、一体どういうつもりで、彼女は自分を食事に誘うのだろうかと、ただ首をひねるのだった。
あるときグリンは、船室に来たルー・パイにそれを尋ねてみた。この船で、女の気持ちというものを一番知っていそうなのは、「彼女」をおいて他にはいそうもなかったからである。
もちろん、相手がジェーンレーンであるなどとはとても言えないので、「一般的に、女性が男を何度も食事に誘うというのはどういう意味なのか」と、さり気なく訊いた。
「あんた。どっかの町に女でもできたのかい?」
ルー・パイは怪訝そうに眉を寄せ、グリンに聞き返してきた。
「いや……その、そういうわけではなくて。ただなんとなく……そうだ、以前そういうことがあったもので」
「ふうん。なんだか怪しいね」
グリンの顔を覗き込み、彼女はにやにやと笑った。
「別に隠さなくてもいいんだよ。あんたがどこで女をつくろうが、あたしはとく束縛しないから。それに……そう、あんたは前よりもずっと素敵になったよ。なんていうか、ただの綺麗なおぼっちゃんでなく、男になったって感じでね。だからまあ、どこかの女がそんなふうに言い寄ってくるのも、まあ仕方ないさね」
まるで自分が恋人ででもあるかのような言いぐさに、思わずグリンは苦笑したが、それについては何も言わずにおいた。やんわりと擦り寄ってくるルー・パイの体をただ引き離すでもなく、すり抜けるように距離を置くやり方も、ここのところ彼が身につけた相手を怒らせずにやり過ごす方法だった。
「ふんだ。まあいいさ。それで?」
つれないグリンの態度に少し拗ねたようなルー・パイだったが、椅子に座りなおすと続きを聞きたがった。
「食事に誘って、それから?」
グリンは、具体的な場所や相手のことは隠しながら話した。彼女はあごを手で持ち上げながら、それをかなり熱心に聞いていた。
「なるほどね。つまり、何度も食事に誘うのに、色っぽい話はおろか、顔をまともに合わせもしないと……そういうわけね」
「ああ、そうなんだ。それはいったいどういうことなんだろう」
「そんなの、決まってるだろ」
首をひねるグリンを呆れたように見て、ルー・パイは言った。
「抱かれたいからだよ」
「な、なんだって?」
グリンは仰天したように声を上げた。
「だ、だって……、なにも言わず、こっちの顔を見ようともしないんだぞ?」
「はっ、馬鹿だねえ。これだから男ってのは。いいかい?女の方からもの欲しそうに相手の顔を見たり、何か色っぽい話を言ったりできるはずもないだろう。娼婦でもないかぎりさ」
「そ、そうなのか……」
驚いたグリンの顔が次には真っ赤になるのを見て、彼女は不敵な笑みを作った。
「なんだ。やっぱり、その女が気になっているんじゃないか。ねえ、いったいどこの女だよ。あんたが惚れたのは。もしかしてポート・イリヤでかい?それともどっか別の町で?」
「いや……そういうわけじゃ」
グリンは慌てて首を振った。
「でも、まったく愛想もないなんてのは、よっぽどのウブのねんねか、でなければ、そう……とんでもなく気位の高い女だね」
ルー・パイはそう言って、じっとグリンを見つめた。
「あたしだったら、好きな男にはそれと分かるように迫っちまうけどね。ほら、こんなふうに……」
「……」
にじり寄ってくるルー・パイに礼を言うと、グリンは逃げるように部屋を飛び出した。
狭い廊下の突き当たりのハッチから船倉へ入る。一人になりたいとき、このひんやりとした船倉はうってつけなのだ。
(ジェーンレーン……)
暗がりの中を、グリンはうろうろと歩き回った
(彼女が自分を?まさか……)
考えながら、ときおり首を振る。そしてまた、考える。
(いや、しかし、もしかして……) もしそうなら……
床に転がった索具につまずき、樽に体をぶつけながら、グリンは暗い船倉を歩き回り、それから床に座り込んだ。
(俺は……)
膝を抱えてじっと考え込んでいた彼は、ついに何事かを決意したように顔を上げた。拳を握りしめ、立ち上がったその顔は、まるで戦に向かう戦士のように凛々しかった。
ブルー・マスター号は順調な航海を続けながら、キャスタナル諸島の島々をめぐっていた。ポート・イリヤを出てひと月近くがたった頃、ついにグリンの待ち望んでいた機会が訪れた。
「今日の夕食は船長室でとるように。お頭の命令だ」といつものように、料理長から告げられたグリンは、今日こそはとばかりに、勢い込んで身だしなみを整え、船長室の扉をノックした。
「来たか。まあ座れ」
白いシャツにズボン姿のジェーンレーンが、無愛想に彼を出迎えた。これもいつもの通りだ。
妙に目つきの鋭いグリンの顔を見て、彼女は一瞬眉をひそめたが、ともかく二人は席に着き、勝負の食事が始まった。
今日のメニューは、塩漬け肉と野菜のスープに、ローガンが銃で撃ち落としたカモメ肉のソテー、それにチーズとパンだった。これでも普段よりはやや豪勢な部類である。
食事の間、グリンはじっとジェーンレーンを見つめ続けた。彼女の方は、グリンと視線を外すように顔をそらし、いつのように黙々とスープを飲み、パンをちぎってはそれを口に運んでいた。
だがグリンはへこたれなかった。彼の決意はおそらく大変なもので、その引き結んだ口元には「まるで今日という日を逃したら明日はない」というような、鬼気せまる意気込みを感じさせた。
そして彼は、無言の食事についに終止符を打った。
ひととおり料理を片付け、彼女の杯にワインを注いでやり、自分のにも注いでそれを一口飲むや、彼は敢然と立ち上がった。
ジェーンレーンは、はっとしたように彼を見上げた。この部屋に来てはじめて、まともに二人の目が合った。
「ジェーンレーン」
力のこもった声で、グリンはその名を呼んだ。
「あの……俺は」
緊張に声を震わせながら、グリンは勇気を振り絞った。
「あ、あなたに訊きたいことが……」
「……」
杯を置いた彼女は、驚きに目を見張るようにして相手を見た。ワインのせいかその頬はわずかに紅潮している。
「な、なんだ?」
互いのうわずった声が重なった。まるでブリキの仕掛け人形のように、二人はぎこちなく向かい合っていた。
「その……。あの、つまり……」
グリンは、背中に汗が流れるのを感じた。顔を真っ赤にして、なんとか言葉を口の中から押し出そうと奮闘する。
「……」
ジェーンレーンも、いつになく緊張した顔つきでグリンの言葉を待っていた。口を引き結んで眉をつり上げた彼女は、ほとんどグリンを睨むような顔をしていたかもしれない。
「あ、あの……」
彼はにわかに、もしかして彼女が怒っているのではないかと思いはじめた。するどい眼差しで自分を見つめている様子は、ひどくいらいらとしているようにも見える。
「……その、つまり」
「つまり、何だ?」
聞き返す彼女の声の鋭さに、グリンの気力が萎えた。
「あの……」
たまらず、彼はとんでもなくつまらぬことを口にした。
「こ、この船の……次の停泊港はどこでしょう?」
そう言って、がっくりとうなだれたグリンは、もう彼女の顔をまともに見ることができなかった。
「……」
ジェーンレーンは黙り込んだ。その顔を凍りつかせて。
どれくらいの時間が過ぎたろうか……おそらくそれは一瞬にしかすぎなかったろうが、グリンにとってはまさに炎に焼かれるような永劫の苦痛の果てだったに違いない。
ようやく、怒りかそれとも失望にか、あるいは別の何かにか、彼女は震える手で杯を持ち直し、ごくりとワインを飲んだ。そして無慈悲に言った。
「知りたければ……オギナに聞くのだな」
その声のあまりの冷たさに、グリンは二度とチャンスが来ないことを知った。敗北感にうちひしがれ、肩を落として立ち上がった彼の顔は、死人のように青ざめていた。
それからというもの、船上や船室でジェーンレーンを見かけても、彼はもうまともに目を合わせられなかった。グリンは、己の勇気のなさ、不甲斐なさを呪った。自分がどうしようもなく愚かな、取るに足らぬ人間に思えた。
だが、たとえそうであっても、彼の周りにはよく人が集まった。
ルー・パイは、まるで自分が「定められし運命の恋人」のような顔をして、なにかにつけグリンに付きまとった。食事の席では常に隣に座り、これまでは手が荒れると言ってほとんどしなかったマストのロープ引きでさえも、グリンの横に来て縄を握り、女らしい様子で……といってもその声はまさしく男のものであったが……一緒に掛け声を上げるのだった。
小さなドリスは、グリンの話を聞きたがった。それは主にどこかの国の港町の話とか、航海の話などであったが、自分が騎士団にいたことなどは言うことはできないので、グリンは少年に悟られない程度には嘘をつかねばならなかった。それでも、ドリスは熱心にグリンの話に聞き入った。おそらくこの少年は、物心ついたときからこの船に乗っていて、海賊船から見る世界の他は知らないのだろう。
その他の海賊たちも、彼によく話しかけてきた。男たちは、船における細かなしきたりやタブーなどを教えてくれ、港に着いたら一緒に飲みにゆこうと誘ってきたり、逆に剣の上達するコツを教えて欲しいと頼んできたりした。この船の海賊たちは、グリンのことをすっかり仲間として気に入っていたのだった。
七月のある日、ブルー・マスター号は、キャスタナル諸島の西側に位置するキーオス島に立ち寄った。
キーオス島は、白い砂浜に囲まれた緑豊かな小島である。オギナの話では、この島には、ポート・イリヤほどではないが海賊たちと取引をする裏商人や情報屋などが多くおり、どこそこの商船がどの海域を通るとか、その積み荷の情報、さらには大きな海賊団の近頃の動静といった最新の情報までが手に入るのだという。
上陸にあたって、今回もジェーンレーンの護衛役を定めるための剣技会が開かれたが、勝ち残ったのはまたしてもグリンであった。
馴染みの情報屋と接触するだけのごく短い上陸になので、二人を下ろして、他のものは船上で待機することになる。単に情報を買うだけであれば、誰が行ってもよいような気がするが、用心深い情報屋を相手にする場合は、どうしても船の船長が直々に顔を見せなければ信用されないのだという。
装備を整えたグリンは、甲板から湾内をざっと眺めた。湾の沖合には数隻の船が停泊していた。そのうちの一隻に彼は目を止めた。
(あれは……)
それは、海賊船にしてはいくぶん大型のガレオン船であった。塗装といい雰囲気といい、一見してただの商船のようではあったが。
(見覚えがあるぞ……あの船)
喫水の浅いブルー・マスター号が、左舷に見えるそのガレオン船を追い抜いてゆく。船の船首が見えた瞬間、グリンは思わず声を上げそうになった。
尖った船首の横に、その船の名前がはっきりと刻まれていた。
(クインズ・ドウター号!)
数隻の海賊船に混じって湾内停泊していたのは、まぎれもない、かつてグリンの乗っていたタンタルス号とともに出帆した五隻の騎士船のひとつ、クインズ・ドウター号だった。
タンタルス号から脱出して以来、ともに任務についている他の騎士船のことは常に気になっていた。あるいは他の船も海賊に襲われ、拿捕されてしまったのかとも考えたこともあった。
こうして、そのうちの一隻をこの目で見られようとは……
(無事だったのか……)
後方に過ぎ去ってゆくその船を見ながら、グリンは己の内でこみ上げてくるある思いに戸惑った。それは、「騎士」という二文字であり、果たすはずの自分の任務、そして仲間たちのことであった。
「どうした?あの船がどうかしたのか」
グリンは、すぐそばに来たジェーンレーンに気づかなかった。はっとして振り向いたときには、彼女は目の前に立っていた。
「い、いや。なんでも……」
自分を見ている女海賊のまなざしから逃れると、グリンの心の震えはいっそう大きくなった。
だが、もう、自分はここにいる……海賊船の一員として。
この美貌の女海賊、赤毛のジェーンとともに。
ここにいるのだ……
そう思ってみても、どうしても吹っ切れないものがある。
「……」
グリンはぎゅっと拳を握りしめた。
「もう、すぐにボートに降りるぞ。用意はいいのか?」
「あ、ああ……」
曖昧にうなずくグリンを見て、ジェーンレーンは周りに聞こえぬように囁いた。
「お前が行きたくないのなら、べつにかまわんが……用はすぐ済むし、私ひとりでもどうということもないからな」
「いや……」
グリンは首を振った。
「僕もゆく。ただ……ちょっと、少し待ってくれ」
「なんだ?」
「部屋に、部屋に忘れ物をした。……ナイフだ。護身用の。念のためにとってくる」
そう言い残し、グリンは急いで船室に降りていった。
少しして戻ってきた彼は、何事もない様子でジェーンレーンの待つボートに乗り込んだ。その首もとには、鎖の付いた銀色のコンパスがかけられていた。
「終わったぞ。待たせたな」
港町の片隅にある小さな酒場から出てきたジェーンレーンは、目的を果たしたことをグリンに告げた。
「次の獲物は決まった。それから、他にもちょっとした情報をもらった」
「そうか」
満足げなジェーンレーンにうなずいたグリンだったが、少し拍子抜けしていた。町は思ったよりも安全で、誰かに襲われたりするようなことはなかった。この町自体が小さく、住むものは海賊相手の商人と情報屋くらいのもので、ポート・イリヤのように酔っぱらいや柄の悪いごろつきなどがうろついていることもない。
「情報では、やはりドルテックのやつらが、色々と企んでいるらしいことは確かなようだ」
港への帰り道、夕暮れの通りを並んで歩きながら、ジェーンレーンは得てきた情報をグリンに聞かせた。
「ポート・イリヤで武器を買っておいたのは正解だったな。ドルテックのやつらはそのすぐ後で、ほとんど武器を買い占めたらしい。近々大きな戦いでも起こすつもりなんだろうとさ。どうも、それにはアナトリア騎士団の大規模な動きが絡んでいるらしいな」
「ほう、そうなのか」
グリンは白々しく相槌を打った。
こうして彼女と二人で話すのは、この前夕食に招かれて以来だったし、自分に対して彼女がもう腹を立ててはいないようなので、グリンはほっとした。だが、同時に、「騎士団」という言葉を聞くたびに、己の中で何かがずきりと痛むのを感じてもいた。
(やはり、やはり俺は……)
ボートの置いてある砂浜まで来たとき、グリンは己のなすべきことを決意した。
「すまない。先に船に戻っていて欲しい」
「どうかしたのか?」
「ああ、いや……さっきの町で、以前の商船の仲間が通りかかるのを見たんだ。少しだけ話をしてきたいんだが」
「ああ、わかった」
とくに怪訝そうな顔もせずジェーンレーンはうなずいた。グリンは「すぐに戻る」と言い残し、早足に今来た道を戻りだした。
日が沈みはじめた通りには、人影はまばらだった。グリンは辺りを見回した。
海賊たちに「情報屋通り」と呼ばれるこの通りには、酒場や食堂、それに宿屋などが多かったが、そのほとんどが、裏では密輸入や武器の密売を請け負ったり、あるいは情報屋が表向きの顔として営む店であるという。
この通りで仲間を見かけたのは本当だった。さきほど店の外でジェーンレーンを待つあいだ、グリンは通りをゆく商人らしき一団の中に、騎士団での知った顔を見つけていた。
(あれは、間違いなくクインズドウター号の騎士たちだ)
彼らは商人を装い、何らかの情報を求めてこの島に来たのだろう。港で船を見かけなければ、おそらく気づかなかったかもしれない。
通りを見回していると、「六つの尾っぽ亭」という食堂の看板が目に入った。
(あの店だ)
ついさっき彼らが入っていった店に違いない。グリンはにわかにどきどきとしはじめた。久しぶりに仲間の騎士たちに会えるのだ。
だが、別の不安もあった。おそらく今の自分を見て、かつての顔見知りでさえも、これがグリン・クロスフォードだとは分からないに違いない。日に焼けた浅黒い顔に不精髭を伸ばし、汚れたシャツと破けたズボン、そして腰に下げた短剣に、改造した小銃……今の自分は、きっと誰が見ても立派な海賊にしか見えないだろう。
だが、これが自分の使命なのだと、グリンは首にかけたコンパスをぎゅっと握りしめた。
近づいたグリンを、店の前にいた見張りがうさん臭そうに睨んだ。この男も騎士なのだろうが見覚えはない。
「……」
店に入ろうとグリンが扉に手を掛けようとすると、男は「待て」と腕をつかんだ。
「ここはしばらく貸し切りでな。他をあたりな」
低い声で男が言った。やはり、こちらを海賊だと思って怪しんでいるようだ。グリンはさっと辺りを見回し、近くに人がいないことを確かめてから、小声で言った。
「店にいるのはクインズ・ドウター号の方々か?」
「なに?」
それを聞いて、男は驚いたような顔をした。
「俺は……俺は、タンタルス号の者だ」
思い切ってグリンが告げると、
「なんだと?」
仰天した様子で、男は声を上げた。
「タンタルス号だと?馬鹿な。あの船は襲撃を受けて……」
男の気がそれたすきに、グリンは掴まれていた手を振り払った。
「あっ、おい!」
飛び込むように店の中へ入ると、そこにいた五、六名の男たちがこちらを振り返った。
「なんだお前は!」
彼らは一斉に銃を取り出した。
背後からは見張りの男が飛び込んでくる。
「この野郎!」
「静かに。怪しいものじゃない」
こちらに向けられたいくつもの銃口を前に、グリンはゆっくり両手を上げた。下手をすればこのまま海賊と勘違いされて、口封じに殺されることになる。
「……」
グリンは、自分が何を言うべきかを考えた。とにかく、まずは敵ではないことを知らせるしかない。
銃を構えた騎士たちが、じりじりと詰め寄ってきた。
緊張に身を固くしながら、グリンは思い切って声を発した。
水平線に日が沈みはじめていた。
残照がきらきらと水面を照らす波打ち際に、ジェーンレーンの姿を見つけた。
「やあ、戻ったか」
こちらに気づいて振り返った彼女が、軽く手を挙げた。
グリンが走り寄ると、砂を払って立ち上がったジェーンレーンがにこりと笑った。
「待っていてくれたのか」
「ああ。砂が……気持ちいいのでな」
彼女は裸足だった。
「それに……私はお前にあやまりたかったんだ」
「あやまる?」
グリンは驚いて聞き返した。
「ああ……」
足の先で砂を掘りかえす彼女は、薄く頬を染めているように見えた。それとも、それはただ夕日のせいだったのだろうか。
「やはり怒るだろう。何度も……食事に呼んだり、でも……」
ジェーンレーンは口ごもった。
「私はそういうつもりじゃ……」
困ったように、浜風になびく赤毛をすいとかき上げる。
「ああ、いや、だから……な」
そんな彼女はとても美しかった。
「私は……」
いったい、彼女は何を言いたいのだろう。グリンは、こんなとき何を言えばいいのか知らなかった。要領のいい男であれば、きっとうまい台詞で助け船を出したり、あるいは、やさしく肩でも抱いたりできるのだろう。
だがグリンには、ただ馬鹿のように突っ立っていることしかできなかった。なんといっても、相手は名高い女海賊なのだ。勘違いをすれば、張り倒されるのが目に見えている。
「……」
沈みゆく夕日を海の彼方に見ながら、二人は砂浜に立ち、ただ黙って向かい合っていた。
「お前は……」
ジェーンレーンが囁くように言った。
「普通の男たちとは違うのだな。なんというか……つまり、紳士なのだな」
自分が褒められているのか、馬鹿にされているのか、それすらもグリンには分からなかった。
「私が悪かった……」
「え?」
「お前は……私の知っている男たちたちとは違う……」
グリンは、自分を見る彼女のまなざしに、にわかに鼓動が早くなるのを感じた。
「ジェーンレーン……」
震える声でグリンがその名を呼ぶと、彼女はくすりと微笑んだ。
「ああ。他の連中なら張り飛ばすところだけどね。お前なら、いいよ。そう呼んでも」
グリンがおそるおそる手を差し出すと、女海賊はその体をそっと寄せてきた。
「ジェーン……レーン」
「ああ、グリン」
二人はぎこちなく、そして静かに、砂浜の上で抱き合っていた。
すでに夕日は海の向こうに沈みゆき、空は深い紫に色を変えはじめていた。海岸線はゆるやかにその暗さを増してゆき、砂浜の二人を包み込む。
「お前は紳士だが、」
耳もとで彼女は囁き、そっと目を閉じた。
「……こうすれば、分かるか?」
風になびく髪が頬をくすぐる。
グリンは、女海賊の細い体を引き寄せた。
顔を近づけようとした、そのとき、
「……?」
奇妙なものが見えた。
「あれは……なんだ?」
無意識のつぶやきが漏れ、グリンの目が大きく開かれた。
「ん……どうした」
じれたようにジェーンレーンが目を開けた。
グリンの視線を追うように、振り返った彼女の口から、「あっ」と叫びが上がった。
暗くなりはじめた空に立ち上る黒煙……
そして海上に、赤々と燃える火の玉が見えた。
「あれは……」
呆然とするグリンの横で、ジェーンレーンは、その鋭いまなざしを燃える火の玉に向けていた。
「焼き討ち船だ」
「焼き討ち……船?」
二人の見ている前で、猛烈な煙を上げながら、燃え盛る炎の塊は、どんどんとこちらに近づいていた。
■次ページへ