ブルーランド・マスター
3/11ページ
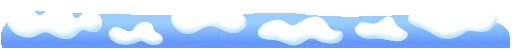
■3■脱出
甲板上の騎士たちに戦慄が走った。
不気味なスループ船の正体が、よもやあの、悪名高きドルテック海賊団のものだとは。マロック海において、もっとも恐れられる海賊団の一つであり、とくに首領のドルテックは、血と殺戮を好む残酷無比な海賊として知られている。その名前は、すべての船乗りたちにとって、災厄ともいうべきものに他ならなかった。
「静まれ。皆、落ちつくのだ」
艦長の一喝で、ざわめきはじめていた騎士たちは口をつぐんだ。
「艦長……やはり、ここは攻撃命令を」
そう進言する副長に、しかし、艦長は首を横に振った。と
「こちらも旗を上げろ。ここで抵抗すればもっとまずいことになる。あくまで商船であることを通すのだ」
タンタルス号のミズンマストに、「交戦の意思無し」を意味する青旗がかかげられた。すると海賊船は滑らかに反転すると、タンタルス号の左舷に横並びに近づいてきた。
「いいか、海賊たちが来ても銃を出すな。誰も抵抗するな」
緊張する騎士たちに、艦長は念を押した。
「海賊船からジョリーボートがやってきます」
やはり、海賊はこの船を検分をするつもりらしい。甲板の騎士たちは騒ぎ立てるのをやめ、言われた通りに整列すると、商船の船員を装うように、それぞれ自分の服装を念入りにチェックした。
海賊船からのボートが横付けされると、どやどやとした気配がして、やがて、船縁に太い腕がぬっと現れた。
「こらしょ……っと」
甲板に最初に立ったのは、黒髪を後ろに束ねたがっしりとした体格の男だった。男はぎらついた目で周りを見回し、言い放った。
「こりゃ、商船にしちゃあずいぶんと小奇麗な甲板だな。はっ」
それが、この海賊団の首領、ドルテックその人であることを、船員たちの誰もが疑わなかった。
他の海賊たちも続々と甲板に上がってきて、それぞれが物騒な目つきで甲板を見回しはじめた。
「さて、船長はどいつだ?」
男はドスの聞いた声で尋ねた。
「私だ」
ブレイスガード艦長が後部甲板から下りてきた。
「へえ、あんたが」
男は無遠慮な目つきで、艦長の顔から足先までをじろじろと見た。
「まず言っておくが、妙な真似をしやがったら、容赦しねえ。俺の船の砲門はずっとこっちを向いているからな。それは覚えておけ」
威嚇的なその言葉に、若い船員がごくりと喉を鳴らした。その横で、グリンはそっと、その海賊の首領を目で追った。
背はさほど高くはないが、足や腕も丸太のように太く、真っ黒に日焼けしている。縮れた髪を束ね、歪んだ口許には皮肉めいた笑みが浮かび、その目つきは鋭く残忍そうで、右の頬にはナイフで付いたような十字の傷があった。赤い長シャツにだっぽりとしたズボン、ベルトにはサーベルと小銃が無造作に突っ込まれている。
その周りの部下たちも、いかにもごろつきらしい凶悪な面構えだ。みなそれぞれに長い銃身のマスケット銃や、剣、ナイフなどを無数に身につけ、獰猛そうなぎらついた目でこちらを見ている。
「言うまでもないだろうが」
首領の男は、タンタルス号の若い船員たちを見回し、臓腑に届くような低いかすれ声でその名を告げた。
「俺はドルテック。ドルテック海賊団の頭だ」
居並んだ船員たちの顔が青ざめるのを、気持ち良さそうに見回し、髭づらの海賊はにやりと笑った。
「しかし、我々は商船です。ただの商人にすぎませんよ」
ブレイスガード艦長は、その顔に怯えた様子を作りながら、おずおずと言った。なかなかの役者ぶりである。
「名高き海賊の猛者、ドルテック様に逆らおうはずはありませんが、こうして商売の妨げをされては、私どもとしては非常に……」
「黙っとけ、船長さん」
海賊は、凄味をきかせた目でぎろりと睨んだ。
「そんなことは知るか。ここは俺らの縄張りよ。拿捕するか掠奪するかは全部俺っちが決めることだ」
海賊はずかずかと甲板を歩き回りはじめた。その間、彼の部下たちは、船員たちを見張るように武器を手に睨みをきかせている。
「しっかし、この船はよう……」
後部甲板の端まで行ってまた戻ってくると、海賊はブレイスガード艦長に向かって言った。
「ポート・イリヤに来るような商売人の船にしちゃあ、こぎれいすぎるな。ああ?」
艦長は黙ったまま平静を保った。
「それに……、船員もな、見れば妙にガタイがいいのが揃っている。どいつも若いしな」
うさん臭そうな目つきで居並んだ船員たちを見渡すと、海賊は部下の一人を呼んだ。
「おいフリッツ。お前、何人か連れて船倉を見てこい」
「へい」
「ただの商船かどうかは、積み荷を見りゃあ分かるからな」
にやりと酷薄な笑いを浮かべて、ドルテックは言った。
「それから、そうだな……案内に誰か適当な奴を、おい……お前」
指をさされたのはグリンだった。彼はきょとんとした顔をして左右を見回した。
「そう、そこの若造……お前だよ。とっとと来い」
「あ……お、俺」
なるたけ目立たぬようにしていた自分が、どうして指名されたのだろうと、グリンは戸惑いながら、にわかに心臓の鼓動が早くなるのを感じた。
「おい坊や、俺をなめるなよ。早く来いっていったら来いよ。それともなんだ、怖くて足がすくんで動けねえってのか?」
後ろに並んだ海賊たちがげらげらと笑った。
「……」
グリンは侮辱に腹を立てるよりも、これから自分がどうなるのかという不安で頭がいっぱいだった。
「この坊やなら抵抗することもねえだろう。気が弱そうだし、戦いの経験などもないだろうしな」
海賊はグリンをじろじろと眺め、満足そうにうなずいた。
「よし、こいつを連れてって積み荷を調べてこい。不審なものが見つかったらすぐに俺を呼べよ。いいな」
「へい。来な、坊や」
「……」
銃を手にした海賊にうながされ、グリンは歩きだした。ブレイスガード艦長に目をやると、艦長はこちらに向かってうなずきかけた。
(……艦長)
すれ違いざまに、艦長は自分の手に何かを押しつけてきた。それが何なのか分からなかったが、海賊たちに見つからぬよう、グリンはそれを握りしめた。
「早く来いよ。なにをぐずぐすしてやがる。ほら、案内しろ!」
手にはランタンを持たされ、背中には銃を押しつけられて、グリンは船内へのハッチをぐった。
後ろに銃を持った海賊たちを連れて船内を歩き、船倉へと続く階段を降りる。背中を押されながら、彼は自分のなすべき使命について考えていた。
艦長から渡されたものは、手の中の感触から想像出来た。そして、その意味について考えると、しだいに恐怖をも上回る、騎士としての任務遂行への意志が、心の中に大きくつのってゆくのだった。
(恐れるな……勇気を、勇気をもつんだ)
タンタルス号の船倉は、いかにも大型の商船を改造した船らしく、とても広かった。巻かれたロープや滑車などの索具が山積みされ、たたまれた予備の帆や索、ケーブルなどと一緒に並べられていた。
「へえ、さすがにこれだけでかいガレオン船ともなると、船倉も立派なもんだ」
「商用の積み荷はこの左側の樽に入っています。主に、ワインや果物などが中心で……」
説明するグリンからランタンを引ったくり、海賊は並べられた樽の前を歩き回りはじめた。
「こう数が多くちゃ、いちいち確かめるのも面倒だな。おいお前ら、適当な樽をいくつか開けてみろ」
この中ではリーダー格らしい背の高い海賊が、仲間に命じた。
「へい」
命じられた二人が、それぞれに目についた樽の蓋を叩いて壊し始めると、グリンは慌てて声を上げた。
「こ、困ります。それらは大切な商品で、これからポート・イリヤに陸揚げするものなんです」
いかにも商人的な物言いで懇願するが、海賊は取り合わない。
樽に隠された武器や火薬などを見つけられるのが、最も恐ろしいのは言うまでもない。ただ、それら特別な樽は見つかりにくいよう奥の方に収めてある。グレンはその場所をしっかりと把握していたので、海賊たちが壊す樽が、それではないことは分かっていた。
「おおっ、こりゃワインですぜ。たっぷりと詰まってら。うひ」
樽の中を覗き込んで、海賊が歓声を上げた。
「一口だけ。一口だけ飲んじまってもいいでしょうね?」
「馬鹿野郎。今はダメだ。見つかったらお頭に半殺しにされるぞ」
「はあ……わかりやした」
海賊は残念そうに樽の木蓋を閉じた。別の海賊が開けたのは果物の入った樽だった。
「こりゃただのライムですぜ」
手にしたライムをひとつ手にしてかじり、海賊はすっぱそうに顔をしかめた。
「ふん。酒に果物……やっぱりただの商船か」
海賊は並んだ樽の前を歩き回り、時々樽を叩いたり蹴飛ばしたりした。グリンは武器が見つからないかと、気が気でなかった。
もし商船を偽装したのがばれ、この船が騎士団の海賊討伐の船であることが知られたら……そのときはどうなるのだろう。
皆殺しか。それとも、海賊たちと戦って勇ましく散るのか。どちらにしても作戦は失敗に終わるのだ。
「……」
グリンはその左手に、艦長から受け取ったものを、それが己の護符であるかのように握りしめた。
「もういいだろう。報告に戻るとするか」
海賊たちは目についた樽を全て叩いてみると、つまらなさそうにぺっとつばを吐いた。
グリンは心底ほっとした。
実際には、並べられた樽のうち一番奥の列の半分が、武器と火薬の入った樽で、他の半分が空洞の樽だった。海賊たちはそれに気づくことなく、グリンを連れて船倉を後にした。
これで作戦はうまくゆく。グリンはそう希望を持った。
さらに運が良いことが起こった。
来るときと同様に、背中に銃を向けられながら階段を上り、船内を歩いている途中、「バーン」という銃声が聞こえてきた。
「なんだ?誰が発砲したんだ」
「奴らが反抗したのかもしれんぞ」
海賊たちは顔を見合せ、慌てて走り出した。
(しめた……)
甲板への階段を上ってゆく海賊たちを見て、グリンはそのまま反対側へ駆けだした。
(船長室は一番船尾だ……)
迷うことなくグリンは走った。
ちらりと振り返ると、海賊たちの姿はもうなかった。甲板に上がったのだろう。
グリンもさっきの銃声が気にはなったが、きっと海賊の誰かが威嚇のために撃ったものだろうと考えた。今はそれよりも、自分には艦長に託された使命があるのだ。
普段なら丁重にノックするはずの艦長室のドアを、グリンは乱暴に開けて、室内に飛び込んだ。
タンタルス号の船長室は、商船として偽装されているため、見た目は地味な普通の船室だった。テーブルの上にはカモフラージュ用に商用の海図が広げられ、その横にはコンパスや天測機、砂時計、それにこちらも見せかけの、積み荷の商品リストなどが置いてある。
室内を見回し、グリンは壁際の戸棚に近づいた。鍵穴がついているのは、この古めかしい戸棚だけだったからだ。
艦長から渡されたもの……左手にずっと握りしめていた鍵を、グリンは戸棚の鍵穴にはめた。カチリと音がして鍵があいた。
戸棚のの中には、銀貨の入った革袋や高級そうなパイプ、拳銃の弾丸などがあった。それらをかき分けると、奥のほうに丸められた紙が無造作に置かれていた。紙を広げてみると、それは、昨夜の会議で艦長が見せた、海賊のアジトが記された海図だった。
「……これだ」
グリンは少し考えると、それを丁寧に小さく折りたたみ、机にあった丸い銀のコンパスの蓋を開けて、そこに押し込んだ。
そのとき、再び頭上で銃声が聞こえた。それも今度は数発、続いて悲鳴や怒声のような声も聞こえてきた。
グリンは急いで海図を入れたコンパスを懐にしまい、部屋を出た。
もと来た廊下を走り、甲板へと続く階段の前まで来ると、海賊たちの怒声が聞こえてきた。グリンは、音をたてぬように慎重に階段を上り、ハッチからそっと顔を出して甲板の様子を窺った。
「……」
思わず、「あっ」と声を上げかけるのを、自分の口を手で塞いでこらえた。
彼が見た甲板上の様子は、タンタルス号の乗組員たち……艦長を含めたほぼ全員が中央のマスト付近に追いやられ、その周囲を銃を手にした海賊たちが取り囲んでいるところだった。すでに数人の乗組員は、血を流して甲板に倒れている。
(く……なんてことだ)
グリンは懐から銃を取り出した。すぐさま飛び出してゆき、海賊たちを撃ってやろうかと考えたが、なんとかそれを自制した。
数十人の海賊たちを相手に、自分一人が向かっていっても、到底勝ち目があるはずはない。それに今出ていけば、囲まれている仲間たちが海賊に撃たれてしまうだろう。
(くそ……どうすれば)
唇を噛みしめ、グリンはハッチの影からしばらく様子を見守った。
「馬鹿めが」
海賊たちの首領、ドルテックの声が甲板上に響いた。
「つまらん抵抗をしようとするからそうなる。懐にスナファンス銃を隠しているなんざ、ただの商人のすることじゃねえな」
乗組員たちの前をのしのしと歩きながら、海賊は鋭く言い放った。
「いいか貴様ら。俺に逆らったら皆殺しだ。次に撃ってみろ、もう容赦はしねえ。ここにいる全員を切り殺して塩漬けにして、焼いて食ってやる。嘘じゃねえぞ。俺はやるといったらやるんだ!」
海賊は腰から剣を引き抜き、それをぶんぶんと振ってみせた。
「船倉の積み荷は一応異常はなかったみたいだが、それだってまだ信用できねえ。さっきの案内の小僧は姿をくらましたっていうしな。まあいい、あとで船内をくまなく探して、怪しいものがないか徹底的に洗い出してやる。あの小僧も見つけたらぶっ殺す」
その言葉にグリンは内心で震え上がった。
(どうする……、どうすればいい)
グリンは必死に考えた。ここで自分がこうしていても、事態はどうにもならない。そしてなによりも、艦長から託されたこの大切な海図を守らなくてはならないのだ。
(くそ……。落ちつけ。こういうときこそ冷静になれと、教わっていたはずだ)
しかし、どきどきとする胸の鼓動は高まるばかりだった。
「さあ、銃を持っている奴は全員こちらに渡せ。そうすりゃ命だけは助けてやってもいいぜ」
ドルテックが船員たちに命じた。船員たちは、皆どうすればいいのかいうように、艦長の方を見た。
「そら、どうした。早くしろ!そうすれば、この船を商船だと認め、なんならポート・イリヤまで送っていってやってもいいんだぞ」
(ダメだ……たぶん、銃を捨てさせたら、奴らはこの船を完全に制圧するつもりだ)
グリンにもそのくらいは分かった。ブレイスガード艦長にもそれは分かっているはずだ。
(どうするんだ……艦長は)
ハッチの影から見守るグリンは、ごくりとつばを飲み込んだ。
海賊たちは、それぞれに先の曲がった長剣を引き抜いた。
「さあ、どうした。船長さんよ。まずはあんたからだ」
「分かった……」
ブレイスガード艦長は、懐からスナファンス銃を取り出した。
「へっ、やはり隠してやがったな」
「……」
艦長は、銃を渡そうとするように手を伸ばした。
「皆、よく聴け」
かちり、と音がした。
「最後まで……騎士として」
「戦え!」
そう言うと同時に、ズガーンという音とともに海賊の一人がひっくり返った。
「野郎!」
意表をつかれた海賊たちが、マスケット銃を撃ち返そうとする。
「散らばれ、皆!」
艦長が叫ぶ。囲まれていた騎士たちは、取り出した銃を手に、一斉に甲板上に散らばった。
「わああっ」
「この、くそ野郎!」
「撃て、撃て!」
一瞬にして、甲板上は怒号と銃声の飛び交う戦場と化した。
「うわっ」
「ぎゃっ」
至近距離で海賊に撃たれた騎士が、血を吹き出して転がる。
スナファンス銃を撃ちながら、甲板上を走り回る騎士たち。それを剣を振り回して追いかける海賊たち。
「こいつらは商人なんかじゃねえ。騎士だぞ!」
「皆殺しだ!」
「犬どもを全員ぶち殺せ!」
海賊たちの凶悪な叫びがこだまする。
「ぎゃあっ」
「ぐあっ」
目の前で始まった戦いを、グリンは呆然と見つめていた。
海賊の大剣で首を落とされる騎士が見えた。飛び交う銃弾が近くをかすめる。
吹き出す血と、断末魔の絶叫。怒号と悲鳴が入り混じり、タンタルス号の甲板を、地獄のような阿鼻叫喚が支配していた。
騎士たちは一人、また一人と切り殺されていった。
至近距離の戦闘では、単発式の銃火器よりも、剣やナイフの方が有効である。騎士たちが一発撃って弾を込める間に、襲いかかってきた海賊のナイフがその喉元を掻き切り、弾がなくなって逃げまどう騎士の背中に、海賊の剣が容赦なく振り下ろされた。
いくら鍛えられた騎士たちとはいえ、素手で剣に立ち向かうのは不可能だった。その上、海賊はよく訓練されていて、こうした暗闇での戦闘にも慣れていたに違いない。
百名近くの船員に対して、海賊は二十名ほどの人数であったにもかかわらず、彼らは次々と騎士を追い詰めては殺し、あるいは手傷を負わせると海にたたき込んだ。
船上は海賊による殺戮の場と化していった。
その光景を影から震えながら見ていたグリンだったが、彼はようやく意を決したように、銃を手にハッチから飛び出そうとした。
そのとき、横からぬっと手が伸びてきて、彼の体を押さえつけた。
「わっ」
思わず悲鳴を上げ、もがこうとしたグリンだったが、「しっ」という耳元の声が彼を制した。それはブレイスガード艦長だった。
「か、艦長……ご無事でしたか」
「ああ。あまり……無事ではないがな」
艦長は、グリンの体に寄り掛かるようにしてにやりと笑った。その額からどろりと血が流れ落ちる。
「いいか。よく聞け」
甲板ではまだ所々で戦いが続いているらしく、悲鳴や銃声がときおり聞こえてくる。周囲を見やりながら、艦長は低く囁いた。
「あの海図は?」
「は、私が持っております」
「よし。では、それをなんとかして他の艦に届けるのだ。いいか」
「は、はい」
「この船は……もうだめだろう」
声を振り絞り出す艦長は、体に何箇所も傷を負っているらしく、ひどく苦しげな様子だった。
「お前は……なんとか生き延びろ。どこかに隠れて、奴らの隙を見て船から逃げるんだ」
「しかし……」
グリンは唇を震わせた。なんと言ったらよいか分からない。
「奴らは残虐だ。見つかればお前も間違いなく殺される」
荒い息を吐き、かすれる声で艦長は言った。
「そうなったら、作戦は失敗に終わる。なんとしても、その海図だけは……ぐっ」
「艦長!」
「行け……。はや……く」
最後の力で立ち上がった艦長は、グリンをハッチの中に押しやると、そこを守るように動かなかった。
「頼むぞ……」
「まだ生きているぞ」という海賊の声と、何発も銃弾が打ち込まれる音が、ハッチの内側にいるグリンにも聞こえた。
「う……」
叫び出しそうになるのをこらえながら、彼は階段を駆け下りた。
海賊たちは、甲板を制圧すれば船内に下りてくるだろう。ここで泣き叫んでも何にもならないのだ。
(そうだ、俺の使命は……やつらからこれを守るんだ)
手の中のコンパスを握りしめる。今はともかく、船内に隠れて海賊をやり過ごことす……それしか考えられなかった。
船倉まで来ると、グリンはその静けさに少し安堵しながら、辺りを見回した。やはり、隠れるとしたらこの場所が一番のはずだ。
「ん?……」
暗がりの中に人の気配を感じた。
グリンは緊張に身構えた。が、そこにいたのは海賊ではなかった。
「お前たち、甲板には出なかったのか」
それは、船内に残っていた若い見習い水夫たちだった。グリンに気づくと、水夫の一人が怯えた様子で近づいてきた。
「ああ、よかった。海賊じゃない。おおい、みんな大丈夫だ」
すると、他にも四、五名の水夫たちが暗がりから集まってきた。彼らは海賊の襲撃を知り、逃げ場をを求めて船倉にやって来て、隠れ場所を探していたのだという。
「なんだか騒がしくなったと思ったら、銃声が聞こえはじめたので、僕らは怖くなって部屋に隠れていたんです。でも部屋にいたんじゃすぐに海賊に見つかってしまうと思って、それでここに……」
「そうだったのか……」
グリンは炊夫たちを見回した。全部で五人、まだあどけない顔をしているが、今は恐怖のためか、皆その顔を青ざめさせている。
「よし、ではこっちに来るんだ」
水夫たちを船倉の奥に連れてゆくと、グリンはそこに並んだ樽を指さし説明した。
「並べられた樽のうち、いちばん奥の列の右端から真ん中までが空の樽になっている。お前達はそこに隠れるといい」
一番前の列の樽は、商船としての見せかけに、果物や酒などが入っている。樽と樽の間隔は、かろうじて人が通れるくらいにしてあった。グリンは、奥の列の樽に水夫たちを誘導した。
「このへんの樽が空のはずだ。さあ、皆、中に入るんだ。すぐに海賊がここにもやってくるだろう。この中に隠れてやりすごし、運がよければ逃げるチャンスが来る。さあ」
おそるおそる、水夫たちが樽の中へ入ってゆく。グリンは彼らを一人ずつ別々の樽へ入れ、蓋を閉めていった。樽には小さな空気穴が開けられていて、窒息の心配はない。
「ちょっと苦しいだろうが、しばらくは我慢するんだ。声も上げるなよ。奴らに見つかって殺されることを考えれば、我慢できるはずだ」
少年たちの怯えきった顔を見ていると、騎士として自分が彼らを守らなければという、強い気持ちが沸いてくる。
全員を樽に入れてしまうと、グリンは自分が入る樽がないことに気づいた。迷ったすえ、彼は手頃な樽を叩いてみて、比較的空洞がありそうなものを選んだ。蓋を開けると、中は腐りかけたチェリーが樽の半分ほど入っていた。顔を近づけると、つんとする嫌な匂いがしたが仕方ない。グリンはその樽に入ることにした。体を丸めればなんとか入れそうだった。
頭の上から蓋を閉めると、樽の中は完全に暗闇になった。鼻をつく腐った匂いに耐えながら、グリンはふうっと大きく息を吐き、目を閉じた。この状態でいつまで辛抱できるのだろう。心の中で不安が込み上げてくる。
そうして、どのくらいの時間が過ぎたろう。
おそらくまだ半刻とはたっていなかったが、狭く息苦しい樽の中にいる者たちにとっては、ひどく長い時間に感じられた。
耳を澄ませると、階段を降りてくる足音が聞こえた。樽の中でグリンは緊張した。少しして、ランタンの明かりが船倉を照らした。
「船室には誰もいなかったし、ここにも誰もいねえ。やっぱり船員どもは殺しつくしたんじゃないですかね、お頭」
声がした。どうやら数人の海賊が船倉に降りてきたらしい。
「ふむ。そうかもしれんな」
聞き覚えのあるドスのきいた声であった。おそらく、それはドルテックのものだろう。グリンは樽の中で息をひそめた。全神経を集中させ、海賊たちの会話に聞き耳を立てる。
「とりあえず、騎士どもの死体はみな海に放り出しときました。降伏した奴らは縛り上げて甲板に転がしときましたし、あとは船ごとかっぱらっていきますかい?それとも積み荷だけいただいて船に火をつけますかい?」
それを聞いて、グリンは身も凍る思いだった。
やはり騎士たちは殺され、船は制圧されたのだ。そして、死体は海に投げ捨てられた……。さらに今度はこの船に火をつけようというのか。そうしたら自分たちは、このまま船倉で生きながら焼かれてしまうだろう。
(くそ……どうしたら)
先程まで忘れかけていた強い恐怖が、再びグリンを襲っていた。どきどきと鼓動が早くなる。それはきっと、隠れている他の水夫たちも同じだったろう。皆、樽のなかで身を縮め、物音を立てないように震えながら、必死に息をひそめているに違いない。
「そうだな……ふむ、それよりも、騎士どもが不穏な作戦を立てているのも気になる。おそらく、商船に偽装しているのはこの船だけじゃねえだろう」
「いくさですかい?騎士ども相手のドンパチ、面白そうだ」
「やりやしょう。頭。犬どもを皆殺しだ!」
海賊たちの物騒な声が、船倉に響きわたる。
「ああ。慌てるな<野郎ども。よし。とりあえずは祝杯だ。このボロ船の制圧記念だ。そのへんにワインの樽があったろう」
「いいですね。今日はしこたま飲みましょうや。犬どもを殺した祝いに」
足音が近づいてきた。海賊たちが樽の前にやってきたのだ。グリンは緊張に身を固くした。
「ええと、確かさっき来たときに、酒の入った樽に印を付けたはず……ああ、これこれ」
「よし、フリッツ。ワインを皆に配ってやれ。一息ついたら、夜明け前までにこの船を出帆させる。見たところ大砲も隠してやがるようだし、ただ燃やすよりはいい戦力になるだろうよ」
「へい」
どうやら海賊たちは酒樽をかついで、そのまま立ち去りそうな様子だった。樽の中で緊張していたグリンは、ほっと息をついた。
だが、そんな安堵も一瞬であった。
「ちょっとまて」
不審そうなドルテックの声に、海賊たちが足をとめた。
「どうしやした?」
「なんだか奥のほうで音がしたぞ」
「なんです?ネズミかなんかじゃないですかね」
「いいや。そうじゃねえ」
海賊はゆっくりと言った。
「その……奥の方の樽だ」
樽の中に身をひそめる、グリンの背中に汗が流れ落ちた。
海賊の足音が、再びこちらに近づいてくる。
「その樽をどかせ……そうだ。おや、こんな奥にもいっぱい樽が並んでいるぜ」
海賊たちの声がすぐ近で聞こえた。グリンは息苦しさに耐えながら、自分の口に手を当て、ひそとも声を立てぬようにした。
「ふむ。……なるほどな」
海賊は、並んだ樽を端からこつこつと叩いていった。
(……)
息をひそめるグリンは、もうこうなったらいっそ飛び出していって、正面から海賊たちと戦ったほうがよっぽどマシなのではないかと考えた。だが、残っている理性がそれをぐっと堪えさせた。
「頭、なにかありますんで?」
「いいや……」
海賊は笑いを含んだような声で答えた。
「別になにもないだろう。だが……そうだな。ちょっと、その樽を撃ってみろ」
「なんですって?」
「その樽を銃で撃ってみろ、と言ったんだよ」
それを聞いたグリンは気を失いそうになった。
(ああ……)
体がぶるぶると震えた。なんということだろう!
「頭、まさかこの中に……」
「さあな。わからん。ただの遊びだ」
海賊は楽しそうに言うと、他の樽も叩きはじめた。
「早く撃て」
「へ、へい」
かちりという音が聞こえ、次の瞬間、船倉に大きな銃声が響きわたった。「ぎゃっ」というかすかな悲鳴が上がるのを、グリンは樽の中で聞いた。
「どうだ?」
「あっ!頭、樽の穴から血が流れてきましたぜ。やっぱり中に誰か隠れていやがったのか」
「ふん。血ではなく、ただのワインかもしれないぞ、それは。くく……試しにその隣の樽も撃ってみろ」
「へへ、おーし」
続いてズカーン、という銃声……そしてまた、押し殺したような悲鳴が上がった。
「おお、こっちも大当たりのようですぜ、頭」
「なるほどな。さあて、次はその隣か……」
「た、助けてくれ!」
樽の中から声が上がった。
「ほうワインが口を聞いたぞ」
ドルテックは面白そうに言った。
「出てきてみろ」
「出る。出るから、助けてくれ!」
若い水夫の悲痛な声に、グリンは樽の中で拳を握りしめた。
「さあ、早く出ろ。みっつ数えたら撃つぞ。ひとつ……」
「ま、待ってくれ、中からじゃなかなか蓋が……」
「ふたつ……」
懸命に開けようとしているのだろう。がたがたと樽が揺れる音がした。
「待ってくれ、今、今出るから、待って……」
「みっつ」
海賊が死刑宣告のように言い放つと、再び恐ろしい銃声が轟き、絶叫にも似た悲鳴が上がった。揺れていた樽が倒れ、ゴロゴロと転がる音が、無残に響いた。
「さあてと、次は……」
海賊は並んだ樽を順番に叩いてゆく。時に残酷な声でそれに話しかけながら。
「入っているかね?おや、これは空っぽかな。では剣を突き刺してみようか」
海賊が樽の板の隙間に剣を突き刺すと、そこから悲痛な呻き声が上がった。それは、別の樽にいるグリンにも、耳を刺すような痛みをともなって聞こえた。
「当たりか。こりゃ、銃を使うより面白いぞ。剣かナイフでいろいろな所から刺してみろ」
「おう。そりゃ面白えや。やろうやろう」
海賊たちはゲラゲラと笑いながら、樽の中の声が弱々しく消えるまで、そこに剣を突きたてていった。
樽の中で膝をかかえながら、グリンは海賊たちの凶悪な行為をその耳に聞き続けた。海賊たちの声や足音のひとつひとつが、たまらなく恐ろしく思われた。彼は、ほとんど発狂しそうなほどの緊張と恐怖とに包まれ、ぶるぶると体を震わせた。
(ああ……ああ!)
すぐそばで、年若い水夫たちが海賊たちになぶられるように殺されてゆく。奴らは笑いながら、ほとんど楽しいゲームでもするように、人が隠れた樽を見つけては、それに銃弾を撃ち込み、剣で刺してゆくのだ。
これは夢だ。はやく終われ、とグリンは思った。
あるいは、この樽から飛び出せば、なんとかして逃げ延びることができるのではないかという考えが、ときおり彼を捕らえた。だが、かろうじて残っている冷静な思考が、それを押し止めた。今出てゆけば、待っているのは確実な死なのだ。
もう一つ、死の恐怖に対してかろうじて発狂せずにいられたのは、他ならぬ騎士としての誇りと、そして己の任務への責任のためであった。なんとしてでも生き延びるのだ。艦長から託された使命をまっとうするのだ。それまでは、決して自ら死を選んだりはしない。
グリンの中のその燃えさかる使命感は、不安げに揺れ動きながらも、決して消えることはなかった。
「さて、他に怪しい樽はあるかな」
まるで宝探しでもあるかのように、海賊は並んだ樽をこんこんと叩いていった。グリンは、樽の中で身じろぎひとつせず、じっと息をひそめ続けた。
海賊の足音が近づいてくると、彼の背中に冷たい汗が流れ落ちた。髪の毛が逆立つほどの緊張と恐怖心で、彼の顔は引きつり、ひどく青ざめていたに違いない。
ついにグリンの入った樽が叩かれた。思わず目を閉じたグリンは、海賊の剣先が、自分の体を貫くことを想像した。
「ふむ……こいつはいかんな」
「どうかしやしたか?頭」
他の海賊たちも、樽の近くに集まってきた。
「そら、匂うだろう」
「はあ、そういや臭いですな」
「腐ってるんだ。チェリーかなんかだろう」
ガツンと樽が蹴飛ばされた。中にいるグリンはびくりとしたが、かろうじて声は上げなかった。
「あとで海に捨てておけ。いいな」
「へい」
そのまま海賊が通りすぎると、グリンは今度こそほっとした。こんなに恐ろしい目にあったことは、生まれてこのかた初めてだった。それからはただ、海賊たちが船倉を出てゆくまで、彼は樽の中で身を丸くして待ちつづけた。
海賊たちの足音が消えてしばらくしても、グリンは樽の外には出なかった。完全に人の気配が消えたのを待って、ゆっくりと樽の蓋を持ち上げてみる。
「……」
船倉は暗がりに包まれていた。とはいっても、樽の中にいるよりはずっとよく周りが見えた。音を立てぬようにグリンはそっと樽から抜け出た。床に降り立つと、今更ながら先程の恐怖に体ががたがたと震える気がしたが、ぎゅっと歯を食いしばると、彼は他の樽を調べはじめた。
水夫たちが隠れていた樽は、見るも無残な状態だった。銃で撃たれた樽からは血が流れ出し、中からはもう呻き声すら聞こえなかった。その他にも、何発もの弾を受けて壊れかかった樽、剣やナイフを突き刺された樽など、水夫たちが隠れた樽は、そのほとんどがやられていた。
「う……」
グリンは思わずしゃがみこみ、込み上げてくるものに嗚咽した。だが、それを堪えてすぐに立ち上がると「誰か、いないか?声を出せるものはいないか?」と、樽の周りを歩きながら呼び続けた。しかし、どの樽からも声は聞こえず、静まり返った船倉には、グリンの声だけがむなしく響いた。
(みんな……やられたのか)
樽を開けて、水夫たちの死体を確認する勇気はなかった。グリンは床に座り込み、しばらく呆然としていた。
だが、ここにこうしていても何も始まらない。そして、自分には重要な任務が残っているのだ。
「……」
ぐっと口を引き結び、立ち上がったグリンは、並んだ樽を振り返って黙祷を捧げた。それから船倉を出ようとしたが、一瞬考えると、彼はやにわに、さっきまで自分が隠れていた樽を担ぎ上げた。
船倉を出て、辺りに人けがないことを確認しながら、樽を担いで階段を上がる。近くに海賊たちのいる気配はなかった。おそらく、奴らは甲板でのんびりと酒でも飲んでいるのだろう。
額に汗をにじませながら、グリンは重い樽を運んで歩いていった。
船尾にある船長室の扉を開けると、
「さあ、勇気を出すんだ」
自分に言い聞かせるようにそうつぶやき、彼は樽を置いて、身につけていた上着を脱ぎ始めた。ベルトや靴など、重いものは全てはずした。それから、懐に隠してあった鎖のついた銀のコンパスを首にかけると、張り出し窓の前に樽を運んだ。
窓を開けると、冷たい海風が波しぶきとともに、彼の顔を吹きつけた。暗い海には、ザーン、ザザーンという波音が響きわたり、海面を見下ろすグリンの心をおびやかすようだった。
夜明けまではまだ、もう少し時間があるだろう。この暗さなら見つかりはすまい。
グリンは運んできた樽を両手で持ち上げると、それを思い切り窓に放り投げた。窓枠ごとガラスが砕け散り、樽は海に落ちていった。
「よし……」
ぷかぷかと海面に浮かぶ樽を見つめ、何度か深呼吸をすると、彼は窓枠に足をかけた。
次の瞬間、グリンは夜の海へ飛び込んでいた。
黒々とした海面に吸い込まれてゆく恐ろしさも、今の彼にはたいした恐怖ではなかった。ざばんと音を立て、海中に体が潜った。
水は冷たく、そして、波は想像以上に荒かった。何度も頭から波をかぶり、水を吐き出しながら、グリンは必死に泳いだ。
こんな所で死んでたまるか。自分は騎士であり、そしてもう、一人前の船乗りでもあるのだ。己を支える唯一のその思いが、彼の両手両足を動かし続けた。
目の前に浮かんでいる樽が見えると、力を振り絞って、グリンはそれにしがみついた。
見上げると、タンタルス号の甲板上には明かりが見えた。窓を割った音で、海賊たちが気づいたのだろう。
グリンは両手で樽を抱えながら、船から遠ざかろうと両足で海面をかきだした。
うっすらと、空の彼方が白みはじめている。
海に飛び込んだ若い騎士の運命を知るものは、もうタンタルス号にはいない。
艦長や、他の仲間たち……それに、恐ろしい海賊たちの声、戦い、銃声と悲鳴……
それらがいっぺんに、頭の中で現れては消える。
そして、すべてはやがて、波の音へ飲み込まれていった。
■次ページへ